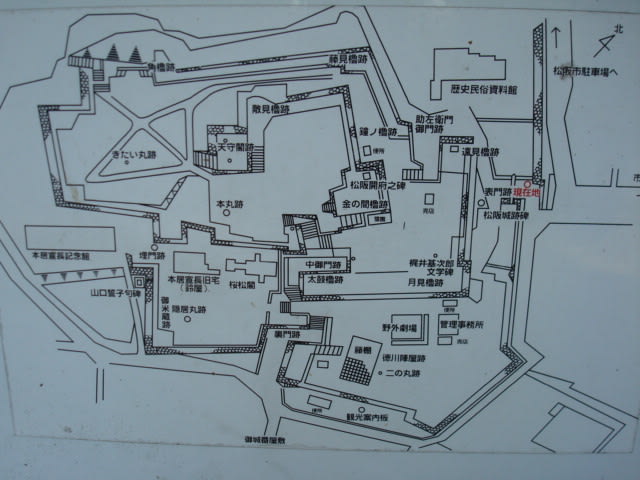2011年3月25日(金)
前日(24日)は松阪から18きっぷで伊勢市まで行き、伊勢市駅の近くのホテルに宿泊。翌日の25日に二見浦に行きました。目的は夫婦岩拝見と二見玉腰神社の御朱印を頂きに。
帰りに撮った写真になりますが

のんびりとした雰囲気でした。

↑ 夫婦岩をモチーフにした駅舎。なかなか洒落てますよね。

↑ 道路を渡ると白い鳥居があり、夫婦岩表参道から撮ったものになります。

↑ 二見町のマンホール。町のシンボルの夫婦岩と町の花ひまわりがデザインされています。
前日(24日)は松阪から18きっぷで伊勢市まで行き、伊勢市駅の近くのホテルに宿泊。翌日の25日に二見浦に行きました。目的は夫婦岩拝見と二見玉腰神社の御朱印を頂きに。

帰りに撮った写真になりますが

のんびりとした雰囲気でした。

↑ 夫婦岩をモチーフにした駅舎。なかなか洒落てますよね。

↑ 道路を渡ると白い鳥居があり、夫婦岩表参道から撮ったものになります。

↑ 二見町のマンホール。町のシンボルの夫婦岩と町の花ひまわりがデザインされています。











 何匹か居ると怖いです。まぁ、私よりもカラスの方がびっくりして飛び立ちましたけどね…。
何匹か居ると怖いです。まぁ、私よりもカラスの方がびっくりして飛び立ちましたけどね…。