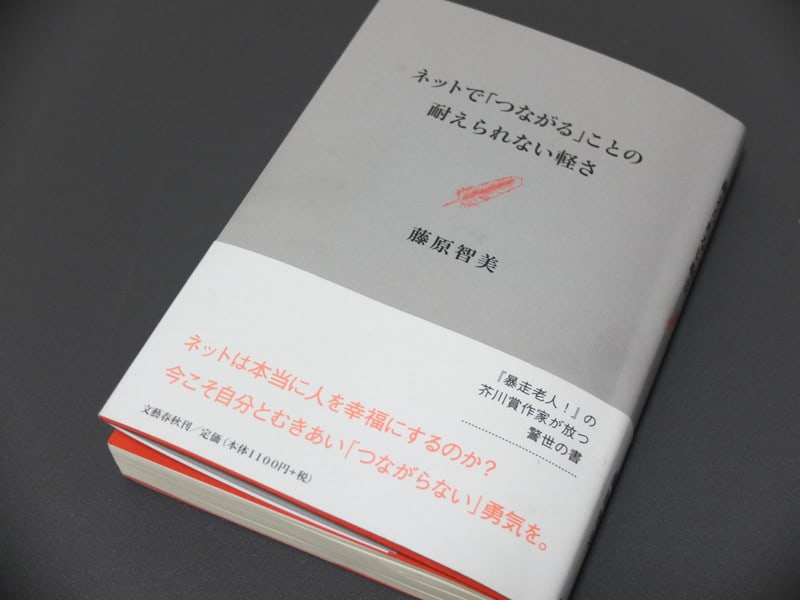少し古い話題で恐縮です。
先日、2011年の11月に追手門大学の建学45周年行事において神戸女子学院大学教授(当時)の内田樹(うちだ・たつる)氏が行った、「大学における教育-教養とキャリア」と題する講演の講演録を目にする機会がありました。
内田氏はこの講演において、明治維新後の日本において「教養」とか「一般教養」などと訳されてきた大学での「リベラルアーツ教育」に関して興味深い視点を投げかけています。
講演の中で内田氏は、「教養」は「知識」とは異なる概念だとしています。氏が示しているのは、知識の一歩手前の「知性」を活性化させるための技術、これが「教養」の本質であるという認識です。
一般に(英語では)、この「技術」のことをリベラルアーツと呼んでいると内田氏は言います。そして、「知は人をして自由を得さしむ」という聖書の言葉を引き、「人を自由にする知の技術」、まさにそれがここで言うところの「教養」であるというのが氏の講演の本旨となります。
さらに講演の中で内田氏は、高等教育機関である大学の目指すべきことは実は一つしかないと指摘しています。そしてそれは、「どうしたら学生たちの知性が活性化するか」について創意工夫を凝らすことであり、学生が知的に前のめりになって自らの力で「もっと知りたい」と思うように導くことだということです。
その目的に焦点化して行う教育こそが「リベラルアーツ」である。別に「総合的な科目」としての「教養」があり、これを総合的に勉強することがリベラルアーツではない。リベラルアーツは「知識」ではなく「目的」であるというのが内田氏の強く主張するところです。
さて、元NHKのアナウンサーでジャーナリストの池上彰氏は、最近出版された著書「おとなの教養」(NHK出版新書)において、日本のリベラルアーツ教育に対し内田氏のこうした認識と共通する視点からひとつの疑問を投げかけています。
池上氏によれば、そもそもリベラルアーツとはギリシャ・ローマ時代に源流を持つ「学問の基本」と位置付けられた7科目のことを指す言葉だということです。具体的には、①文法、②修辞学、③論理学、④算術、⑤幾何学、⑥天文学、⑦音楽に関する7つの教養であり、かつてはこれらの科目に習熟することが教養人の要件であったということです。
リベラル(liberal)は「自由」であり、アーツ(arts)は技術、学問、芸術などと訳されていることからも分かるように、リベラルアーツは「人を自由にするための技術(学問)」であると池上氏はしています。こういう技を身に着けていれば、人は様々な偏見や束縛から逃れ、自由な発想や嗜好を展開していくことができる。池上氏が示しているのは、(内田氏とも共通する)そうした認識です。
実際、アメリカのハーバード大学の学部教育の基本は、このリベラルアーツであると池上氏は言います。ハーバードでは、通常4年間のリベラルアーツ教育を受けたうえで、医者になりたい者はその後メディカルスクールで専門の技術や知識を学び、法律家を目指すものはロースクールに進み、経営学を学びたかったらビジネススクールへ行くことになる。
マサチューセッツ工科大学のような科学技術の先端を行く(理系の)大学やボストンのエリート女子大ウェルズリーカレッジなどでも基本的に同じシステムを採用している。実は、世界基準での「エリート」を養成する大学の「学部」は技術を学ぶところではなく、「もの」を考えるためのベースを学ぶ場(段階)として位置付けられていると、池上氏は改めて指摘しています。
一方、現代日本においては、特に昨今、大学新卒者に対し「即戦力」となることが求められるようになってきています。企業や政府は大学に対し、声をそろえて「社会に出てすぐに役に立つ学問」を教えてほしいと要請しているようです。
しかし、これだけ市場優先主義が徹底されているアメリカであってさえも、実はすぐに役に立つ知識や技術を教えるのはあくまで「専門学校」であり、いわゆるエリート大学は、「すぐに役立たなくてもいいこと」を教えているということを、著書の中で池上氏は強調しています。
「すぐに役に立つことは、世の中に出てすぐに役に立たなくなる。すぐに役には立たないことが、実は長い目で見ると役に立つ」と池上氏は言います。そこにあるのは、本当の「教養」というものは長い人生を生きていく上で自分を支える基盤になる存在であり、その基盤さえしっかりしていれば世の中の動きにブレることなく自分の頭で道を切り開いていけるという視点です。そして、現代において求められている「教養」とは、そういうものではないかというのが池上氏の認識です。
知性は、自分を閉じ込めていた知の檻から逃れ出たいという欲望が起動した時に生まれると、前述の講演において内田氏は言っています。自分自身が何を知っており、何を知らないのか。さらに、何を知らなければならないのかについて俯瞰的に見ることのできる力、それが本来の知性のかたちであり、リベラルアーツ教育が目指しているものだというものです。
自らを知り、社会を知り、状況を切り開いていく力を「教養」(リベラルアーツ)」がもらたしてくれるという二人の論客のこうした指摘を、約3年という年月を挟んで、この機会に私も大変興味深く読んだところです。