レミ講座の詳細レポートです。
予定は
・『レ・ミゼラブルとは』
・歌唱指導
・ワークショップ
・おまけ
です。
まずは垣ヶ原さんによる『レ・ミゼラブル』の説明から。
フランスのオリジナルミュージカルを作ろう、ということでこの作品が選ばれたとか。
フランス人が大切にしている作品、フランス人なら誰もが知っている作品、いわば『国の誇り』ともいえる作品だから選ばれたとのこと。
作曲者のクロード=ミシェル・シェーンブルクは譜面を読むことも書くこともできないそうです。
頭に浮かんだ旋律をそのままピアノで弾き、時には自分で歌うこともある。
これは1910のさおり先生から聞いたことあったんで「ふんふん」と聴いてました。
やがてその時代背景や人物の説明へ。
日本初演時は天安門事件の年でもあり、観客も役者もそのことを念頭においていたとか。
俳優さんたちは『19世紀初頭』という過去の話ではなく、『20世紀後半』という現在をも演じていた、ともいえる。
それは21世紀に入った今も、どこかで革命が起こり、貧しい人々が犠牲になる『21世紀初頭』を演じることでもある。
各人物について。
農業国フランスではパンでお腹を満たしていたそうです。
(そういや当時1日1キロものパンを食べていたと何かで読んだ記憶がある)
そんな状況でヴァルジャンが犯した罪――パンを1つ盗むということはどういうことなのか?
ちょっと考えればわかりますな。
たとえ犯罪者に転落したとしても、生きていくためには、養っていくためには、そうせざるを得なかったのだ。
ジャヴェールとは何者か?
彼は警察官という、罪を犯した人とかかわる仕事についている。
彼の出生――牢獄で生まれ育ったということを考えると、「俺はこうはならないぞ」という強い信念があったからこそ、法律がすべてという考えの持ち主になったんじゃかなろうか。
そんなジャヴェールを汚れた人(=罪人)とかかわる、忌まわしい存在として嫌う市民たち。
逆に、法律を破って生活しているテナルディエとその仲間(パトロン・ミネット)は、彼に捕まったら次はないと考えていた。
マリウスは貧乏だけど、裕福な家庭で育った。爵位も持っている。
しかし自ら家を飛び出し、服や時計を売り、翻訳の仕事をするようになる。
(実際はクールフェラックが世話をしたんだけどね)
同時に大学で勉学に励み、やがて弁護士になる。
彼は大学に通えるほど頭が良くて、女性が見とれるほど格好いい。背筋も伸びて五体満足、髪や歯も清潔だ。
マリウスは裕福な生活と貧しい暮らしの両方を知っている。だからこそ、革命へと突き進んでいく。
(原作では消去法で選んだ道だけど)
アンジョルラスをはじめ、学生たちはパリに出て来て初めて華やかな都市の裏側にある惨状を目の当たりにする。
学生といっても若い人ばかりではなく、初登場時は最年少クールフェラック(21歳)、次いでアンジョルラス・コンブフェール・プルヴェール(22歳)、ジョリ(23歳)、レーグル(25歳)。全員マリウスより年上だ。
グランテールにいたっては年齢(本名も)不詳、ミュージカルには出て来ないバオレルは11年学生を続けている。
フイイは扇子職人。ミュージカルではそれから大学に入り直したという設定だけど、原作では学生ではない(確か)。
そんな彼らが「なんとかしなくては」と思って立ち上げたのが『ABCの友(Les amis de l'ABC)』。
貧しい人々に読み書きを教え、かつ生活基盤をなんとかしようという秘密結社だ。
当時都市に住んでいた女性たちは?
ファンティーヌのようなお針子をはじめ、女中や修道女(当時は教師や看護婦の仕事もこなしていた)、買い入れ屋やかつら屋、女優の端くれに乳母や門番、そして売春婦……。
マテロットやジベロットのように酒場で働けたらまだマシだっただろう。
中にはマドレーヌのような娼婦や物乞いに身を落とした人だって、きっといたはずだ。エポニーヌも春をひさいでいた可能性は捨てきれない。
そんな中、コゼットは修道院で教養を身につけられた。これはもちろん、ヴァルジャンが働いて築き上げた財産によるものだ。
マリウスとコゼット、アンジョルラスを初めとする『ABCの友』とベガーズは一体どこが違うんだろう?
これがのちのワークショップへ繋がっていきます。
さて、この『レ・ミゼラブル』の世界を表現するため、衣装は当時と同じ素材を使うことを求められたとのこと。
日本では手に入りづらい厚手の生地を入手するのに苦労し、帽子の高さもフランスやイギリス人に合う高さから日本人に合う高さに変えるよう説き伏せたこともあるとか。
歌詞の翻訳も大変だったそうで、「1音につき1音節」を守るために相当苦労したらしい。言語学を学ぶ人間としてはその苦労は察するに余りある。
役者さんたちも、歌詞を翻訳して台詞に直し、読み合わせをして自分が何を伝えようとしているかという作業もしたようです。
(それがフランス語からなのか英語からなのかが気になるが、ここでは問題にしない)
美しい男女が出会い、恋に落ちる。結末は必ずハッピーエンド。
それは、ミュージカルでは王道だったストーリー。
この作品は同じく『愛』をテーマにしながらも、恋愛だけではなく親子愛、友愛、郷土愛――語弊を恐れずに言えば、『博愛』の精神を貫いたもの。
社会の底辺に生きる人々や、彼らが流した多くの血と涙を描いた作品。
それこそ、『レ・ミゼラブル(Les Miserables)』――『惨めな人々』――という作品なのです。
予定は
・『レ・ミゼラブルとは』
・歌唱指導
・ワークショップ
・おまけ
です。
まずは垣ヶ原さんによる『レ・ミゼラブル』の説明から。
フランスのオリジナルミュージカルを作ろう、ということでこの作品が選ばれたとか。
フランス人が大切にしている作品、フランス人なら誰もが知っている作品、いわば『国の誇り』ともいえる作品だから選ばれたとのこと。
作曲者のクロード=ミシェル・シェーンブルクは譜面を読むことも書くこともできないそうです。
頭に浮かんだ旋律をそのままピアノで弾き、時には自分で歌うこともある。
これは1910のさおり先生から聞いたことあったんで「ふんふん」と聴いてました。
やがてその時代背景や人物の説明へ。
日本初演時は天安門事件の年でもあり、観客も役者もそのことを念頭においていたとか。
俳優さんたちは『19世紀初頭』という過去の話ではなく、『20世紀後半』という現在をも演じていた、ともいえる。
それは21世紀に入った今も、どこかで革命が起こり、貧しい人々が犠牲になる『21世紀初頭』を演じることでもある。
各人物について。
農業国フランスではパンでお腹を満たしていたそうです。
(そういや当時1日1キロものパンを食べていたと何かで読んだ記憶がある)
そんな状況でヴァルジャンが犯した罪――パンを1つ盗むということはどういうことなのか?
ちょっと考えればわかりますな。
たとえ犯罪者に転落したとしても、生きていくためには、養っていくためには、そうせざるを得なかったのだ。
ジャヴェールとは何者か?
彼は警察官という、罪を犯した人とかかわる仕事についている。
彼の出生――牢獄で生まれ育ったということを考えると、「俺はこうはならないぞ」という強い信念があったからこそ、法律がすべてという考えの持ち主になったんじゃかなろうか。
そんなジャヴェールを汚れた人(=罪人)とかかわる、忌まわしい存在として嫌う市民たち。
逆に、法律を破って生活しているテナルディエとその仲間(パトロン・ミネット)は、彼に捕まったら次はないと考えていた。
マリウスは貧乏だけど、裕福な家庭で育った。爵位も持っている。
しかし自ら家を飛び出し、服や時計を売り、翻訳の仕事をするようになる。
(実際はクールフェラックが世話をしたんだけどね)
同時に大学で勉学に励み、やがて弁護士になる。
彼は大学に通えるほど頭が良くて、女性が見とれるほど格好いい。背筋も伸びて五体満足、髪や歯も清潔だ。
マリウスは裕福な生活と貧しい暮らしの両方を知っている。だからこそ、革命へと突き進んでいく。
(原作では消去法で選んだ道だけど)
アンジョルラスをはじめ、学生たちはパリに出て来て初めて華やかな都市の裏側にある惨状を目の当たりにする。
学生といっても若い人ばかりではなく、初登場時は最年少クールフェラック(21歳)、次いでアンジョルラス・コンブフェール・プルヴェール(22歳)、ジョリ(23歳)、レーグル(25歳)。全員マリウスより年上だ。
グランテールにいたっては年齢(本名も)不詳、ミュージカルには出て来ないバオレルは11年学生を続けている。
フイイは扇子職人。ミュージカルではそれから大学に入り直したという設定だけど、原作では学生ではない(確か)。
そんな彼らが「なんとかしなくては」と思って立ち上げたのが『ABCの友(Les amis de l'ABC)』。
貧しい人々に読み書きを教え、かつ生活基盤をなんとかしようという秘密結社だ。
当時都市に住んでいた女性たちは?
ファンティーヌのようなお針子をはじめ、女中や修道女(当時は教師や看護婦の仕事もこなしていた)、買い入れ屋やかつら屋、女優の端くれに乳母や門番、そして売春婦……。
マテロットやジベロットのように酒場で働けたらまだマシだっただろう。
中にはマドレーヌのような娼婦や物乞いに身を落とした人だって、きっといたはずだ。エポニーヌも春をひさいでいた可能性は捨てきれない。
そんな中、コゼットは修道院で教養を身につけられた。これはもちろん、ヴァルジャンが働いて築き上げた財産によるものだ。
マリウスとコゼット、アンジョルラスを初めとする『ABCの友』とベガーズは一体どこが違うんだろう?
これがのちのワークショップへ繋がっていきます。
さて、この『レ・ミゼラブル』の世界を表現するため、衣装は当時と同じ素材を使うことを求められたとのこと。
日本では手に入りづらい厚手の生地を入手するのに苦労し、帽子の高さもフランスやイギリス人に合う高さから日本人に合う高さに変えるよう説き伏せたこともあるとか。
歌詞の翻訳も大変だったそうで、「1音につき1音節」を守るために相当苦労したらしい。言語学を学ぶ人間としてはその苦労は察するに余りある。
役者さんたちも、歌詞を翻訳して台詞に直し、読み合わせをして自分が何を伝えようとしているかという作業もしたようです。
(それがフランス語からなのか英語からなのかが気になるが、ここでは問題にしない)
美しい男女が出会い、恋に落ちる。結末は必ずハッピーエンド。
それは、ミュージカルでは王道だったストーリー。
この作品は同じく『愛』をテーマにしながらも、恋愛だけではなく親子愛、友愛、郷土愛――語弊を恐れずに言えば、『博愛』の精神を貫いたもの。
社会の底辺に生きる人々や、彼らが流した多くの血と涙を描いた作品。
それこそ、『レ・ミゼラブル(Les Miserables)』――『惨めな人々』――という作品なのです。










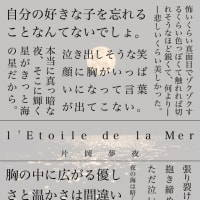















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます