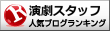寒い冬。そう天候には恵まれないなか、たくさんの観客の皆様にきて270名だそうである。私は仕込みと最終日の会場整理、バラシしか参加させていただいていないが、練習も2回見させていただいて、芝居の過程もいっしょにいながら、今回参加させていただいた。
全体としては尼崎のオリジナルイメージ世界は現実に刃物をつきつけて向き合っている。先輩の芝居人に怪我をされながらも来ていただいて
帰りに現代のアングラやなといい意味で感想をいっていただけた。
現場の人間なので、客観的にいうのも、変なのだが、劇日誌なので、
思ったことをかくと、現実に生きることの、こころのやみを刃物をもちつづけるぐらい怖い存在として、若いこれからのひとを世界をイメージしていること。それは決していまの社会に迎合いれることを悩むこと。
この真摯さがひしひしと伝わってくる。それはこんなにちまたには変なその当事者たちはもう回復できないぐらい事件があふれるぐらいにあるのに変なとか、自分たちとは違うという、日常生活安心感のなかで、どうしても、排除して忘れてしまう。さらに、芝居は最近そういうことすらタブー視する感があったりする。そんなことには関係ないぐらい、いこうとしている。今回ももう私たちでは救えないことなのだ。それにゆるせないと思う気持ちそれはとても大切なことだ。そして、それはもうしかしてじぶんたちのこころのなかにあることなのだとつきつけてくる。
その作品世界を鉄パイプをつりさげ、大型スピーカーとテレビで簡素なかわいた世界。音や映像もたくみに使い、臨場感ある舞台をつくっていた。
そのなかで役者たちは大変であっただろう。それは作者の世界を自分はどう思い、自分のものとして変換させるのか(唐十郎いわく誤読)。
それが、ステージごとに波があったということは、役者のつくりだす共同幻想の世界はぬけきれていないものだったかもしれない。
この芝居をみたあと、観客は感情があふれてくるのだとおもう。そんな舞台へとさらに、変わっていくだろう。そのてがかりの舞台であったと感じた。

全体としては尼崎のオリジナルイメージ世界は現実に刃物をつきつけて向き合っている。先輩の芝居人に怪我をされながらも来ていただいて
帰りに現代のアングラやなといい意味で感想をいっていただけた。
現場の人間なので、客観的にいうのも、変なのだが、劇日誌なので、
思ったことをかくと、現実に生きることの、こころのやみを刃物をもちつづけるぐらい怖い存在として、若いこれからのひとを世界をイメージしていること。それは決していまの社会に迎合いれることを悩むこと。
この真摯さがひしひしと伝わってくる。それはこんなにちまたには変なその当事者たちはもう回復できないぐらい事件があふれるぐらいにあるのに変なとか、自分たちとは違うという、日常生活安心感のなかで、どうしても、排除して忘れてしまう。さらに、芝居は最近そういうことすらタブー視する感があったりする。そんなことには関係ないぐらい、いこうとしている。今回ももう私たちでは救えないことなのだ。それにゆるせないと思う気持ちそれはとても大切なことだ。そして、それはもうしかしてじぶんたちのこころのなかにあることなのだとつきつけてくる。
その作品世界を鉄パイプをつりさげ、大型スピーカーとテレビで簡素なかわいた世界。音や映像もたくみに使い、臨場感ある舞台をつくっていた。
そのなかで役者たちは大変であっただろう。それは作者の世界を自分はどう思い、自分のものとして変換させるのか(唐十郎いわく誤読)。
それが、ステージごとに波があったということは、役者のつくりだす共同幻想の世界はぬけきれていないものだったかもしれない。
この芝居をみたあと、観客は感情があふれてくるのだとおもう。そんな舞台へとさらに、変わっていくだろう。そのてがかりの舞台であったと感じた。