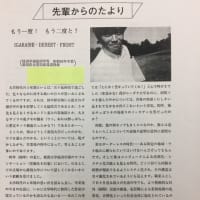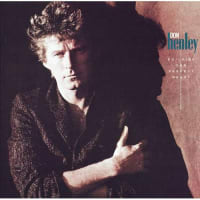< 仕事観の形成と就職するまで編9>---------------------
●広告代理店営業
当時、多くの学生に見られたパターンと同様に、就活を勘案して私も大学卒業に必要な単位は殆ど3年生で取り終えて、週に1日のゼミナール1コマのみの登校となる4年生への進学を目前にしていた。そんな春休みを迎えるかの頃、知人のつてで大手広告代理店の新潟支店でのアルバイトの誘いがあった。
新潟駅前の貸しオフィスビルの4階フロアに東京から進出してきたばかりの事務所を訪れると、15人ほどの職員が3つほどのグループに分かれて机に座り、窓際に配列された2席に座る上司と思しき人達とともに忙しそうに電話応対や事務仕事、打合せなどをしていた。就職情報を扱うこの企業は、数日前に新潟大学生数人に就活に関するアンケートを行っており、それに答えた中から私にアルバイトの声を掛けてきたのだ。"営業に関心あり"との記述が注目されたのかもしれない。
スカウト役の職員は「新潟に少数で進出してきたばかりでマンパワーに余裕が無い。補助的なアルバイトというよりフルタイムで正規職員並に働けないか」という。4年生だと殆ど登校不要ということをお見通しのようだ。授業のある日を除く月曜から金曜まで9:00から17:00のフルタイム、レンタカーを使って、新潟県内の指定された100箇所程の事業所を自ら計画して順次回り、社の出版物の職員達への配布受諾や広告出しの御用聞きに回るという業務だ。そんな経緯で、新潟の主要道路が雪解けする2月下旬から、かねて興味のあった営業の体験が始まった。
フルタイムだとはいえ大学生に預ける仕事として内容と程度は良く考えられていたようだ。指定された訪問先は温厚に対応してくれる所が多く、出版物を案内したり広告掲載を取り付けたりする仕事そのものは特に困難ではなかった。それまで経験してきたバイトでの不条理なクレーム対応などと比べれば、広告出稿に係る費用対効果などを論理的に説明したり交渉したりする仕事は面白いものであった。
また、営業訪問先は新潟県内の当時112もあった市町村にあまねく及ぶもので、レンタカーという移動手段も相まって、このバイトを通じて収入を得ながら図らずも、新潟県土のほとんど全てを見て回ることができた。生まれてこのかた大学まで、一貫して新潟県内であったものの、中学で部活、高校で受験勉強、大学に進学してからはサークルやバイト三昧という生活の中で、殆ど知る機会の無かった海、山、川に島まで抱えて面積も広く形も間延びした新潟県の各地域について、見聞を高めることができた。この時に得た土地勘や知見は、就職してから今日まで仕事や生活に大いに活かせる私の知的財産となっている。
さらに得るものが多かったのは、東京本社との交流であった。2週に1度ほど、金曜の夕方から銀座の本社に関東甲信越各地の担当が招集されて打合せが行われた。午後過ぎまで新潟県内で営業回りをして午後3時頃に新潟発の新幹線に飛び乗って上京した。本社での打ち合わせの相手方は、大卒後20代前半の正規職員達が殆どだったのだが、生き馬の目を抜くような東京暮らしの連中とのやり取りは、当時の私に大変な刺激になった。
彼らは、仕事ができそうだという良い意味で、目つきがギラついており、会話のテンポと頭の回転が速い。偏差値が高いというよりも"世間ずれ"というか"狡猾"というか、とにかくうかうかしていられない気分にさせるほぼ同世代の若者たちだった。田舎の大学でのんびり暮らしの私は、例えば都内の企業あたりに就職すると、こんな強かで"すばしこい"連中と職場で競り合うことになるのか…と恐れに近いものを抱いたものだ。
かくして、大手広告代理店での数か月にわたる経験を通じて、営業活動の勘所も面白味も体得できたが、図らずも、当たり前のように考えていた民間企業への就職という考え方について、自らに再考を迫る思いが沸々と湧き上がってきた。大学まで出るのだから都内の大手企業も目指す選択肢と考えていたものの、少し情けないが、"東京組"と太刀打ちできるのかという弱気と、新潟県内をつぶさに車で見て回る中で、生まれ育った土地を良く知りもしないままに、ただ出て行くだけで良いのかな…というモヤモヤ感が募ってきたのだ。
(「仕事観の形成と就職するまで編9」終わり。「仕事観の形成と就職するまで編10「県勢への貢献に帰結」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。