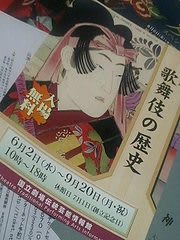国立劇場伝統芸能情報館で、企画展の「歌舞伎入門 歌舞伎の歴史」が開催中。
出雲の阿国から始まる歌舞伎の誕生から現代までを
5つの時代にわけて衣装や錦絵などで解説している。
400年以上の歴史を誇る歌舞伎も
1603年に阿国が現れてから、すぐに遊女歌舞伎や若衆歌舞伎が現れ、
それらの禁止によって野郎歌舞伎の時代になるが
「物真似狂言」を演ずべきという制約のもとに「劇」という形態ができる
1700年以降である元禄時代に花開き現在にいたるようだ。
墨絵に手彩色した丹絵で初代團十郎を描いた「竹抜き五郎」(鳥居清倍)
京都万太夫座の役割番付(けいせい壬生大念仏)
三大名作の錦絵や漆絵…
九代目團十郎や五代目菊五郎の押隈などが展示されている。
映像資料では、昭和53年製作の「歌舞伎の魅力 演技」が上映されており
先代勘三郎の直次郎と当代菊五郎の遊女三千歳の逢瀬のシーンを
少しだけだが嬉しく拝見した。
出雲の阿国から始まる歌舞伎の誕生から現代までを
5つの時代にわけて衣装や錦絵などで解説している。
400年以上の歴史を誇る歌舞伎も
1603年に阿国が現れてから、すぐに遊女歌舞伎や若衆歌舞伎が現れ、
それらの禁止によって野郎歌舞伎の時代になるが
「物真似狂言」を演ずべきという制約のもとに「劇」という形態ができる
1700年以降である元禄時代に花開き現在にいたるようだ。
墨絵に手彩色した丹絵で初代團十郎を描いた「竹抜き五郎」(鳥居清倍)
京都万太夫座の役割番付(けいせい壬生大念仏)
三大名作の錦絵や漆絵…
九代目團十郎や五代目菊五郎の押隈などが展示されている。
映像資料では、昭和53年製作の「歌舞伎の魅力 演技」が上映されており
先代勘三郎の直次郎と当代菊五郎の遊女三千歳の逢瀬のシーンを
少しだけだが嬉しく拝見した。