セロニアス・モンクはアート・ペッパーをどう評したか?
この動画、腑に落ちる所が満載。モンクがペッパーをディスってるって内容(僕にとっては一寸悲しい)になるんだけど、それ以上に「ストックフレーズ」所謂「リック」について話が及んでいるのも面白い。以前僕が「リックって?」で書いた内容に通ずるものでもある。
また、大きく「実務家タイプ」と「経営者タイプ」に分けた話も面白い。話を聞いてると、僕は明らかに経営者タイプで、バンドを会社に例えて、バンドの方向性=経営方針を先ずは考え、音楽を俯瞰で観てアプローチしたりメンバーに指示するというやり方。一方、実務家タイプは、曲に対する処理能力がとにかく高くて速いという事らしい。まぁ、超個人主義という事か。そこで、処理能力の速さには「ストックフレーズ」がどうしても必要になる…という話に繋がる。それがペッパーって事になるんだけど、僕自身はあまりそうは思わない。ことバラードプレイに関しては寧ろソニースティットの方がそのタイプだと考えている。
まぁ、お話の中でこの方がおっしゃる通り、必ずしも「これらのタイプのどちらか」という訳ではなく、どちらの要素が強いか?という事だろう。
僕自身もNY時代は、仕事を得る為に処理能力を上げる必要が有り、リックを溜め込んだ時期が有る。特に日本では、多分に処理能力の速さを求められる傾向に有る。仕方ないので、そういう演奏をする事も多いが、そういう意味では、どちらかと言うと音楽的にはジャズというよりクラシック的だと思う。その場その場のクリエイティビティより澱みなさを求められる感じ。
ただ、僕は極端な「飽き性」なのだ。同じ事を繰り返す行為がとても嫌いで、常に現場で何か新しい事を追い求める傾向に有る。それは、音のチョイスに迷いや躊躇を生じさせ、とてもリスキーな事だし、練習で得られるものでは無い。(練習と言えば、どちらかと言うと楽器の練習より音感の訓練の方がメインになる。) でも、スリリングで楽しいものなのだ。こういうアーティストは恐らく日本では嫌われる傾向にあり、仕事を得るのは困難だと言える。だから、上手くバランスを取る事が肝要となって来る。
以前から、「クラシックは落語、ジャズは漫才」と例えて来たが、それは、クラシックは決まり切った噺を如何に個人的な情感を込めて語れるか?であり、一方ジャズは会話形式であり、日常的な言葉のキャッチボールを楽しむものだ…と考えていたからだ。
でも、僕のその考えを一変させたのが、天才落語家の桂枝雀だ。登場人物にアドリブで不規則発言をワザとさせ、自分自身の躊躇や迷いで困惑しながらも噺を展開させてオチに持って行くというやり方。これは、明らかにジャズのインプロビゼーションにあたる。しっかりと基礎的なアウトラインを踏まえながらも古典落語を創作落語に近い所まで昇華させる、僕にとっては理想的な形だ。ただ、枝雀は余りにも芸にストイックで鬱病になり自殺してしまうのだが。
漫才で言うと、中川家がそれに近く、毎回、ネタの内容が微妙に変わって行くのだが、それは兄・剛が実はコンビでもイニシアチブを持っており、方向性が毎回変化し、それに弟・礼二が付き合っているらしいのだ。台本は有って無い様なものだという。漫才は二人で息を合わせる必要が有り、至難の技の筈だ。ジャズのバンド・エクスプレッションから考えるとこれも理想像だ。
この二つの例で共通しているのは、明らかに「飽き性」という事だ。決まり切った事をそのまま人前でやる事に価値を感じ無いという事になる。
僕もこの歳になり、漸く好き勝手が出来る様になったワケだが、若い頃は先輩ミュージシャンやリスナーの意見にかなり振り回されたものだ。そういう意味では、今の若手がもっとクリエイティブに好き勝手出来る土壌を作ってあげる事が今後の僕の役割かも知れない。若手達には、NYばかり追っかけてないで、俺でさえ聴いたことの無い全く新しい音楽を聴かせてくれや!って思ってるので。でも、最も大切なのは、そういう音楽を受容れる土壌、この国のリスナーの文化度…がもっと高くなる事だと思う。
最近、YouTubeでヘビーリスニングしてるのは、2ちゃんねる創設者のひろゆきのチャンネルと、この方のジャズのチャンネルだ。僕が聞いた事も無い様な、ジャズジャイアンツ達のエピソードが聞けたり、とても楽しい。今後も楽しみだ。
追記: この方がこの動画で歌ってるシラブルは固定ドであり、移動ドの僕はこのパーカーのフレーズを「sol do,re,ri,mi,fa,fi,sol…」や「di re,fa,la,do,la,li,ti…」と「階名」で歌うので、正確には「音名」だと思います。














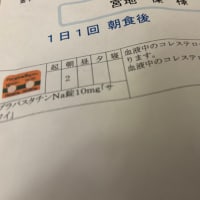













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます