「那覇ショッピングセンター」の近く、那覇市西1丁目付近に、「伊波普猷生家跡地」があります。「伊波普猷生家跡地」から南へ5分ほど歩いた場所に、「東恩納寛惇生家跡」があります。「沖縄学の父」といわれる伊波普猷とともに、沖縄学の確立に大きな役割を果たした東恩納寛惇の生家跡が、こんなに近かったとは、意外でした。

01-0517 伊波普猷生家跡地

02-0510 伊波普猷生家跡地

03-0510 伊波普猷生家跡地

04-0510 伊波普猷生家跡地

05-0510 伊波普猷生家跡地

06-0510 伊波普猷生家跡地
「伊波普猷生家跡地(イハフユウセイカアトチ)…沖縄学の父と言われる伊波普猷の生家跡地。伊波は琉球処分を目前にした1876年、那覇の西村(にしむら)で生まれた。生家は那覇士族魚氏(ぎょうじ)の家系で、素封家(そほうか)として知られていた。 沖縄県立一中在学中の1895年、英語科廃止問題から起こったストライキ事件で首謀者の一人として退学処分。上京して浪人後、京都の三高(現京都大学)に入学。1903年には東京帝国大学(現東京大学)に進み、言語学を専攻した。 1906年、卒業して帰郷すると、沖縄に関する画期的な研究論文を次々発表し、沖縄人による沖縄研究の先陣を切った。 1910年、沖縄県立図書館の初代館長となり、資料の収集の他、各地で300回余りに及ぶ衛生に関する講演を行うなど、啓蒙運動にも精力的に取り組んだ。 1911年には諸論考をまとめて、沖縄研究の記念碑的著作となる『古琉球(こりゅうきゅう)』を出帆した。その後も真境名安興(まじきなあんこう)、東恩納寛惇(ひがしおんなかんじゅん)とともに沖縄学の確立に大きな役割を果たし続けた。 1925年、館長職を辞して上京。生涯をかけた『もろそうし』の研究に没頭し、多くの成果を遺した。 終戦間もない1947年8月13日、米軍占領下の故郷沖縄の将来を憂(うれ)いながら東京で病没した。享年72才。 伊波は、近代沖縄が生んだ第一級の研究者、啓蒙家であった。 設置 1997年8月 那覇市文化局歴史資料室」
モノレール旭橋駅の西、「東町外科医院」近くに「東恩納寛惇生家跡」があります。「伊波普猷生家跡地」から南へ5分ほどの所です。

07-0517 東町外科医院

08-0517 東恩納寛惇生家跡

09-0517 東恩納寛惇生家跡

10-0517 東恩納寛惇生家跡

11-0517 東恩納寛惇生家跡
「東恩納寛惇生家跡(ひがおんなかんじゅんせいかあと)…沖縄研究者東恩納寛惇の生家跡。東恩納寛惇は1881年、当時の那覇東村に生まれた。東恩納家は那覇士族慎氏(しんうじ)である。 東恩納は、沖縄尋常中学校を経て、熊本の第五高等学校(現熊本大学)、ついで東京帝国大学史学科に進んだ。1908年卒業。その後も東京に留まり、1919年東京府立第一中学校の教諭、1929年には東京府立高等学校の教授となった。この間、1933年には東京府から派遣されて東南アジア・インドを歴訪、タイでは、日本人町の調査を行った。戦後は、1949年に拓殖大学の教授となった。 東恩納の沖縄研究は、大学在学中からで、『琉球新報』や各種雑誌等へ論文を発表している。主な著書に、『尚泰侯実録(しょうたいこうじつろく)』(1924)、『黎明期(れいめいき)の海外交通史』『泰ビルマ印度』(1941)など多数あり戦後も地名研究の名著『南島風土記』(1950)、『校注羽地仕置(こうちゅぅはねじしおき)』(1952)がある。 1963年に東京で死去、享年83才。60年余かけて収集された蔵書は、郷里沖縄に寄贈され、現在沖縄県立図書館に『東恩納文庫(ひがおんなぶんこ)』として収蔵されている。 なお、同生家跡は、王国時代は薩摩藩在藩奉行所(さつまはんざいはんぶぎょうしょ)の脇仮屋(ワチカイヤ)で、1900年から沖縄戦にかけては、並川金物店となっていた。」
「天使館跡」の説明板は、「那覇市医師会館」前にあります。医師と天使ということで、てっきり白衣の天使(看護師)養成施設なのかと思っていたのですが、説明を読み、中国から派遣した冊封使(天使)の施設・宿舎跡だとわかりました。この近くには、「下天妃宮」や「那覇里主所」などもありました。

12-0510 那覇市医師会館

13-0413 天使館跡

14-0413 天使館跡

15-0413 天使館跡

16-0413 天使館跡

17-0413下天妃宮

18-0413 那覇里主所
「天使館跡(テンシカンアト)…琉球王国時代、中国が派遣した冊封使(さっぽうし、天使)のための施設・宿舎。一般に館屋(クヮンヤ)と称した。創建年代は不明だが、16世紀前半には確認される。冊封使の渡来は三山(さんざん)時代から1866年まで都合23回を数えた。正・副使以下400~500人が夏から冬の約半年間滞在。崇元寺(そうげんじ)で故国王を弔(とむら)い(諭祭、ゆさい)、首里城で新国王を冊封した。国王一世一代の大行事であった。 冊封使滞在時の他は、通常その一部が砂糖座(さとうざ)として用いられ、砂糖の収納、薩摩藩(さつまはん)への送り出し、砂糖樽の製造が行われた。 沖縄県設置の後、1896年には那覇区役所(後に市役所)となり、1917年には新庁舎を建てていたが、沖縄戦の前哨(ぜんしょう)となる、1944年10月10日の大空襲で破壊された。
下天妃宮(シムヌティンピ)…航海安全の守護神、天妃(媽祖、まそ)を祀った廟(びょう)。現在石門のみ残る上天妃宮より先の永楽(えいらく)年間(1403~24)の創建とされる。中国から渡来した?人(びんじん)三十六姓(せい)の請来(しょうらい)と考えられている。 廃藩後の1880年6月には、隣接する那覇里主所(なはさとぬしじょ)敷地ともども沖縄小学師範(しはん)学校(後に沖縄県立師範学校)が設置され、廟内の神像はすべて上天妃宮に移された。 1886年1月、師範学校が首里に移って後、那覇郵便局となっていた。
那覇里主所(ナハサトヌシジョ)…那覇四町(ユマチ)の行政および薩摩藩在藩奉行所(さつまはんざいはんぶぎょうしょ)との接渉(せっしょう)、唐船(とうせん)・楷船(かいせん)・旅役(たびやく)などの事務を下天妃宮管掌(かんしょう)した首里王府の役所跡。長官は那覇里主、下役には那覇大筆者(ウフひっしゃ)、脇筆者(ワチひっしゃ)がいる。 那覇里主は、古琉球期、親見世(おやみせ)の長たる御物城(おものぐすく)職とともに王国の対外窓口たる那覇の港、町の管理にあたっていた。近世期においても基本的役割は変わらなかったが、任職者は首里の上級士族に限定され、王府中枢(ちゅうすう)役人の出世コースの一職となった。 設置 1997年3月 那覇市文化局歴史資料室」
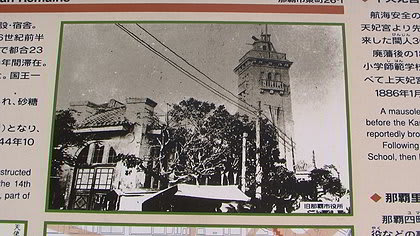
19-0413 天使館跡

20-0413 天使館跡

21-0413 天使館跡




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます