
奈良東大寺で行われるお水取りは、修二会(しゅにえ)という自らの罪を悔い改め、人々の幸せを祈る苦行です。
この行事が始まったのは天平勝宝4年(752年)
以来今年で1270回目を迎えるにあたり、過去幾度かあった危機を一度たりとも中断することなく続けられてきました。
そのことから「不退の行法」とも称されています。
お水取りという言葉は、東大寺にある井戸から「お香水」を汲み上げ、それを観音菩薩にお供えをするということからきています。
この井戸の水の源泉は、なんと福井県の若狭です。
由来の話は、神様達が東大寺へ一斉に集まる時に、魚釣りに興じて遅れてやってきた神様がいたのです。
その神様が、若狭の国の遠敷明神。
おわびに、2月堂のほとりに湧水を出して、それを観音様に捧げたという話です。(参照⇒東大寺)
3月2日に福井県小浜市の若狭神宮寺で東大寺へ水を送る行事が行われています。
ここで注がれた水は10日かけて東大寺の「若狭井」に湧き出るとされています。
お水送りの場所 鵜の瀬
若狭神宮寺から2キロほど
福井県小浜市を流れる遠敷川(おにゅうがわ)の中流に位置する淵で、ここの水は日本の名水100選にも選ばれています。
⇒ニッポン旅マガジン
3月2日 鵜の瀬お水送りの様子
住職が竹の筒に入った「お香水」を川に注いでいます。
⇒産経フォト
福井県若狭神宮寺から神聖な香水が送られ100km先の東大寺へ辿り着く
送られた水は、二月堂のそばに閼伽井屋(あかいや)というお堂があり、その中にある若狭井という井戸に着きます。
ここで、お水取りの儀式が執り行われます。
⇒奈良まちあるき風景紀行
閼伽井屋から二月堂を見る
⇒奈良歴史散歩
実際に、お香水を汲み上げる儀式は、日が変わって13日の午前1時半ごろになります。
13日未明のの儀式 香水汲み
⇒奈良新聞
コロナの影響がまだ残り、拝観には制限がありますが、長い歴史と空間広がる水の送りと汲みに想像を膨らませば、お水取りは春の一大行事です。
二月堂から少し離れた春日野園地に大型ビジョンが設置されるようですので、闇の中広々とした公園で味わうのもまたよしかとも・・・・










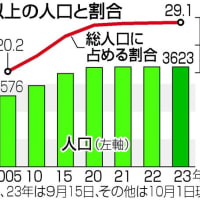















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます