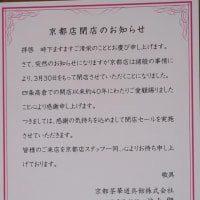好文棚 濃茶 長緒
懸け釜の準備のため
皆で鶴屋八幡に道具を搬入した
あの日から
あっという間に
二週間が過ぎました
記憶の新しいうちに
皆様より
今回の懸け釜において
気づいたことなど
お話を伺っています
次回の懸け釜については
まだ何も決まってはいないのですが
せっかくいただいた勉強の機会を
無駄にしないよう
意見交換をしております

さて
客の作法の一つとして
正客と詰めが出会って
拝見物を返すという
習いがあります
この時
正客の座る場所について
先日の稽古で
ご指導を受けて
家に帰ってから
本を開いてみますと
目からウロコの発見がありました

『習事八箇条』27頁より
これは
台飾で正客が
茶碗と台を返す場面です
私が思っていたより
かなり炉に近い場所に
座っておられます
これは
拝見物を仮置きする際に
膝線より後ろに置かないように
するためなのだそうです
それでは
風炉の場合はどうなのかと思い
調べてみました

『習事十三箇條』54頁より
正客は
久田宗匠の若かりし頃の御姿と
伺っております
あら!
やはり私がこれまで座ってきた位置よりも
ずいぶん下がった場所に
お座りになっておられます
お身体は通い畳より外に出て
つまり
足先は床畳に入った状態で
座っておられるのです
確かに
ここに座れば
仮置きする場所は
膝線より下がることはありません
これまで
何度も拝見していた写真なのですが
今まで気づきませんでした
もちろん
お茶の所作は
時と場合によって
臨機応変・融通無碍に対処することが
最も大切なことかと思いますので
唯一の正解を求めるべきでは
ないかもしれませんが
皆様も是非
拝見物を返す時の
正客の座る場所について
ご一考なさってみてはいかがでしょうか
新たな気づきが
あるかもしれません

主菓子 ねじ梅 鼓月製

干菓子 土佐の青のりせんべい