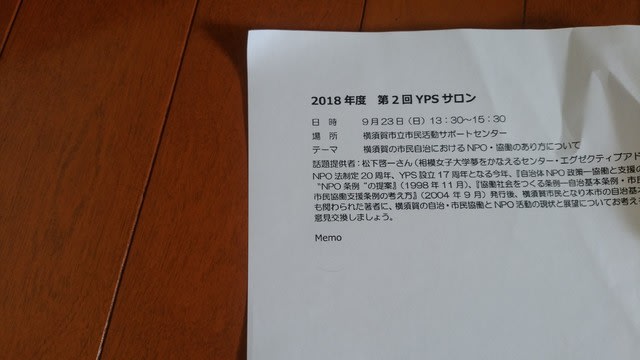
NPO活動をしている人たちから誘われて、横須賀市の市民自治について大いに語った。少人数の参加なので、座談会風の話とした。
横須賀は、市長さんが変わり、少し変化し始めた。音楽のまちづくりもそのひとつである。音楽を通して、人が元気になり、街が活性化することが狙いである。
市長さんが変わって、手法の違いが面白い。
以前の市長さんは、理念から入り、その後に施策を実施するという行動パターンであるが、今度の市長さんは、とにかくやってみてという手法である。理屈よりは実践で、横須賀っぽいといえば、横須賀っぽい。
その例のひとつが、LGBTである。横須賀は、LGBT施策が最も進んでいるというが、条例を作ってから施策を組み立てるというやり方ではなく、簡単に要綱を作って、ともかく施策をたくさんと積み上げるというやり方である。
後者のやり方は、勢いがあり、市長の勢いに押されて、行政職員も頑張っているが、そのうち、知恵が枯渇し、息切れしたときに、途端にパワーダウンとなる恐れもある。今はいいが、早晩、壁にぶつかる。
そこで、早いうちから、体系化をする必要があるだろう。体系のひとつが、自治基本条例で、お客としての市民ではなく、自治の主体としての市民をきちんと位置づけ、みんなでまちを盛り上げるようにしないといけないだろう。
市長さんが、理論的・体系的にまちづくりを進めるのが、好みでないとしたら、それを行うのが市民の役割というのが、この日の話である。
ではどうやるかであるが、区民会議の体験など、いくつかのヒントはあるが、まだ私自身のなかでも記述化できていない。この日に向けて、準備しようと考えたが、忙しさにかまけて、できなかった。バラバラと話したことをまとめたらよいが、談論風発、うまくまとまらない。
そこで、宣言したのは、今度、市民協働の審議会の公募があったら、市民委員として出て、市民による政策提案の実証的に証明してみようというものである。若者参画のまちづくりなどの提案である。大学教授から、定年した市民に戻ったので、ちょうどよい。
ただ、この勉強会に出席した市民からは、ほぼ全員、「松下さんは、採用されない」というものである。横須賀市の場合、審議会の市民委員になるには、小論文と面接があるそうであるが、絶対、落ちるという見立てである。その理由は、「委員長がビビる」ということのようであるが(まさか!)、市民がきちんと政策提案できるというのは、これから大事なことであるし、行政にとってもメリットがあることなので、私としては、採用される自信がある。
2月くらいに募集があるだろうから、差し障りのない範囲で、顛末を報告したい。
横須賀は、市長さんが変わり、少し変化し始めた。音楽のまちづくりもそのひとつである。音楽を通して、人が元気になり、街が活性化することが狙いである。
市長さんが変わって、手法の違いが面白い。
以前の市長さんは、理念から入り、その後に施策を実施するという行動パターンであるが、今度の市長さんは、とにかくやってみてという手法である。理屈よりは実践で、横須賀っぽいといえば、横須賀っぽい。
その例のひとつが、LGBTである。横須賀は、LGBT施策が最も進んでいるというが、条例を作ってから施策を組み立てるというやり方ではなく、簡単に要綱を作って、ともかく施策をたくさんと積み上げるというやり方である。
後者のやり方は、勢いがあり、市長の勢いに押されて、行政職員も頑張っているが、そのうち、知恵が枯渇し、息切れしたときに、途端にパワーダウンとなる恐れもある。今はいいが、早晩、壁にぶつかる。
そこで、早いうちから、体系化をする必要があるだろう。体系のひとつが、自治基本条例で、お客としての市民ではなく、自治の主体としての市民をきちんと位置づけ、みんなでまちを盛り上げるようにしないといけないだろう。
市長さんが、理論的・体系的にまちづくりを進めるのが、好みでないとしたら、それを行うのが市民の役割というのが、この日の話である。
ではどうやるかであるが、区民会議の体験など、いくつかのヒントはあるが、まだ私自身のなかでも記述化できていない。この日に向けて、準備しようと考えたが、忙しさにかまけて、できなかった。バラバラと話したことをまとめたらよいが、談論風発、うまくまとまらない。
そこで、宣言したのは、今度、市民協働の審議会の公募があったら、市民委員として出て、市民による政策提案の実証的に証明してみようというものである。若者参画のまちづくりなどの提案である。大学教授から、定年した市民に戻ったので、ちょうどよい。
ただ、この勉強会に出席した市民からは、ほぼ全員、「松下さんは、採用されない」というものである。横須賀市の場合、審議会の市民委員になるには、小論文と面接があるそうであるが、絶対、落ちるという見立てである。その理由は、「委員長がビビる」ということのようであるが(まさか!)、市民がきちんと政策提案できるというのは、これから大事なことであるし、行政にとってもメリットがあることなので、私としては、採用される自信がある。
2月くらいに募集があるだろうから、差し障りのない範囲で、顛末を報告したい。

























