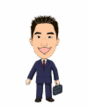シリーズ平成の本音―防衛省へ募る不信と不安
政府は2012年より、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に100人規模の陸上自衛隊員を派遣しているが、政権が安定せず、治安状況の悪化と共に、派遣中断問題も検討対象となる。
南スーダンは、2011年にスーダンが南北に分裂して独立したが、2013年12月に大統領派と副大統領派が対立し、その後両派の武力衝突が繰り返されており、事実上の‘内戦状態’とも言われている。その後2015年8月に両派間に和平合意がなされたが、2016年7月にジュバで両派間の大規模な戦闘が発生し、市民を含め数百人が死亡した。
こうした状況を背景として、国会審議では民進党など野党から「PKO参加5原則」に照らし引き上げなどの検討が指摘されていた。自衛隊のPKO参加の前提条件として、(1)紛争当事者間での停戦合意、(2)日本の参加に現地政府や紛争当事者が同意、(3)中立の厳守、(4)以上のいずれかが満たされなければ撤収可能、及び(5)必要最小限の武器使用というPKO 5原則が定められている。
なお、武器の使用については、安全保障関連法(2015年9月)に基づく新任務として「駆けつけ警護」が付与され、これを盛り込んだ「実施計画」が閣議決定されている。‘駆けつけ警護’は、周辺で襲われた国連職員やNGO職員等の救援に向かう任務で、任務遂行のための武器使用が可能になる一方、生命の危険が高まる。
国連平和維持活動に自衛隊を派遣する要件として最も重要な点は、表現の問題ではなく、紛争当事者間での停戦合意が維持されているか否かという実態であるだけに、南スーダンで武力衝突や戦闘行為があるか否かが大きな問題となる。
‘武力衝突’と‘戦闘’との間にはそれ程大きな差はない。前者は、状態を表現し、後者は行為を表現しているに過ぎず、どっちの表現が正しいかなどは不毛な議論だ。
この問題で、技術的、法律的な問題は別として、将来の日本にとって深刻な点が2つある。
一つは、防衛当局が国会を含め、情報や資料を隠し、また資料やデータを廃棄したなどと嘘をつくことではないだろうか。仮にも国会での答弁であるので、虚偽と分かれば処罰すべきであろう。現地部隊からの‘日々日報’は、情勢判断するための生の情報であると共に、今後派遣をされる場合の隊員にとって有用な情報となるので、短期に‘廃棄’すべき情報ではない。ましてや政府当局の公務上の情報は、いわゆる‘ヤバイ’情報でもない限り、3年間ほど、少なくても1年以上保管されているし、保管するのが義務であろう。当局が、勝手に短期に‘廃棄’するのは、ケースによっては証拠隠滅となる恐れがある。これは重大な問題であるので、厳重に調査し、適正な対処が必要だ。
もう一つは、現場の部隊と本部との間で見解の差がある中で、防衛大臣が、国会や国民に誠実に事実を伝えないことだ。
現場の部隊からは、‘戦闘’があった旨の報告があったのは明らかである。それを、防衛相は、国会での野党の質問に対し、‘戦闘’ではなく‘武力衝突’と答えた。更なる追及に対し、防衛相は、「事実行為としての殺傷行為はあったが、憲法9条上の問題になる言葉は使うべきではないことから、武力衝突という言葉を使っている」とし、‘法律上の戦闘ではない’とした。要するに、憲法上問題になる表現は避けるというだけで、言葉をすり替えているに過ぎない。
スーダン等で政府軍と反政府勢力が、衝突し、武器を持って射ち合えば‘戦闘’である。現場は生きるか死ぬかの状態であるので、日本の憲法や法律の問題などでは考える余裕はなし、その必要もない。
現場の部隊と大臣を含む本部との間の情勢認識が違う場合、PKO活動を遂行する上で致命的な結果をもたらすことにもなる。本部が現地情勢を楽観し、国会や国民にそのように報告し、任務を継続させれば、現地の部隊に致命的な被害を与える恐れがあるばかりでなく、政府の姿勢が内外から問われる恐れがある。第2次世界戦争中、戦争遂行の中枢であった‘大本営’は、太平洋各地での戦闘で手柄のみを宣伝し、不利な情勢は流さず、戦争を続けて停戦の機会を逃し、また被害を拡大させた過去がある。‘大本営発表’として知られているが、今回の事件もそれに一脈通じるものがある。
シビリアン・コントロールの確保は重要ではあるが、現場の部隊(制服組)と防衛相を中心とする幹部(背広組)や首相等との間に情勢認識や情勢判断に差異が存在することは望ましくない。特に部隊が発する情勢認識を首相や大臣が握りつぶし、また政権に都合の良い方に歪めて発表等することは、国家、国民の針路を誤らせることにもなり兼ねない。
3月10日、政府は、本年5月で南スーダンの国連平和維持活動(PKO)参加している陸上自衛隊員を撤退させることを発表した。しかし、防衛大臣は、それはあくまでも‘任務達成のため’であり、‘治安情勢悪化のためではない’とした。最初に虚偽を発表するとその後の対応についてつじつまを合わせる必要があるのだろうが、こんなことでは防衛大臣も防衛相も信用は出来ない。
国連のディエン事務総長特別顧問は、2016年12月7日にも、対立が続く南スーダンについて、‘衝突は継続し、大虐殺が起きる恐れが常に存在する’旨警告する声明を改めて発表した。危険な状況は続いているとみられ、治安の悪化は明らかなようだ。
北東アジア情勢は、緊迫と混迷の度を増している。中国の軍備増強と海洋進出は一段と進んでいる。また中東和平は進展せず、イスラム過激派による国際テロはアフガニスタンや中東地域、一部アフリカ諸国に拡大し、その過程でイラク、シリアにイスラム国(IS)が台頭していると共に、国際テロの危険性は世界に拡散し、膨れ上がる難民問題等が欧州にも影を落としている。このような状況で、本来であれば日本も海・空を中心として防衛力を増強しなくてはならないが、情報隠しや情報の歪曲などをする現在の防衛省では、国民の理解は得られそうにない。
因みに稲田防衛相は、安倍首相同様、東条英機などの戦争責任者も祀られている靖国神社を‘防衛大臣’として毎年参拝している。2016年12月には、首相に同行して太平洋戦争に突入する直接の契機となったハワイのパールハーバーをオバマ大統領(当時)と共に訪問し、戦争体験を克服し和解したことを内外に示したが、その帰国直後、稲田防衛相は靖国神社を訪問した。何を懺悔し何を誓ったのか。同相は、首相やほとんどの閣僚がメンバーとなっている神道政治連盟国会議員懇談会や日本会議など、神道や神社、天皇制を擁護する団体に属しているとされている。どのような宗教観、政治信条を持つかは各人の自由だが、政治家であれば、国民や有権者にそれを明らかにして活動し、また支持を集めるべきであろう。表舞台では建前やきれい事を言い、裏では特定の団体、グループを優遇するなど、不明朗且つ不誠実な活動を行っているとすれば、不気味ではある。(2017.3.14)
政府は2012年より、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に100人規模の陸上自衛隊員を派遣しているが、政権が安定せず、治安状況の悪化と共に、派遣中断問題も検討対象となる。
南スーダンは、2011年にスーダンが南北に分裂して独立したが、2013年12月に大統領派と副大統領派が対立し、その後両派の武力衝突が繰り返されており、事実上の‘内戦状態’とも言われている。その後2015年8月に両派間に和平合意がなされたが、2016年7月にジュバで両派間の大規模な戦闘が発生し、市民を含め数百人が死亡した。
こうした状況を背景として、国会審議では民進党など野党から「PKO参加5原則」に照らし引き上げなどの検討が指摘されていた。自衛隊のPKO参加の前提条件として、(1)紛争当事者間での停戦合意、(2)日本の参加に現地政府や紛争当事者が同意、(3)中立の厳守、(4)以上のいずれかが満たされなければ撤収可能、及び(5)必要最小限の武器使用というPKO 5原則が定められている。
なお、武器の使用については、安全保障関連法(2015年9月)に基づく新任務として「駆けつけ警護」が付与され、これを盛り込んだ「実施計画」が閣議決定されている。‘駆けつけ警護’は、周辺で襲われた国連職員やNGO職員等の救援に向かう任務で、任務遂行のための武器使用が可能になる一方、生命の危険が高まる。
国連平和維持活動に自衛隊を派遣する要件として最も重要な点は、表現の問題ではなく、紛争当事者間での停戦合意が維持されているか否かという実態であるだけに、南スーダンで武力衝突や戦闘行為があるか否かが大きな問題となる。
‘武力衝突’と‘戦闘’との間にはそれ程大きな差はない。前者は、状態を表現し、後者は行為を表現しているに過ぎず、どっちの表現が正しいかなどは不毛な議論だ。
この問題で、技術的、法律的な問題は別として、将来の日本にとって深刻な点が2つある。
一つは、防衛当局が国会を含め、情報や資料を隠し、また資料やデータを廃棄したなどと嘘をつくことではないだろうか。仮にも国会での答弁であるので、虚偽と分かれば処罰すべきであろう。現地部隊からの‘日々日報’は、情勢判断するための生の情報であると共に、今後派遣をされる場合の隊員にとって有用な情報となるので、短期に‘廃棄’すべき情報ではない。ましてや政府当局の公務上の情報は、いわゆる‘ヤバイ’情報でもない限り、3年間ほど、少なくても1年以上保管されているし、保管するのが義務であろう。当局が、勝手に短期に‘廃棄’するのは、ケースによっては証拠隠滅となる恐れがある。これは重大な問題であるので、厳重に調査し、適正な対処が必要だ。
もう一つは、現場の部隊と本部との間で見解の差がある中で、防衛大臣が、国会や国民に誠実に事実を伝えないことだ。
現場の部隊からは、‘戦闘’があった旨の報告があったのは明らかである。それを、防衛相は、国会での野党の質問に対し、‘戦闘’ではなく‘武力衝突’と答えた。更なる追及に対し、防衛相は、「事実行為としての殺傷行為はあったが、憲法9条上の問題になる言葉は使うべきではないことから、武力衝突という言葉を使っている」とし、‘法律上の戦闘ではない’とした。要するに、憲法上問題になる表現は避けるというだけで、言葉をすり替えているに過ぎない。
スーダン等で政府軍と反政府勢力が、衝突し、武器を持って射ち合えば‘戦闘’である。現場は生きるか死ぬかの状態であるので、日本の憲法や法律の問題などでは考える余裕はなし、その必要もない。
現場の部隊と大臣を含む本部との間の情勢認識が違う場合、PKO活動を遂行する上で致命的な結果をもたらすことにもなる。本部が現地情勢を楽観し、国会や国民にそのように報告し、任務を継続させれば、現地の部隊に致命的な被害を与える恐れがあるばかりでなく、政府の姿勢が内外から問われる恐れがある。第2次世界戦争中、戦争遂行の中枢であった‘大本営’は、太平洋各地での戦闘で手柄のみを宣伝し、不利な情勢は流さず、戦争を続けて停戦の機会を逃し、また被害を拡大させた過去がある。‘大本営発表’として知られているが、今回の事件もそれに一脈通じるものがある。
シビリアン・コントロールの確保は重要ではあるが、現場の部隊(制服組)と防衛相を中心とする幹部(背広組)や首相等との間に情勢認識や情勢判断に差異が存在することは望ましくない。特に部隊が発する情勢認識を首相や大臣が握りつぶし、また政権に都合の良い方に歪めて発表等することは、国家、国民の針路を誤らせることにもなり兼ねない。
3月10日、政府は、本年5月で南スーダンの国連平和維持活動(PKO)参加している陸上自衛隊員を撤退させることを発表した。しかし、防衛大臣は、それはあくまでも‘任務達成のため’であり、‘治安情勢悪化のためではない’とした。最初に虚偽を発表するとその後の対応についてつじつまを合わせる必要があるのだろうが、こんなことでは防衛大臣も防衛相も信用は出来ない。
国連のディエン事務総長特別顧問は、2016年12月7日にも、対立が続く南スーダンについて、‘衝突は継続し、大虐殺が起きる恐れが常に存在する’旨警告する声明を改めて発表した。危険な状況は続いているとみられ、治安の悪化は明らかなようだ。
北東アジア情勢は、緊迫と混迷の度を増している。中国の軍備増強と海洋進出は一段と進んでいる。また中東和平は進展せず、イスラム過激派による国際テロはアフガニスタンや中東地域、一部アフリカ諸国に拡大し、その過程でイラク、シリアにイスラム国(IS)が台頭していると共に、国際テロの危険性は世界に拡散し、膨れ上がる難民問題等が欧州にも影を落としている。このような状況で、本来であれば日本も海・空を中心として防衛力を増強しなくてはならないが、情報隠しや情報の歪曲などをする現在の防衛省では、国民の理解は得られそうにない。
因みに稲田防衛相は、安倍首相同様、東条英機などの戦争責任者も祀られている靖国神社を‘防衛大臣’として毎年参拝している。2016年12月には、首相に同行して太平洋戦争に突入する直接の契機となったハワイのパールハーバーをオバマ大統領(当時)と共に訪問し、戦争体験を克服し和解したことを内外に示したが、その帰国直後、稲田防衛相は靖国神社を訪問した。何を懺悔し何を誓ったのか。同相は、首相やほとんどの閣僚がメンバーとなっている神道政治連盟国会議員懇談会や日本会議など、神道や神社、天皇制を擁護する団体に属しているとされている。どのような宗教観、政治信条を持つかは各人の自由だが、政治家であれば、国民や有権者にそれを明らかにして活動し、また支持を集めるべきであろう。表舞台では建前やきれい事を言い、裏では特定の団体、グループを優遇するなど、不明朗且つ不誠実な活動を行っているとすれば、不気味ではある。(2017.3.14)