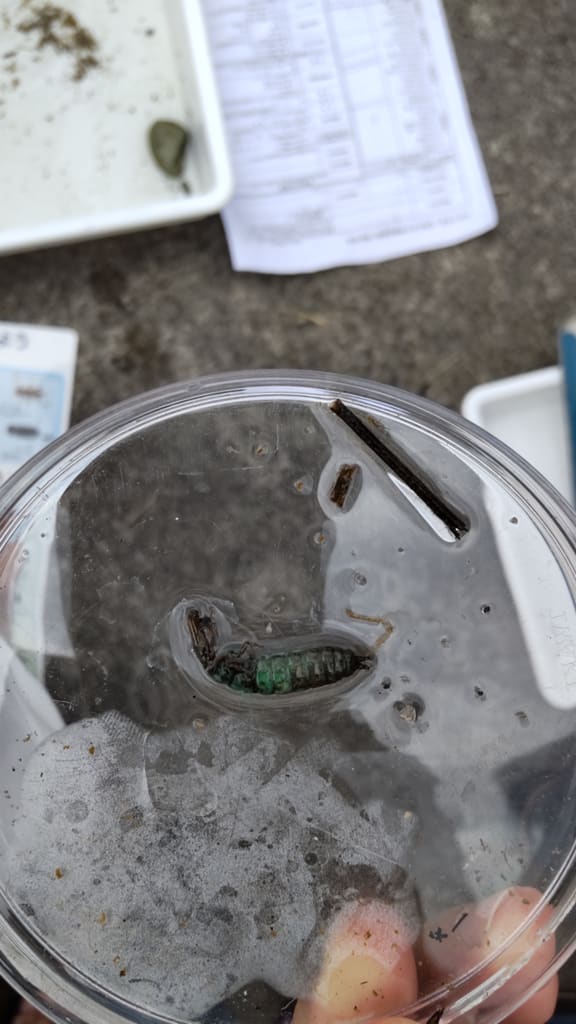第3段 色恋に苦労しない男には、ひとかどの人物としてのオーラは感じられないの?
「玉の巵(さかずき)の当(あて)なき心地ぞすべき」って「底の抜けた玉杯のようなもの」ということらしいけど、どんな感じ?
「玉の巵(さかずき)の当(あて)なき心地ぞすべき」って「底の抜けた玉杯のようなもの」ということらしいけど、どんな感じ?
立派で高価な材料で作られたものだけど、底が抜けている盃っていうのは?
才能とかが優れた人物のようだけれど、色恋に悶々としたことのない男のことを指していっているようなんだけど。
なんか、すごい例えみたいな感じはする。
簡単にいえば「見た目はいいが味のない人物」ということかな?
恋情が高まって、雨に濡れてまで女性の家を行き来したり、それで世間的に嘲笑され、親にたしなめられるほどなのに、思いが果たせず、結局、自分のベッドの中で悶々としている、こんな男を作者はいったんは馬鹿にしているようで、そんな男こそが味がある、人間味があると評価している。
じゃあ、そんな男がいいのかと結論しているのかというとそうでもない。
色恋しない男は味気ない。
色恋しすぎる男は、その積み重ねられた経験の味わいがあるが、女に軽く思われそうで、これもイマイチ。
ほどほどの色恋で止めている男がクールといえようって感じなのかなー。
仏教思想からいえば、色恋なんて虚しいとの発言がありそうだけど、390年間ほど続いた貴族の文化からすると、たしなみとして色恋は完全否定はできないものだったんだろうなあ。
ほどほどという感覚は儒教や仏教の中庸の精神に繋がるよね。
なんか、すごい例えみたいな感じはする。
簡単にいえば「見た目はいいが味のない人物」ということかな?
恋情が高まって、雨に濡れてまで女性の家を行き来したり、それで世間的に嘲笑され、親にたしなめられるほどなのに、思いが果たせず、結局、自分のベッドの中で悶々としている、こんな男を作者はいったんは馬鹿にしているようで、そんな男こそが味がある、人間味があると評価している。
じゃあ、そんな男がいいのかと結論しているのかというとそうでもない。
色恋しない男は味気ない。
色恋しすぎる男は、その積み重ねられた経験の味わいがあるが、女に軽く思われそうで、これもイマイチ。
ほどほどの色恋で止めている男がクールといえようって感じなのかなー。
仏教思想からいえば、色恋なんて虚しいとの発言がありそうだけど、390年間ほど続いた貴族の文化からすると、たしなみとして色恋は完全否定はできないものだったんだろうなあ。
ほどほどという感覚は儒教や仏教の中庸の精神に繋がるよね。