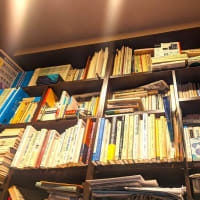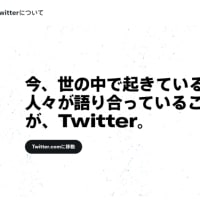昨日、とあるコンビニに立ち寄った。
そのコンビニのレジには、20代半ば~後半くらいの女性と、高校生の女の子がいた。二人ともバイトの子のようだった。レジは二台あり、左手にはその20代半ば~後半くらいの女性がおり、右手には女子高生が立っていた。
二人の間には、会話はなく、ただ立っている様子だった。高校生の方は新入りっぽい感じで、若々しく、元気がある感じだった。
しばらくすると、その女子高校生のバイトの子の友だちが二人、コンビニにやってきて、そのバイトの子となにやら話をしていた。どうやら応援しにきたみたいだった。その光景は、僕の目には、ほほえましく、朗らかに見えた。バイト先に友だちが応援しにきてくれたら、それはとても嬉しいだろう。
だが、その隣にいる20歳半ば~後半の女性は、それを鬱陶しそうに、怪訝そうに見ていた。それも理解できる。バイト中なのに、友だちとおしゃべりを始めたのだから。お客さんが来ると、おしゃべりはなくなり、もくもくと商品のレジを打つ。仕事は真面目にやっている。けれど、お客さんが帰ると、その友だちとまたおしゃべりを始める。
一瞬、二人の目があった。が、何も会話はなく、少し緊張感のある一瞬だった。
きっと、20代半ば~後半の女性は、「なにやってんのよ。この娘は。今は仕事中でしょ。のんきにおしゃべりなんかしてんじゃねーよ」、と思っていただろう。想像するに。でも、それはぐっとこらえて、我慢していたのではないか。少なくとも、彼女の表情から、我慢している様子は窺えた。
他方、女子高校生は、「いい年して、コンビニのバイトかよ。おばさんがなによ。ウザいわね。あー、ウザイウザイ」というような感じだった。「私はあんたとは違うからね。私なら、あんたの年なら、コンビニのバイトはしないから。申し訳ないけど」、という印象を受けた。
もちろん、本人たちに聞いたわけじゃないから、想像の域を出ない。半ば、僕の妄想だ。だが、こういう「世代間対立」というのは、いろんなところで起こっているようにも思う。
20代の方の女性を見ると、たしかに茶髪で、昔はかなりやんちゃだったんだろうなという感じだった。そして、年をとり、仕事をしなければならない年齢になり、コンビニのバイトを見つけ出し、働き出したのだろう。正規雇用の乏しい時代だ。学歴やある程度の専門技術や資格がなければ、それなりの職場での正規雇用は難しい。単純労働はみんな非正規雇用や臨時採用ばかりだし、女性となれば、さらに正規雇用の道は険しい。この20代の女性を眺めていると、そういう苦しさが痛いほどに伝わってきた。(バイトをしているときの目がすごい悲しそうで、、、)
他方、高校生の方を見ると、何も考えずただバイトをしている様子が窺えた。頭がやわらかい青年期に、若者たちは「高等教育」にふさわしい勉学に励むことなく、バイトに精を尽くしている。それは今も昔も変わらないかもしれない。ただ、色んなことが学べる時期に、こうやって小銭を稼いでいるのが、この国の高校生たちである。もちろん、「受験勉強」や「部活動」に精を尽くす若者も決して少なくない。でも、高等学校での学びに全力で取り組んでいる生徒は実際どれだけいるのだろうか。もちろんいるとは思う。でも、その多くが、「学校で真面目に勉強をやっている」という意味であって、学校での学びに朝も夜も問わず3年間ずっと没頭している生徒はどれだけいるのだろうか。少なくとも、この目の前にいる高校生の女の子は、
この両者は、全く世界を異にしている。希望が消えかけている20代の女性、そして、未来の可能性が未知数の高校生、この両者には、超えられない溝があるように見えた。そして、そこには「対話」はない。
もし、この二人がお互いに関心をもち、対話をしたらどうなるのだろうか。きっとお互いに何かを得て、何かを学べるのではないか。そんな気持ちにもなった。いや、あるいは、お互いに分かり合えないことが分かって、暗い気持ちになるかもしれないし、嫌悪の関係になってしまうかもしれない。ただ、実際には、そんな対話は起こらないまま、離れ離れになってしまうのだろう。
特に、僕は20代の女性が気になった。どんな気持ちでレジを打っているのだろう。彼女の目は暗く沈んでいるように見えた。もちろん、想像の領域なので、違うかもしれない。もしかしたら、生き生きと、心から楽しくレジを打っているかもしれない。でも、そう考えるのは無理がありそうなくらいに、沈んでいる瞳をしていた。
日々、若者相手に仕事をしている僕としては、やはり若者みんなにしっかりとした仕事があってほしいと願う。もちろん、自ら非正規や臨時の採用を望む場合は、それでよいと思うし、そういう選択肢があることはよいことだと思う。けれど、正規雇用を望む若者たちには、やはり全員正規雇用の職場を提供してもらいたいと願う。
ただ、世の中というのは不条理なもので、社会の進歩、技術の進化と共に、いわゆる「人手」がいらなくなってしまった。それは全体的なことで、個別的には「人手」が必要ではある。けれど、その「人手」は正規雇用でなくてもよい労働力であり、誰でもよくて、何の職業訓練も必要のないものなのである。いや、いつの時代でも、そういう「誰でもよい仕事」、「誰でもできる仕事」しかなかったのかもしれない。けれど、かつての仕事は、技術が弱い分、長いキャリア、経験、知恵が求められていた。数日の「研修」で済むような仕事ではなく、長い下積み、長いキャリアが必要な仕事だった。(第一次産業はどれも長い経験と知恵が必要だったはず)
そういう長い下積み、長い修養時代が必要な仕事は、やはり「正規雇用」を導くことになる。「長い経験」それ自体に、「価値」があるからである。「実際に行った労働価値」ではなく、「これから行なうであろう労働価値」に対しても、賃金が支払われるのだ。若者の正規雇用は、未来への投資でもある。
だが、今の労働環境をみていると、そういう「長い下積み経験」を必要としない仕事ばかりになっている。長年の経験、長年の積み重ね、長年のキャリアが価値をもたないのだ。逆に、頭がやらわかい高校生の方が、はるかにスムーズに早く(単純な)労働に順応できてしまうほどである。
上の事例から、それが言えるかどうかは分からないけど、この二人の女性の間にある溝は、どこまでも深く、分かり合えない断絶があるように思えてならなかった。