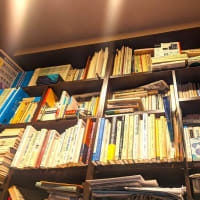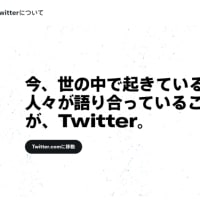現在講義で話している内容のスケッチです。
***
養護・ケアの原理を探すために、精神科学の扉を開いた。精神科学は、通常自然科学と対置するもので、説明ではなく、理解がその重要な方法となる。芸術作品、古典文学、文献解釈など、自然科学の手法では歯が立たないような領域においては、理解が常に問題となる。(第一回)
精神科学を理解する上で、書き手と読み手、プレイヤーとリスナーの関係性が役に立つ。書き手やプレイヤーは、通常「テクニック」が問われ、自らの技能を高めていくことでその質を上げていく。だが、読み手やリスナーは、そのようなテクニックや技能が固定されてあるわけでなく、その人の感覚やセンス、その人の価値観や生き方によって、良いか悪いかを判断する。俗的に言えば、「読み手/リスナーの自由」に任されている。(第二回)
読み手やリスナーは、通常の場合、その作品や曲が自分に共鳴するかどうかで、その作品や曲の良し悪しを判断する。つまりは共感できるかどうかが重要となる。時代が変わり、一つ前の時代の作品に共感することは難しいし、次の世代にも共感されるような作品を作るのはとても難しい。どの作品も、時代による審判を受けることになる。
では、人間(他者)の場合、どうであろうか。理解が問題となるのは、われわれが、読み手やリスナーのように、相手の話の聴き手となる時に問題となる-養護やケアの原理の一つに「相手の話を聴く」というのがある!-。こちらが話し手である場合は、理解が問題となるのではなく、説明が問題となるだろう。講演者は、聴衆のことを理解する必要はないし、また聴衆がどのように自分の話を理解するかについても、講演者はコミットすることができない。聴き手である時に、理解が問題となるのだ(第二回~第三回)
対象が作品や曲ではなく、他者であっても、どのように相手の話を受け止めるかは、こちらの判断に委ねられている。相手の話をどう聴くか、ということだ。さしあたって、日常的な態度としては、「共感的な態度」で話を聴く、というのがスタンダードであろう。われわれの日常の聴き方を考えれば、そのほとんどが共感的である。
だが、共感は、相手の話をそのまま受け止めるのではなく、かつての自分の体験に基づいて、その体験と合致するかどうかを量っているだけで、また、ある出来事に対して相手と同じ感情が生じるかどうかを問うている。とすると、それは理解ではなく、相手の体験を自分の体験として聴くことでしかなくなってしまう。相手の体験そのものは切り捨てられ、自分の体験の追体験でしかなくなってしまうのだ。ゆえに、他者の話を聴くということは、共感では不十分であるどころか、相手の話の内容そのものを歪めてしまう結果となる。
では、共感することなく、相手の話を聴くとはどういうことか? これが大きな問題となる。他者共感ではなく、他者理解は、どのようなプロセスを経て達成可能なのであろうか?これが分からなければ、相手の話をじっと聴く(zuhören)ことなどできるわけがない。相手の話を聴いているふりをすることはできても、相手の話を理解することはできない。
そこで、一つキーワードになるのが、「先入見」(Vorurteil)である。われわれが他者の話を聴く際、われわれは常に自分の先入見を用いて相手の言葉を聴いている。難しく言えば、われわれは人の話を聴く以前から、(なんとなく)相手の話を理解してしまっているのである。だから、相手の話を聴くと、すぐに(なんとなく)相手の言いたいことが分かってしまうのである。こうした先入見(日常的判断)を留保すること(エポケー)を目指してもよいが、あまり実際的ではない。むしろ、自分の先入見が起動していることを自覚しつつ、相手の話は常に自分の先入見によって歪められている、ということを自覚して、注意して聴くだけでも十分に理解の道が拓けるはずである。
自分の先入見の彼方にあるものが、相手の話である。相手の話は、自分の先入見である程度予測はできるものの、その先入見には収まりきらない内容を常に含んでいる。当然、自分がこれまで体験したことのないような出来事も相手の話には含まれている。つまり、「未知の領域」が常に相手の話にはあるのである。その未知の領域に自分が入り込んでこそ、真なる理解の可能性が拓かれるのである。その際、自分の先入見は、相手の先入見とせめぎ合いながらも、少しずつ融合していく。解釈学的には、おのれの地平と相手の地平が融合していく、ということである(「地平の融合」)。聴き手の側に特化すれば、相手の地平へと自ら入り込んでいくのである。相手の話の世界に入り込む、と言ってもいいだろう。他者の話の内容を自らにひきつけるのではなく、自らの先入見という殻を打ち破って、未知の領域である他者の世界へと入り込んでいくことが、理解するという態度であろう。
これは、子どもの理解を考えれば、容易に理解できることであろう。子どもという存在は、大人と違い、固くなった先入見を持ち合わせていない。ゆえに、「まっさらな状態」で人の話を聴くことができる。絵本を読んでいる子どもは、共感的に読んでいるのではなく、物語の世界に本当に入り込んでしまうのである。言葉や絵といった「道しるべ」を頼りに、物語の世界の中を生きてしまうのである。もちろん子どもは物語に書いてあるような体験をこれまでしているわけではない。まさに「未知の領域」である。
このことから分かるように、理解とは、共感と違い、おのれの狭い先入見を超え出て、相手の話そのものの中に入り込む行為を意味するのである。では、こうした理解を遂行するとき、われわれの方は一体そもそもどのようなことが起こっているのだろうか?
*次回は、「理解するとはおのれが変わること」について!