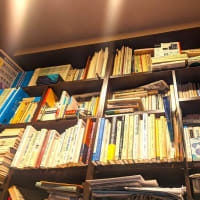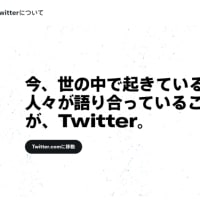もうすぐ夏だ。学生たちは長い休みになる。僕はこの時期こそ最も激しく働くことになるのだが・・・
昨日、ある講義の中で学生に「どんな本を読んだらいいですか?」と質問された。どんな本・・・ そういう質問が来るか?と思って考え込んだ。僕の心の中では、「本は自分が自由きままに読むもの」という観念があり、誰かに読め!と言われて読んだ経験に乏しいからだ。もちろん、その学生にはそのように伝えたのだが、実際、いつの時代にもしっかりとした本を読んでいる人間はそれほど多くはない。俗本やマニュアル本や単なる説教本はたしかにとてもよく売れているし、小説や漫画はとてもよく読まれている。が、その先を一歩進んで、文芸書や学術書に(自ら)手を伸ばそうとする学生の数はいつの時代でも少数派だと思う。もちろんそういった本を読まない学生たちは是非ともこの夏の長い時間に読んでもらいたい。基本的な読書量は、人間が生きるうえでの糧であるし、他者の考えを柔軟に取り入れることは若い時代にしかできないことである。だが、本ばかりを読みすぎると、それはそれで問題だ。それはいつの時代でも変わらない一つのメッセージだ。ショーペンハウアーも読書については厳しく戒めていた。そんな箇所を翻訳してみた。
われわれが読書をするとき、われわれに代わって別の人間が考えてくれる。われわれはただその著者の精神的な過程をなぞるだけなのだ。それは、書き方を学ぶ生徒が先生に鉛筆で書いてもらった筆跡をペンでなぞるようなものだ。こうして、読書をする際、考えるという営みの大部分をわれわれは写し取っているのである。ゆえに、自分独自で考えることから読書に移行するとき、心が軽くなるのを感じるのである。しかし、読書をしている間、われわれの頭の中は元来、単に他人の考えのたまり場(Tummelplatz)でしかない。ゆえに、たくさんの本をほとんど一日中読みふけっている人は、たしかにその間、何も考えずにただ時間をつぶすなかで心を休めているのだが、自ら考える力を徐々に失っていくのである―それは、いつも馬に乗っていて、歩き方を忘れた人間のように。このことは、学術書の多くについても言えることである。学術書を読むなんていうのはバカなことだ。
あらゆる自由な瞬間を瞬時に写し取ってしまう読書を続けることは、手作業を続けることよりも精神を麻痺させてしまう。というのも、後者の手作業の場合、それでも、自分独自の考えを推し進めていけるからである。しまいには、他の力の圧力が長い時間かかることでバネ(Springfaden)の弾力性が失われるように、精神も、他人の考えを押しつけられ続けるで、自らの弾力性を失っていくのである。そして、たくさんの栄養を摂り過ぎることで胃をこわし、それによって体全体が害されてしまうのと同様に、人はまた多くの精神の栄養を摂り過ぎるで、精神を満たしすぎて、窒息させてしまうのである。というのも、人が読書をすればするほど、それだけいっそうそれらの本の内容が精神の中でまとまらなくなってしまうからである。つまり、彼は、多くのことがぐちゃぐちゃと書いてある黒板のようになってしまうのである。 (「読書と本について」)
この痛烈なメッセージは、たしかに現代のごくわずかな若者たちには通用することであろう。だが、大衆化された大学の学生たちには通じない言葉かもしれない。この当時のヨーロッパの学生は、かなり限られていたし、学生の学習意欲もとてつもなく高かったと思う。また、本以外のメディアもそんなにあるわけじゃなかった。パソコンもなければ、ケータイもない。もちろんテレビだって。本だけが唯一のメディアだったのだ。そう考えると、この上の文章は、「本」だけじゃなくて、「様々な外部の考えのすべて」と置き換えて読む必要がある。
たしかに、現在のわれわれは、あらゆる情報の波に飲み込まれているようにも思う。あらゆる最新情報が頭の中に入りきらなくなるほどに注ぎ込まれている。「最新商品」は常に棚に陳列されているし、CMではなんだかよく分からないけど何となくほしくなるような刺激物が与えられている。僕らの精神は、もうパンパンに膨れ上がっていて、これ以上新しい何かを入れ込むことができなくなっているようにも思える。
そして、自分で考える、という最も当たり前の原始的な人間の技術が失われつつあるようにも思う。いや、もうとっくの昔に失われてしまったのかもしれない。僕らは、もうすでに生まれたときから、自分で考えるということを失ってしまっているのかもしれないのだ。
一度、今注がれている情報をリセットし、今の自分に必要な「知」(よい本)だけをゆっくりとじっくりと自分の精神に注ぐことこそ、一番大切なことなのかもしれない。まずは今の自分の精神に入り込む邪魔なものを捨ててみることから初めてみてはどうだろうか? まずは精神を空にしてみよう。 もちろん僕の精神も。