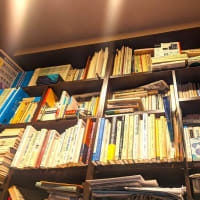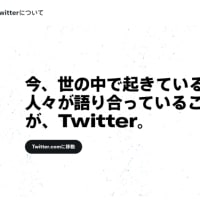学士号(学位:Diplom)を誇りに思っている日本人はどれだけいるだろうか。日本の大学や短大は、学位ではなく、資格取得に躍起になっているように思う。学生もしかりで、「大学に来たのだから、資格くらい取っておきたい」と語る学生は実に多い。あるいは、学士号取得を本気で目指すというよりは、「卒業」を目指す。
ドイツでは、この学士号が名刺に明記されることが多い。今回の訪独で、色んな人と名刺交換したが、そのほとんどの名刺に学士号が明記されていた。「心理学学士」「社会学学士」「犯罪学学士」「政治学学士」等々。この学士号を見て、人は、その人がどんな知的バックボーンをもっているのかを判断する。
しかし、日本の名刺に学士号が明記されることはまずない。職業上の立場、ポジション、地位に関する情報はあっても、学位を記した名刺というのはほとんどない。教員や保育士や介護系職員も同様で、資格名か、施設等でのポジションだけが明記されている。教師にだって色々な学位をもった人がいる。理科や数学を教える先生は、一教師であるが、学位はバラバラだろう。物理学学士、工学学士、数学学士、生物学学士等々。文系だっていろいろある。そうした「学士号」が明記されない、ということ自体が、実は大学軽視、あるいは学問の軽視となっているのではないだろうか。
ドイツでもFachshule、Fachhochschuleという職業に結び付いた高等教育機関がいっぱいある。今回、改めて気づいたのだが、ドイツの書店に行くと、必ずレジのそばにこのFachschuleやFachhochschuleのシラバスが置かれている。地域に開かれた高等教育機関として機能しているのである。もちろん職業訓練的な意味合いもあるが、それにとどまらない。語学や文学や宗教など、人間の生活のベーシックな部分を作る意味合いでも、地域に開かれている。
皆、キャリアを充実させたいとは思っている。ただ、そのために必要なのは「資格取得」ではない。その専門的知識の獲得である。
だが、日本の高等教育はそうではない。学生たちは皆、知識を取得するのではなく、資格を取得したいだけなのである。そういう意味では、日本の学生は、極めて形式主義的で、物質主義的で、資格主義的である。
僕は料理のできない「調理師免許取得者」だ。だから、資格や免許がどれほど形式的で、表面的で、実際とかけ離れているものかを痛感している。「教員免許」ももっているが、僕ほど教員としてふさわしくない人間はいないとも思っている。けれど、学問的、専門的には、自分のこれまでのキャリアを誇りに思っている。資格には誇りがもてない。けれど、学んできた知性には誇りを感じている。
ドイツの社会人は、資格よりも、何を専攻し、何を学んだかを大切にしている。それこそが、高等教育を受けることの意味なのではないか。ドイツ人の名刺を見るたびに、こっちの人たちがうらやましく思えて仕方ない。有資格者としてではなく、学識のある人として見られているからだ。もちろん学士号がなくても、様々なそれに類する名称がある。その典型が「マイスター」であろう。
たかが名刺、されど名刺である。一度、自分の名刺を見て、そこに何が示されているのかどうか、考えてみるのも悪くはないだろう。