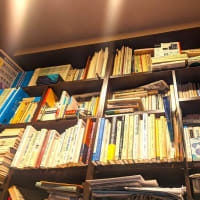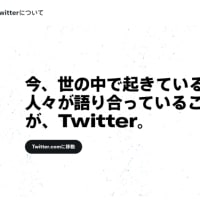「将来、どんな仕事に就こう」
「どんな仕事があるのだろう」
「就職するときに、具体的に何をどう考えたらいいのだろう」
…
そんな悩みの声をよく聴きます。
人間、いずれは何らかの仕方ではたらくことを考えなければなりません。
もちろん親が莫大な資産をもっていて、「僕は働く必要ないんだよ~」という人は除きます。
だいたいの人は、18歳~24歳くらいで一度は「就職」を覚悟していると思います。
じゃ、いったい「はたらく上で、具体的に何をどう考えたらいいんだ?」ということを、僕なりに考えて、超シンプルな図で表わしてみました。(上の画像)
いきなり独立開業する人や個人で事業を興す人は別として、どこかの組織に属して「はたらく」ということを考えると、どこかの組織や営利団体に入ることをまず考えますね。
これが、「就活」です。
どの組織にも、どの団体にも、必ずあるのが、
①開発(創造すること)
②製造(つくること)
③販売(売ること)
です。
はたらくことの「3要素」と言ってもいいかもしれません。
はたらくことを三つに分ければ、創造することとつくることと売ること、となります。
まず、自分がこの①~③のどこで働きたいかを考えることが大事かな、と思います。
僕は基本的に②のつくることが好きなのですが、実際にやっているのは①と③かなと思います💦
…
①の開発には、「クリエイティブな能力」と「専門的な知識」が必要となるかと思います。
例えば新しい「アプリ(商品)」を開発しようと思うと、「これまでに存在しないものを創造する」というクリエイティブな力と、「そのアプリを実現するためのプログラミングの技能」がどうしても必要となります。どちらが欠けてもダメですし、会社によっては、その双方のエキスパートを採用している会社もあるみたいです。
②の製造には、「注意深さ」と「持続力」と「繰り返し反復する力」が必要になってきます。
新たな商品やサービスが開発されると、それを量産していかなければなりません。多くの会社は自社工場を作り、そこでひたすら製造していきます。小さなラーメン屋さんが大きくなると、自社工場を作って、そこで量産体制に入ります。いわゆる「セントラルキッチン方式」で、麺やスープを次々に生産していき、各店舗に運んでいきます。その際に必要なのが、指定されたものを常にきちんと正しくつくり続ける力となります。
③の販売には、「コミュニケーション能力」や「プレゼンテーション能力」、つまりは「言語能力」が必要になります。言語には、バーバルなものだけでなく、ノンバーバルなもの(非言語能力)も必要になってきます。ノンバーバルなものには、「笑顔」や「清潔感」や「ルッキズム(見た目)」や「教養」や「臨機応変さ」などもあって、人間性や高い道徳性が問われてもきます。
はたらくことを考える際に、自分はどの分野で活躍したいか・活躍できるかを考えなければなりません。(大事なのは、どの分野であれば、生き生きと活躍できるかを考えることだと思います)
例えば、自由な発想が得意でコミュニケーション能力の高い人が、②の製造を仕事に選ぶと、その人にとってもキツイでしょうし、また会社としても「宝の持ち腐れ」になってしまい、結果として「儲け」を逃すことになってしまいますし、また、逆に、決められたことを毎日同じように繰り返してそれを常に注意深くチェックすることのできる人は、まさにその②の製造に合っているわけです。
中には、ホント、自然にいろんなアイデアを思いつく人がいます。次から次に新しく柔軟で自由な発想で色んなアイデアを出せる人がいます。そういう人は、やっぱり間違いなく①の開発の道を選ぶべきでしょう。
また、しゃべるのが嫌いで、黙々と手や足を動かしたい人もいると思います。しゃべっても疲れるだけ、人と話すのが得意じゃない、人のことを考えるのが辛い、そういう人は、①か②(あるいは①´の研究)を選択すべきでしょう。
…
この図をつくる前に、実はこのかたちではなくて、「一般・総合職」と「専門職(資格職)」に分けたんです。が、専門職って、基本的に①の開発に向かうか、あるいは、③´の「サービスの提供(販売)」に向かうかだなぁと思って、やめたんです。
例えば美容師さんは、専門学校等で習得してきた技術(髪の毛を切る・カラーリングする等)をお客さんに提供するサービスを売っているんですよね。介護士や心理士や税理士も同様に、習得してきた知識や技術をお客さんに提供する仕事で、広い意味では(ものではなく)無形のサービスを提供する仕事になるな、と思ったんです。
よく、親御さんたちから「なにもないよりは、資格をもっている方が有利ですよね」と聞きますが、それもまた注意が必要だと思うんですね。
コミュニケーション能力や言語的な能力が低い人が例えば、対人援助職を目指してしまうと、資格は取れたとしても、すぐに苦しみ始めると思います。資格を取ること自体には、コミュニケーション能力はさほど要らないかもしれませんが、職場に出れば、もう毎日毎日、バリバリのコミュニケーションの連続連続です。
なので、資格を取る/取らないではなく、自分が①~③のどれに就きたいか、①~③のどれならできるか、①~③のどこでなら自分が一番頑張れるか、それを考えてほしいなと思います。
…
そして、それと同時に考えたいのが、「どんな業種ではたらきたいか」「どんな分野なら楽しくはたらけるか」だと思います。
僕は食べるのが好きです。中でもお菓子・駄菓子は永遠に大好きです。なので、やっぱり僕の場合、今の仕事でなければ、「食品分野」で働きたいなぁて思いますし、具体的には、「株式会社華道」に就職したいなぁって思います(苦笑)
好きなことを仕事にすることは悪いことじゃないんです。ただ、大人たち(親や教師)の言い方が問題なんです。「将来、どんな仕事に就きたい?」って、みんな尋ねますよね。それ、やめません?
それより、「君が好きなことはなんだい?」って聞くんです。そして、子どもが例えば「洋服!」って答えたら、「じゃ、将来、新しい洋服を考えたい? 洋服を作る仕事がしたい? それとも、洋服を売っているお店の人になりたい?」って聞くんです。
そっちの方がよっぽど現実的じゃないですか?
当たり前の話だと思うのですが、今回述べた「開発」「製造」「販売」という三つの視点って、実はあまりみなに共有されていないんじゃないか?、と思って、書いてみました。
世の中の「しごと」には、三つのかたちがある。①新たに生み出すこと、②それをつくること、③それを売ること、その三つですよ、と。
***
まとめ
冒頭にも出しましたが、「将来、どんな仕事に就こう」とか「どんな仕事があるのだろう」とかと考えるとき、ざっくりと、三つのカテゴリーを思い浮かべてください。
周囲の大人たちは、具体的な職種(警察官やら保育士やら公認会計士やら税理士やら●×セラピストやら)を出してくると思いますが、まずは、自分が「好きなこと」「飽きないこと」の中で考えてほしいと思います。
音楽が好きなら、その音楽の分野で、開発、製造、販売があります。
おもちゃが好きなら、そのおもちゃの分野で、開発、製造、販売があります。
お酒が好きなら、そのお酒の分野で、開発、製造、販売があります。
やっぱりまずは「好きこそ物の上手なれ」だと思います。
そして、それに次いで、「得意こそ物の上手なれ」でありましょう。
一度きりの人生、好きなことで且つできることでお金💰を稼いでいきたいですものね。
ちなみに、かつての僕は、「音楽は好きだったけど、地道に楽器を練習する能力に欠いていた」ので、ミュージシャンの道は断念して、また、「料理は好きだったけど、つくることより食べることの方が好き過ぎた」という理由で、料理人の道も挫折しました(💦)(←せっかく調理師免許まで取ったのに…😢)
で、結局、「子どもが好きで、若者たちが好きで、且つ、教えたりコミュニケーションしたりする能力が多少人よりあった」ということで、今の仕事をしているんですよね…。
好きなだけじゃダメ。でも、好きじゃないけど能力があるからというだけでもダメ。
難しいですよね、、、