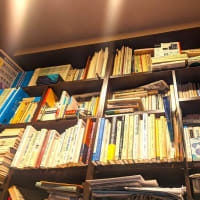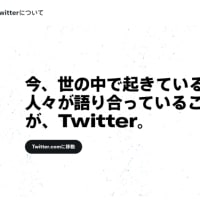教育界では、よく『他者とのコミュニケーション』が教育目標に掲げられる。
他者とのコミュニケーションは、たしかに教育の目標になり得るし、それ自体とても大切なことだと思う。人間、他者とのコミュニケーションなしには生きていけないし、他者から隔離されたところで生きることほど辛いことはない。
が、この他者とのコミュニケーションをきちんと理解している人はどれほどいるのだろうか。一部の哲学マニアをのぞいて、「他者」という問題としっかり向かい合っている人はどれだけいるだろうか。
日常的には、他者とのコミュニケーションというと、どうも、「友だちとの関係」とか、「身近な人とのよい人間関係」というふうに理解されているようなのだ。教育の文脈だと、クラスの人間関係とか、教師と生徒のかかわり合いとか、そういう次元で「他者とのコミュニケーション」を捉えている人が多い。
でも、そういう次元の話だったら、わざわざ教育目標にしなくても、みんな必死にやっているのではないか。日本人の多くは、近隣の人との調和や暗黙の了解みたいなものにやたら気を使っている。「世間」や「KY」を持ち出すまでもなく、ほとんどの人が身近な人との微妙な機微を察し合い、自分の感情を殺し、あうんの呼吸で人との交流を図っているのではないか。クラスの一体感なら、運動会や発表会や音楽などで充分体験している。わざわざ教育の目標にしなくても、十分一体感は味わっているし、学校外にも、様々な場所で一体感は味わえる(野球場やライブ会場など)。
教育目標となる他者とのコミュニケーションはそういう次元の問題ではないはずだ。むしろ、有効な人間関係とは違う、別の関係のあり方なのではないか。
クラスの中のグループ内でのよい人間関係ではなく、むしろグループ外の人間との交流こそが、他者とのコミュニケーションであるし、クラス内の交流ではなく、クラス外との交流こそが、他者とのコミュニケーションであるはずだ。あるいは、学校内のコミュニケーションではなく、学校外とのコミュニケーションがそういうコミュニケーションであるはず。つまり、内内の人間関係ではなく、内と外とのコミュニケーションこそが、他者のコミュニケーションの真意なのである。
だが、相変わらず日本の教育界(のみならずすべてにおいて)では、「内内のコミュニケーション」に気をとられているように思う。似たような人間同士がくっつき合い、ちょっとした違いを認めず、いじめたり、排除したりする。子どもたちは、他の子どもと違わないように配慮し、できるだけ角が立たないように心がける。よい人間関係をキープするために、最大限自己を抑制し、空気を読み、まわりと波長を合わせる。そういうことを止めさせようとする人はおらず、むしろそれをどんどん助長させているのが今の教育界のようにも思える。
しかし、上で書いたように、他者とのコミュニケーションは、内と外とのコミュニケーションのことである。喩えていえば、ヤンキー少年と文学少女の交流、キャバ嬢予備軍とオタク少年との交流、真面目なエリート少年と何にも考えていないキャピキャピ娘との対話、生徒会長候補の少女と無口で内気でシャイな少年との交流、そういうかかわりこそ、本当の他者とのコミュニケーションであるはずだ。あるいは、学校しか知らない生徒と施設の中で過ごすだけのお年寄りの方とのかかわりや、日本の子どもとロシアの子どもとの交流、そういう「他」との接触こそが、他者とのコミュニケーションの真の姿であるはずだ。
同属集団でうまくやっていくことが重要なのではなく、異分子集団でもめながらギリギリのところで均衡を保つようなかかわり合い、それが他者とのコミュニケーションなのだ。先日某大臣が問題発言で辞任したが、彼は日本人を「単一民族」と言っていた。そうではなく、「単一的な人々」と言えばそれほど問題はなかったのではないか。あるいは「他者を押し殺す人々」とか。そう、日本人が最も苦手とするようなコミュニケーションこそが、他者とのコミュニケーションなのだ。日本人は、おそらく無意識の中に、他者を容認せず、他者を自己に取り込み、「われわれみんな」としたい欲望があるのではないか。
だが、相手の空気が読めず、雰囲気で理解することができず、自分を殺すことでは成立せず、住んでいる場所ももっている文化も抱いている価値観も何もかも違うところに居る人こそが、他者である。そういう人とのかかわりが、他者とのコミュニケーションの中身だ。これを教えるためには、まずもって教師自身が他者とのコミュニケーションに長けていなければならない。
けれど、その教師自身が他者とのコミュニケーションができていなかったら・・・ そうしたら他者とのコミュニケーションについて豊かに教えることはできないだろう。(だからこそ、介護等体験が教員養成カリキュラムに入っているのだろう)
他者との対話に力を注いできた僕としては、この日本ではまだまだ課題が山積だと思う。同属集団内の身内的な世間話は得意であったとしても、異分子集団での緊張感溢れる対話はまだまだ日本人には難しいと思う。それを克服することは、この国際社会の中では緊急の課題だと思う。
外国人との対等のコミュニケーションも、やはり他者とのコミュニケーションが前提となっているはずだ。相手との違いを十分に理解し、相手に自分の要求を押し付けることなく、じっと相手の声に耳を傾けながら、違和感を覚えながら、じっくりと向かい合う。そういう態度でなければ、他者とのコミュニケーションなどできるはずがない。
他者とのコミュニケーションを豊かなものにするためには、まずは「内内のよい人間関係」を放棄することから始めるべきであろう。そのためには、一人になる勇気と、孤独に耐えられる強靭な精神が必要である。こうした精神を教育するというのであれば、「他者とのコミュニケーション」は立派な教育目標となることができるだろう。
まだまだ色々と考えられそうなテーマである!
(*今日行った講義の内容で気になったところを書いてみました)

![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/18/76/2fb568a5717bda67be91d432644be3e7.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/1a/8c/f1f51f662c6bb851bda1a6a047e94359.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/66/6c/ce0b6ebd716f4651da5c764d5acdc1ec.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/38/c8/62c131c5e2bec8fa8d60a9b5559e3ea8.jpg)