〜ピアノで心を育て、豊かな人生を〜
千葉県野田市の「せとピアノ教室」
講師の瀬戸喜美子です♪
ご訪問ありがとうございます♪
**********************
今日は、ヤマハミュージックメンバーズ会員限定のイベント
いい音ってなんだろう〜レクチャーコンサート〜
に行ってきました。
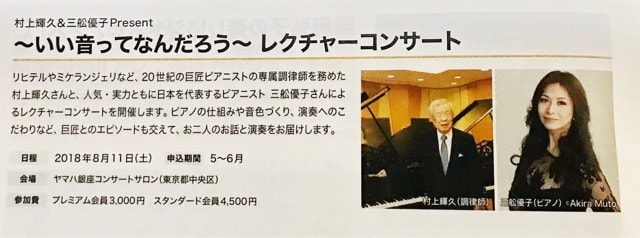
定員50名の抽選に当たっての参加

日本の調律師の第一人者である村上輝久さんと、ピアニストの三舩優子さんのレクチャーコンサートです。
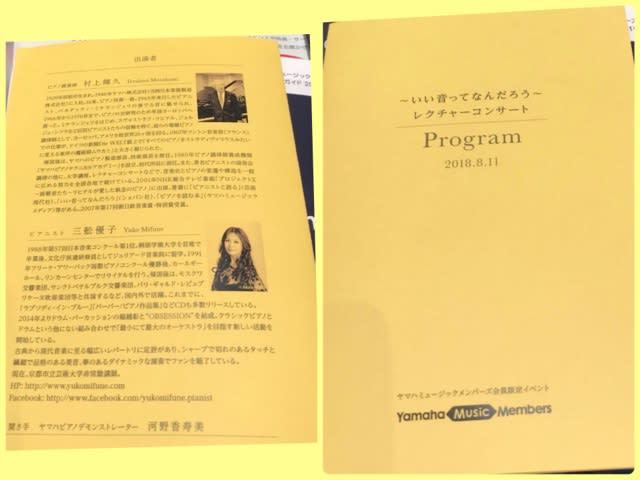
※写真撮影・録音・録画は禁止だったので、画はありません

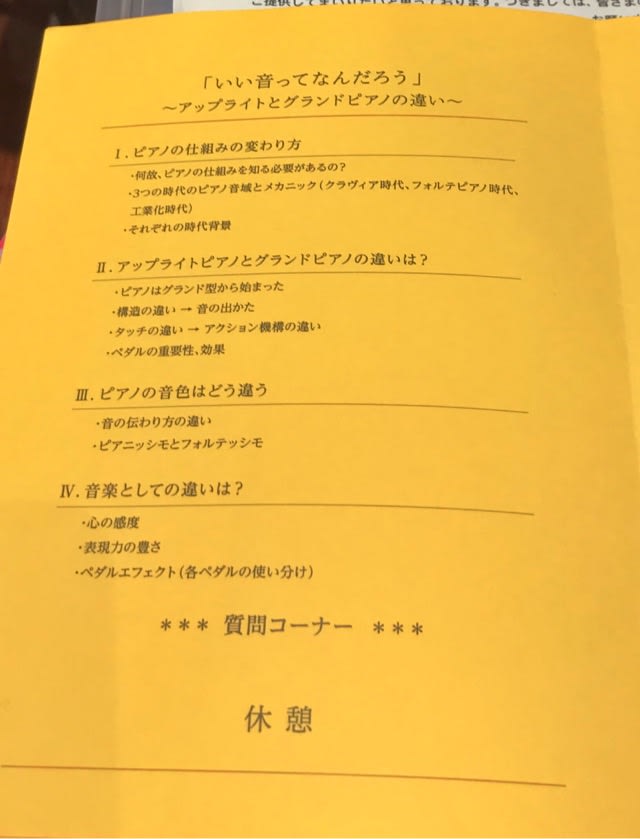
(レクチャーの抜粋)
クリストフォリがピアノを発明したのが1709年なので、ピアノができてから310年ほどたちます。
それ以前は、チェンバロ(アメリカではハープシコードと呼ぶ)でした。
チェンバロは、弦を引っ掻いて音を出す仕組み。
あまり大きな音が出ず、音量の調節もできなくて一定であり、平らです。
その分リズムに変化を出します。
バッハの音楽は、リズムがとてもしっかりしています。
チェンバロは、61鍵しかなかったので、音域もせまいです。
クリストフォリは、弦をハンマーで叩く仕組みを作りました。
現代では、木にフエルトを巻いていますが、当時は皮を巻いていたそうです。
鍵盤が増えていったのは、ベートーヴェンが作曲する上で、「もっと鍵盤を増やせないか」と要求したおかげだということは、知られています。
ベートーヴェンの作品をみていくと、音域が広くなっていくのがわかります。
ショパンやリストの時に88鍵になり、それからずっと88鍵です。
それは、人が聞き分けられて心地よい音の、最高音と最低音の限界だからだそうです。
モーツァルトの頃はまだ足踏みペダルはなく、レバーペダルでした。
ベートーヴェンが『月光ソナタ』を作る直前に足踏みペダルが作られ、普及していきました。
『月光ソナタ』は、足踏みペダルができたからこそ生まれた曲なのですね。
・・・・・・
ピアノの形は本来グランド型ですが、1700年代後半から起こった産業革命により、ピアノも工業化され、場所をとらないアップライト型が大量に作られました。
そのことによって、一般の家庭にもピアノが置かれることとなりました。
ちょうどロマン派の時代です。
グランド型とアップライト型の大きな違いは、弦の方向です。
グランド型は、床に対して平行に張られているので、弦を叩くハンマーは上下に動きます。
アップライト型は、弦がタテに張られてますから、ハンマーも立っていて前後に動きます。
ハンマーの動きは、グランド型では1秒間に14回ほど(計算上。実際弾くとなると10回位)、アップライト型では半分の7回です。
ペダルの機能も、グランド型とアップライト型では違います。
グランド型は、音が下へ向かい、床に跳ね返って上へ行く。フタにぶつかり、外へ向かうんだそうです。
アップライト型は、音は後ろへ向かいます。
アップライトピアノは、壁にくっつけず、少し空間をもたせて置くのがよいです。
・・・・・
村上さんはほかにも、世界的なピアニスト、ミケランジェリやリヒテル、ポリーニなどとのエピソードなどもお話しくださり、とても楽しい時間でした。
休憩をはさんで、三舩優子さんのコンサート。
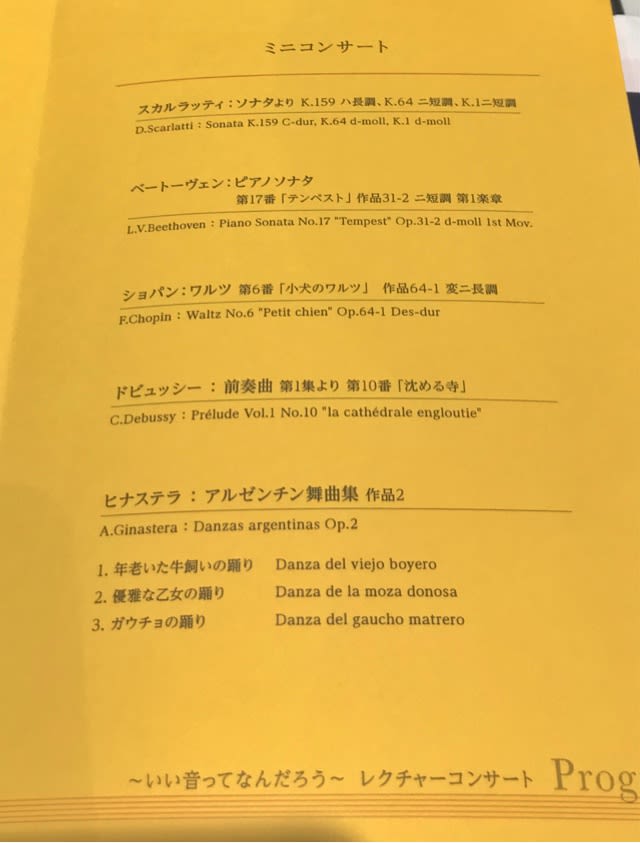
小さい頃から四期の時代(バロック・古典・ロマン・近現代)の音楽を学んできたという三舩さんは、「時代によって曲を引き分けられるようになりたい」と思って研鑽を積んでこられたのだそうです。
バロック時代のスカルラッティ「ソナタ」3曲は、バロックペダルを使って♪
古典時代のベートーヴェン「テンペスト 第1楽章」は、ベートーヴェンペダル(たとえにごってしまっても、ベートーヴェンが指示したペダルは踏まなくてはならない)にも注目♪
ロマン派時代のショパン「小犬のワルツ」♪
近代のドビュッシー「沈める寺」は、倍音がよくわかる曲♪
現代のヒナステラ(アルゼンチン)はピアソラの先生でもあった人。「アルゼンチン舞曲集」から3曲♪
アンコールは、ピアノの魅力を最大限に生かしているという、シューマン=リストの「献呈」を弾いてくれました。
どの曲も素晴らしい演奏でした!!
そして時代ごとに1曲ずつ演奏するこのスタイルは面白いと思いました。
参加できてよかったです☆
**********************
お問い合わせ・体験レッスンご希望の方は、入会金がオフになるお問合せフォームからどうぞ。
お問合せフォーム⇒コチラ
ホームページは、コチラ
♪お気軽にお問い合わせください♪
![]() にほんブログ村 ←ランキングに参加しています。ポチっと押して下さるとうれしいです!
にほんブログ村 ←ランキングに参加しています。ポチっと押して下さるとうれしいです!






















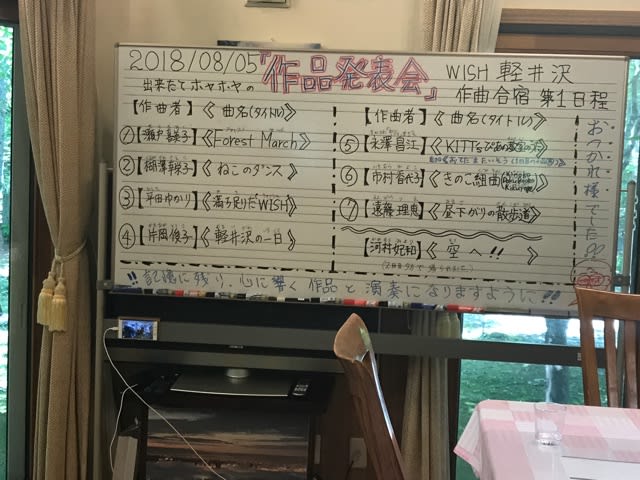
























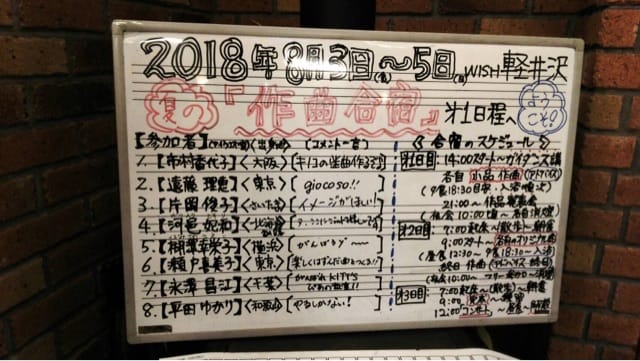
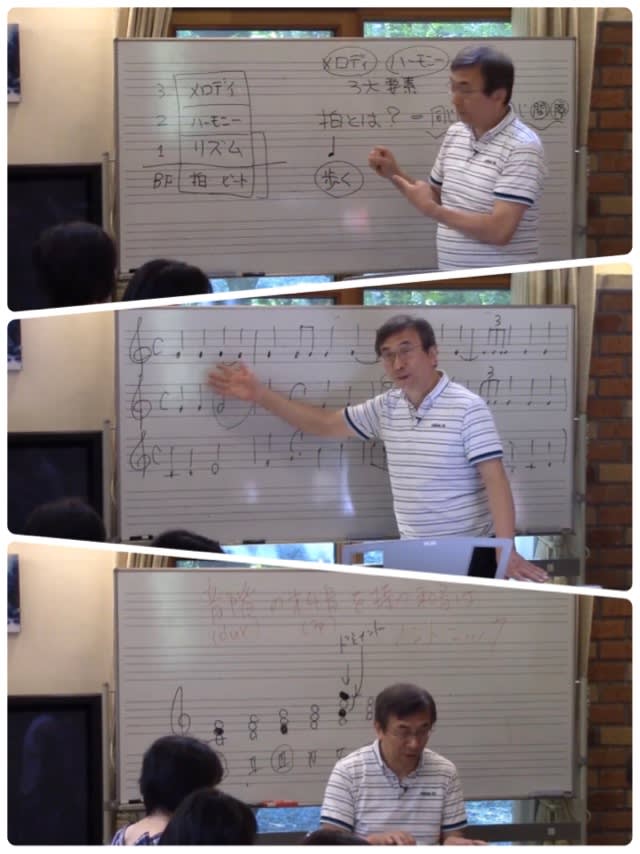



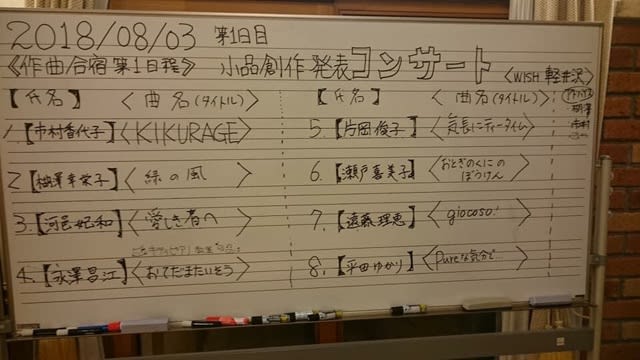






 )
)






