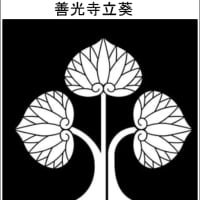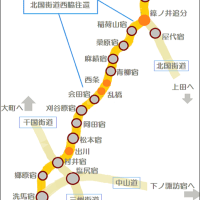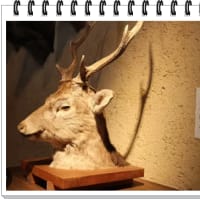指扇付近 ・・・散策 地名の裏を覗くと・・・
 指扇駅(駅所在地は宝木になる)転用
指扇駅(駅所在地は宝木になる)転用
大宮から川越に向かう埼京線の途中の駅に、「指扇」という名の駅があります。
その土地の名前は、”妙”で、かつ極めて美しい。
この指扇の地区内に、特徴のある地区名が見受けられます。枇杷島と五味貝戸という地名です。さらに、五味貝戸からは、貝塚が発見されています。まず、貝塚があって、そこから五味貝戸の名がついたのだと思われます。そうだとしたら、古代から中世まで、ここの地区の近くまで、海が迫り上がってきていたと思われます。この付近で発見された貝塚は、平方(上尾)には、昔貝塚村が存在し、また荒川対岸の富士見市水子に、60ヶ所に及ぶ貝塚が発見されています。川越の小仙波にも貝塚跡が発見されています。・・・昔の海岸線の変遷は、水子貝塚資料館(富士見市)に行くと展示されているそうです。
指扇の地形を見てみると、台地を形成しています。台地の奥は、湧き水が豊富な井戸尻という地区もあります。まだ鴨川が出来る前の事、湧き水が、小川となって海に流れ込んでいた。小川は沿岸の土を運び、砂洲を形成していた。沖には、少し高台の琵琶島が浮かんでいた。・・・こんな風景が想像できます。

 枇杷島公園
枇杷島公園
・・枇杷島は・県道2号線脇の土屋中学の並びに枇杷島公園があり、”びわじま”の名を残している。

 五味貝戸貝塚
五味貝戸貝塚
・・五味貝戸は・県道2号線の五味貝戸からプラザへの境界あたりに栄小学校があり、北門の前の塚で貝塚が発見されたそうです。
指扇の地名の扇の方は、”砂洲”+”沖”がなまって、さしおうぎ(=指扇)になったのかも知れません。あるいは、貝塚あたりから段丘で傾斜地になっており、遠目に扇の形に見えたのかも知れません。今では住宅が密集し、斜面の形をうかがい知ることは不可能になっています。砂洲自体が扇に似ていた可能性もあります。それで、”砂洲”+”扇”、指扇になった。
いずれにしても、江戸の頃から、この美しい地名の呼び名で「指扇」が生まれたようです。
参考:指扇村由来紀
現さいたま市西区にある指扇地区は古くは指扇村と言い指扇,宝来、指扇領辻、指扇領別所、峰岸、中釘、高木、清河寺、西新井、内野本郷、五味貝戸や下郷などの地区からなる村であった。村名の由来は諸説が有っていまだ確定されてないように思われる。
○一番有名なのは、山之内一唯が大阪冬の陣で軍功があったので徳川秀忠から扇で指して「この地を与える」と言われた説である。古老からは家康からもらったと聞いているが正式には史実では徳川秀忠からが正しいと思う。伊能忠敬記念館でみた地図に指扇は無かった。[大日本沿海輿地全図]には「差扇領十九ヶ村」とある。安政三年(1856)頃の武蔵国全図には「指扇」とある。「差扇」とも記されることもある。
○第2の説は指扇には大きな木があって聞かれるとその木の方を指したので、「指し大木」それが「さしおおうぎ」に成ったという説もある。
○第3の説では これが古くからの言われと思われるものであるが、指扇地区の南に枇杷島と言われる高い丘があるが昔は海の中に有って赤土で丸く琵琶のように見えたので枇杷島と呼ばれていたのではないかと思う。その先は沖であった。そこに漁のために棒が沢山さしてあった。置き針を着けた目印の棒のことかもしれない。あるいは魚をとるために筌(うけ、ウケ)と言われる竹や葛で作ったワナで魚が入ったら出られないような仕掛けである。昔良くそれを仕掛けて置いて魚を捕った記憶がある。これを流されないように縄で棒につないで置くための棒かも知れない。それで「刺し置き」「刺し沖」と呼ばれている内に「さしおき」となり「さしおうぎ」となったと言う説である。
・・・(以上は横田米作著「指扇村の由来」より)