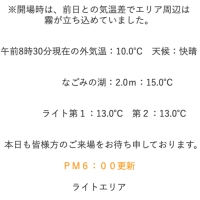日経に「白黒では蛇を見つけにくく、カラーだと容易でそれは蛇をみつけるため」という研究結果が記載されていたがなにか間違えていると思う。
研究結果ではヒトを含む猿、つまり類人猿が蛇を本能的に怖れる原因の解明に繋がると述べ、類人猿の高度な色彩感覚は蛇を見つける為に後天的に取得したという解釈だが、類人猿は蛇を見分けるために色彩感覚を得たのではないはずだ。
まず、脊椎動物で最も原始的な魚類で考えてみよう。
魚類は近紫外領域の感度を持っている。可視光に対する感受性がある。一方赤い光に対しては感度が。その低い理由は水中では赤外及び赤い光が吸収されて青い光が強くなるためであろう。つまり、関知できない可視光より長波長の赤外光は始めから感知する能力がなかった。また、青い光の中でちょっとした違いを見分ける為には近紫外の感度が必要となる。受光素子で言えばRGB+Vとなる(Rは低いのかもしれないが)。
次に鳥類で考えてみよう。
基本的に非常に視力が良い。そして夜間の低い光量では見えなくなる鳥目だ。また、耳もなく聴力は良くないはずだ。聴力はそれ程でもないのは耳がないことでわかる。ほとんど不要なのだ。だから、ばかでかい声で鳴く。さえずりというよりも声がでかすぎる。
恐竜と祖を等しくするということは当時は優先種のため昼行性だったのだろう。魚類時代に得られなかった赤外は関知できないが可視光から紫外までの光は十分に関知できていたはずだ。受光素子がRGB+Vと考えると分解能が高いから高度からのちょっとした違いを見分けるのに役立つだろう。さらに昼行性ということは明るい光の中で十分な光量を得る様な目の仕組みなんだろう。まISO100みたいなものか。一方ほ乳類は後述する様に夜光性の時期がある。その時期にも視力があったので視力ISO800とかISO1600みたいなものだろう。つまり夜間の感度が高いが光量が高くなると全部ぼやける。だから絞りで調節する訳だ。鳥類は明るい所を絞りで絞る必要はないのだろう。
類人猿を含む哺乳類で考えてみよう。
魚類と違って近紫外領域の感度が低い。実際我々は青に対して微妙な区別はあまりできない。濃淡の区別はつくが。
これは恐竜が跋扈していた頃に夜行性になったことによるのだろう。まず光が弱いので高感度の受光素子が必要となる。つまり上述のISO800/1600みたいなものだ。そして聴力が鳥類よりも必要になる。一方明け方や夕方は赤い光があるが、これは紫外線や青い光は大気圏を通る距離が長いため空中のチリ等に散乱されて地上に届かないためであるのはよく知られている。つまり、夜行性になると朝夕の赤い光だけが重要になり、光量の低い青や紫外は不要なので感度を失ったのだろう。猿から進化した人類は緑色の感度が高く、微妙な差を見分ける。これは緑色の強い環境つまりジャングル等の葉っぱの多い所で長い間過ごしたことを意味する。遠くまで見渡す必要はない。その後、草原に出て、遠距離を見渡す必要が生じた。緑は少なく、赤系統の光が重要になる。この辺は鳥類の視覚との比較が歴史的に面白いはずだ。
ヒトや猿が色彩感覚を持つのは緑の世界に育ち、草原に出て赤が必要になったこと、そしてたまたま緑が可視光のど真ん中の波長帯であっただけのこと。
さらに、夜間になると白黒っぽく見えるのは赤色光の感度だけがあって他(緑や青)の情報がないからだろう。
さて、白黒とカラーの情報量は全く異なることを無視した先の論文は悲しい。保護色の概念もない。白黒であればヤマカガシの様な警戒色も認識できない。
だから幼児は気づかないのだ。
あほらし。
研究結果ではヒトを含む猿、つまり類人猿が蛇を本能的に怖れる原因の解明に繋がると述べ、類人猿の高度な色彩感覚は蛇を見つける為に後天的に取得したという解釈だが、類人猿は蛇を見分けるために色彩感覚を得たのではないはずだ。
まず、脊椎動物で最も原始的な魚類で考えてみよう。
魚類は近紫外領域の感度を持っている。可視光に対する感受性がある。一方赤い光に対しては感度が。その低い理由は水中では赤外及び赤い光が吸収されて青い光が強くなるためであろう。つまり、関知できない可視光より長波長の赤外光は始めから感知する能力がなかった。また、青い光の中でちょっとした違いを見分ける為には近紫外の感度が必要となる。受光素子で言えばRGB+Vとなる(Rは低いのかもしれないが)。
次に鳥類で考えてみよう。
基本的に非常に視力が良い。そして夜間の低い光量では見えなくなる鳥目だ。また、耳もなく聴力は良くないはずだ。聴力はそれ程でもないのは耳がないことでわかる。ほとんど不要なのだ。だから、ばかでかい声で鳴く。さえずりというよりも声がでかすぎる。
恐竜と祖を等しくするということは当時は優先種のため昼行性だったのだろう。魚類時代に得られなかった赤外は関知できないが可視光から紫外までの光は十分に関知できていたはずだ。受光素子がRGB+Vと考えると分解能が高いから高度からのちょっとした違いを見分けるのに役立つだろう。さらに昼行性ということは明るい光の中で十分な光量を得る様な目の仕組みなんだろう。まISO100みたいなものか。一方ほ乳類は後述する様に夜光性の時期がある。その時期にも視力があったので視力ISO800とかISO1600みたいなものだろう。つまり夜間の感度が高いが光量が高くなると全部ぼやける。だから絞りで調節する訳だ。鳥類は明るい所を絞りで絞る必要はないのだろう。
類人猿を含む哺乳類で考えてみよう。
魚類と違って近紫外領域の感度が低い。実際我々は青に対して微妙な区別はあまりできない。濃淡の区別はつくが。
これは恐竜が跋扈していた頃に夜行性になったことによるのだろう。まず光が弱いので高感度の受光素子が必要となる。つまり上述のISO800/1600みたいなものだ。そして聴力が鳥類よりも必要になる。一方明け方や夕方は赤い光があるが、これは紫外線や青い光は大気圏を通る距離が長いため空中のチリ等に散乱されて地上に届かないためであるのはよく知られている。つまり、夜行性になると朝夕の赤い光だけが重要になり、光量の低い青や紫外は不要なので感度を失ったのだろう。猿から進化した人類は緑色の感度が高く、微妙な差を見分ける。これは緑色の強い環境つまりジャングル等の葉っぱの多い所で長い間過ごしたことを意味する。遠くまで見渡す必要はない。その後、草原に出て、遠距離を見渡す必要が生じた。緑は少なく、赤系統の光が重要になる。この辺は鳥類の視覚との比較が歴史的に面白いはずだ。
ヒトや猿が色彩感覚を持つのは緑の世界に育ち、草原に出て赤が必要になったこと、そしてたまたま緑が可視光のど真ん中の波長帯であっただけのこと。
さらに、夜間になると白黒っぽく見えるのは赤色光の感度だけがあって他(緑や青)の情報がないからだろう。
さて、白黒とカラーの情報量は全く異なることを無視した先の論文は悲しい。保護色の概念もない。白黒であればヤマカガシの様な警戒色も認識できない。
だから幼児は気づかないのだ。
あほらし。