
色々と忙しいので普通に45分、飛ばして30分のなごみの湖に行く時間が取れない。
ライトエリア2時間は可能だろうけど、上の池で5番を思い切り曲げる引きを堪能したい。
添付図は最新のなごみの湖の水温解析図。早朝気温が10℃を切ることも多い信楽近郊(標高約400m)なので現在ターンオ-バー真っ盛り。
先々週末の雨と今週始めの雨のせいで水温は15-16℃に低下。どこもかしこも同じ水温になっている。
雨のおかげで上の池のさらに上流にある堰堤の汚水も流れ落ちたのか、魚の活性は上がっている。前回10月の頭に行った頃はまだ「暖かい水」が上から流れているので堰堤下には白い泡が出来ていた。その水も流れ落ちたのだろう。
現在はルースニングでも棚1m程度。シンキングリトリーブで入れ食いという絶好調の様子。だいたいこういう時には仕事で行けないのが辛いところだ。
こういうときならソフトハックルを引いても良い釣りが出来るだろうし、ドライにも出るだろう。
表水温が16℃を切るとあとは人のプレッシャ過多が表層から魚を奪う。でも適度に沈めて引けば出る。
水温が下がると酸素濃度が増える。これはヘンリーの法則で、サイダーの原則である。ヘンリーさんが作ったのではなく関係を導き出しただけ。分子論的に解説すると高温になると気体分子の動きが液体分子の動きを越えるため、表面から離脱する。同じエネルギーを与えると分子量の小さいモノほど速くなるので脱出速度を超えると行っても良い。
だから高水温になると金魚はアップアップする。ニジマスはロケットジャンプだ。これは酸素不足を端的に示している。低温下でこういう行動を取らないのは十分な酸素が溶解しているからだ。
一般に池・湖沼では「水草」が酸素供給源として重要になる。植物プランクトンが繁茂すると余り良くない。昼間は酸素供給者だが夜間は酸素消費者。さらに昼間も表層で光エネルギーを奪い取るため中下層に光が届かない。よって酸素不足を招く。金魚養殖池などの黄緑色のアオミドロだらけの水はそういう状態です。
今のところなごみの湖は黄緑色に変色することはなく、暫く雨がないと一気に2m程度まで透明度が上がるのでこの心配は不要だろう。水底の水草からの酸素供給は小さいだろう。
いずれにしても最近の温度は釣りやすくなっている。これから先はいつ温度がひっくり返るのかが楽しみだ。
・現在のターンオーバーが消失して底が4℃になる時期はいつか。
・底よりも表層が低温になる時期はあるのか。
・冬季も水温躍層は出来るのか。
そして魚の棚がどこになるのか。新着情報と水温を見比べながら脳内フィッシングを楽しみましょう。
私が渓流そのものへ行かずに管理釣り場、特になごみの湖に足を運ぶ理由は何だろう。
・便利(近い)
・大物が釣れる(魔王クラスは少ないが)
・そこそこロケーションがよい。
・遠投ができる。
・魚のコンディションがよい(50cm程度の鱒が思い切りジャンプ)
こんな所か。
確かに渓流は美しくて心地よい。しかし・・・
・駐車場は完備されていない。
・釣りやすい時期に殆どの魚が抜かれている。
・釣りやすい所は鮎区間。
・日帰りで気軽に楽しめない。
と考えるとC&R区間の佐々里や天川がよさそうだが、
・佐々里は規模が里川で何かピンと来ない。
・天川は異様に摺れていると聞く。
・それにどちらも片道2Hコース・・・。
そこまでするのなら大台ヶ原下の源流に入ってもよいけど下手したら遭難の危険もあるし、魚は結構抜かれている。わざわざ信州や美濃に行くのも遠い。
とネガティブ要素しか浮かばない。
で、他の管理釣り場はどうかというと
・滋賀県北部の浅くて小さい池はイマイチで二度と行く気がしない。
・滋賀と京都の境目は悪く無さそうだが、2H以上かけて行く気がしない。
・京都市北端の小さい池はBBQが楽しみだ(笑:又行きたい)。
・三重県北部は遠い。(片一方は何かおかしくなってきている)
・東吉野は・・・狭い。
・滋賀県東端は・・・狭い。
最後の二つは水がとっても綺麗だが、もう一つ行く気にならない。
これは川の中に堰堤で変な池を作っているためだ。魚が見えて釣りやすいのだがLure, Fly向きではない。
大戸川(ここの管理人がなごみの湖の管理人になっている)は川のルアーを結構楽しめました。
ここは(今は魚の規模が変わったけど)大きなニジマスが流れに乗って一気に下るのでまるでアラスカ・NZ気分。今の管理池の釣り方ではなく、流れを使った釣り方で楽しめました。
主に段差の上流から黒いスピナーを落として白泡の中で定位。たまに誘うだけ。これでいきなりガツンと。これはアッパークロスでやるとまず無理。沈むジグやスプーンでやっても根掛かりするか、白泡の上を舐めて魚が気づかないままポイントを流れるだけ。ダウンクロスならスピナーに限らす有効でした。色は黒かな。
このやり方のメリットは魚から人は白泡で見えないことと、ルアーを上流から落ちてポイント上で定位できること。糸ふけで沈めたり下流へ流したり色々できる。
いわゆるリトリーブは全く不要というより川の流れで泳がすやりかたです。
ただ、ある程度の水量がないと難しいけど大抵のポイントで有効でしょう。魚は白泡の裏に潜んでいるのです。
落ち込みがものすごく深いポイントではアッパークロスで脇から沈めても行けますが、ダウンクロスでジグを使うってのも有りです。これは確実に底の大物をゲットできました。底を叩くと先行者の有無に限らずでかいのを後から拾えるのもメリットでした。
なごみの湖ではそういう釣りは出来ませんが、ヒレピンなニジマスが桟橋をくぐって後ろでジャンプしたり、リールファイトを楽しめるのはココくらいかな。
でかい魚って鯉やニゴイもでかいけど・・・。ちょっと違う。
(村田基氏が池原で鯉のサイトフィッシングしてたなぁ。あれはアレで楽しそう(笑)。)
確かに鯉の引きは凄い。でもニジマスのジャンプと「ラン」はない。
ニゴイはもっと地味だ。のたうつけどね。
というわけで私はなごみの湖へ通う。
ライトエリア2時間は可能だろうけど、上の池で5番を思い切り曲げる引きを堪能したい。
添付図は最新のなごみの湖の水温解析図。早朝気温が10℃を切ることも多い信楽近郊(標高約400m)なので現在ターンオ-バー真っ盛り。
先々週末の雨と今週始めの雨のせいで水温は15-16℃に低下。どこもかしこも同じ水温になっている。
雨のおかげで上の池のさらに上流にある堰堤の汚水も流れ落ちたのか、魚の活性は上がっている。前回10月の頭に行った頃はまだ「暖かい水」が上から流れているので堰堤下には白い泡が出来ていた。その水も流れ落ちたのだろう。
現在はルースニングでも棚1m程度。シンキングリトリーブで入れ食いという絶好調の様子。だいたいこういう時には仕事で行けないのが辛いところだ。
こういうときならソフトハックルを引いても良い釣りが出来るだろうし、ドライにも出るだろう。
表水温が16℃を切るとあとは人のプレッシャ過多が表層から魚を奪う。でも適度に沈めて引けば出る。
水温が下がると酸素濃度が増える。これはヘンリーの法則で、サイダーの原則である。ヘンリーさんが作ったのではなく関係を導き出しただけ。分子論的に解説すると高温になると気体分子の動きが液体分子の動きを越えるため、表面から離脱する。同じエネルギーを与えると分子量の小さいモノほど速くなるので脱出速度を超えると行っても良い。
だから高水温になると金魚はアップアップする。ニジマスはロケットジャンプだ。これは酸素不足を端的に示している。低温下でこういう行動を取らないのは十分な酸素が溶解しているからだ。
一般に池・湖沼では「水草」が酸素供給源として重要になる。植物プランクトンが繁茂すると余り良くない。昼間は酸素供給者だが夜間は酸素消費者。さらに昼間も表層で光エネルギーを奪い取るため中下層に光が届かない。よって酸素不足を招く。金魚養殖池などの黄緑色のアオミドロだらけの水はそういう状態です。
今のところなごみの湖は黄緑色に変色することはなく、暫く雨がないと一気に2m程度まで透明度が上がるのでこの心配は不要だろう。水底の水草からの酸素供給は小さいだろう。
いずれにしても最近の温度は釣りやすくなっている。これから先はいつ温度がひっくり返るのかが楽しみだ。
・現在のターンオーバーが消失して底が4℃になる時期はいつか。
・底よりも表層が低温になる時期はあるのか。
・冬季も水温躍層は出来るのか。
そして魚の棚がどこになるのか。新着情報と水温を見比べながら脳内フィッシングを楽しみましょう。
私が渓流そのものへ行かずに管理釣り場、特になごみの湖に足を運ぶ理由は何だろう。
・便利(近い)
・大物が釣れる(魔王クラスは少ないが)
・そこそこロケーションがよい。
・遠投ができる。
・魚のコンディションがよい(50cm程度の鱒が思い切りジャンプ)
こんな所か。
確かに渓流は美しくて心地よい。しかし・・・
・駐車場は完備されていない。
・釣りやすい時期に殆どの魚が抜かれている。
・釣りやすい所は鮎区間。
・日帰りで気軽に楽しめない。
と考えるとC&R区間の佐々里や天川がよさそうだが、
・佐々里は規模が里川で何かピンと来ない。
・天川は異様に摺れていると聞く。
・それにどちらも片道2Hコース・・・。
そこまでするのなら大台ヶ原下の源流に入ってもよいけど下手したら遭難の危険もあるし、魚は結構抜かれている。わざわざ信州や美濃に行くのも遠い。
とネガティブ要素しか浮かばない。
で、他の管理釣り場はどうかというと
・滋賀県北部の浅くて小さい池はイマイチで二度と行く気がしない。
・滋賀と京都の境目は悪く無さそうだが、2H以上かけて行く気がしない。
・京都市北端の小さい池はBBQが楽しみだ(笑:又行きたい)。
・三重県北部は遠い。(片一方は何かおかしくなってきている)
・東吉野は・・・狭い。
・滋賀県東端は・・・狭い。
最後の二つは水がとっても綺麗だが、もう一つ行く気にならない。
これは川の中に堰堤で変な池を作っているためだ。魚が見えて釣りやすいのだがLure, Fly向きではない。
大戸川(ここの管理人がなごみの湖の管理人になっている)は川のルアーを結構楽しめました。
ここは(今は魚の規模が変わったけど)大きなニジマスが流れに乗って一気に下るのでまるでアラスカ・NZ気分。今の管理池の釣り方ではなく、流れを使った釣り方で楽しめました。
主に段差の上流から黒いスピナーを落として白泡の中で定位。たまに誘うだけ。これでいきなりガツンと。これはアッパークロスでやるとまず無理。沈むジグやスプーンでやっても根掛かりするか、白泡の上を舐めて魚が気づかないままポイントを流れるだけ。ダウンクロスならスピナーに限らす有効でした。色は黒かな。
このやり方のメリットは魚から人は白泡で見えないことと、ルアーを上流から落ちてポイント上で定位できること。糸ふけで沈めたり下流へ流したり色々できる。
いわゆるリトリーブは全く不要というより川の流れで泳がすやりかたです。
ただ、ある程度の水量がないと難しいけど大抵のポイントで有効でしょう。魚は白泡の裏に潜んでいるのです。
落ち込みがものすごく深いポイントではアッパークロスで脇から沈めても行けますが、ダウンクロスでジグを使うってのも有りです。これは確実に底の大物をゲットできました。底を叩くと先行者の有無に限らずでかいのを後から拾えるのもメリットでした。
なごみの湖ではそういう釣りは出来ませんが、ヒレピンなニジマスが桟橋をくぐって後ろでジャンプしたり、リールファイトを楽しめるのはココくらいかな。
でかい魚って鯉やニゴイもでかいけど・・・。ちょっと違う。
(村田基氏が池原で鯉のサイトフィッシングしてたなぁ。あれはアレで楽しそう(笑)。)
確かに鯉の引きは凄い。でもニジマスのジャンプと「ラン」はない。
ニゴイはもっと地味だ。のたうつけどね。
というわけで私はなごみの湖へ通う。














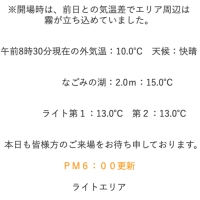





見たー?細山長司VS北米キングサーモン。
もの凄かったよー!地元のフィッシングガイドが延竿に見とれてたよー!
ってわけで影響されて日曜日はスチールヘッド狙いにつーてん湖まで行っちゃいました(笑)。
東吉野は木○ヶ森?滋賀県東端は永○寺?
この記事読みながら、家族で管釣りあてクイズしてましたー(笑)。
で、「釣りロマン」は見逃しました。
ツーテン湖では楽しめたようで羨ましいです。
いつもブログを楽しみに読ませてもらっている「ひげオヤジ」と申します。特に
なごみの湖
についての詳細な分析は、本当に無学な小生にとって「バイブル」のようなものです。
さて、今週はじめ、小生も久々に「なごみ」に釣行したのですが、その釣行記で「ならおうさん」のブログを紹介させて頂こうと考えました。小生のブログのような低劣なものに、貴兄のお名前をご披露しますこと、誠に無礼千万の極みとは存じますが、是非ともお許しいただきますよう、心よりお願い申し上げます。
もしかすると、これから「なごみ」や他の管理釣り場で、すれ違うこともあるやも知れません。(とはいえ、ヘタクソFF師の小生はライトエリアをうろついていることが多いのですが)先ずはそんな奇遇も期待しつつ、今後ともよろしくお願いいたします。
なお、私のフライ歴は浅くひげオヤジさんの足元にも及びません。
どこかの管理池等で遭遇した折はよろしくお願いします。なお、似顔絵は全く似ていませんが、新着情報でたまに撮影されています(笑)。