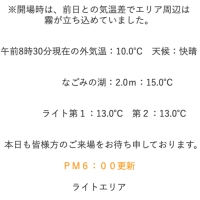B787の火災事故。GSユアサが悪い。という結論でいいのか?リチウムイオン電池はダメなのか?と考えてたらこんな記事を見た。
内容を簡単に記すと次になる。
電池
・リチウム電池は90年代にPCで充電中の発熱、発火問題があった。
・充電中の電圧変動、温度変化、圧力変化が主原因だった。
・電池内部に充電中の状態を監視する安全装置を持つ様になった。
・発熱発火事故は大きく減った。(電気自動車、HV、PCでは殆どない)
・GSユアサは安全技術でトップクラスだろう。
以上から電池の不良は考えにくい。
電源マネジメントシステム
・フランスのタレス社が電源マネジメントシステムを担当。
・タレス社は宇宙・航空・防衛関連企業である。
・高度な電源マネジメントシステムのノウハウを持っているだろう。
以上から電源マネジメントシステム不良も考えにくい。
そして記事が指摘するのは配線ミス。
・ローガン空港の燃料漏れ
・航空機(だけじゃないが)の電装系配線は「手作業」
・ヒューマンエラーの可能性は排除できない
結構大問題。
この記事の最後はエールを送る。
いいね。是非国産の大型輸送機を開発して欲しい。
さて、50機中半数が日航と全日空。つまり25機だ。ヒューマンエラーによる接続ミスはありえそうだ。
まずは充電システムの最も簡単な例「自動車」を示そう。
自動車はエンジンの発電機(オルタネーター)から常に鉛蓄電池のバッテリーを充電している。

オルタネーターからの交流出力をレギュレーターで電圧と向きを整え、メインの正極回路を介して接続。負極側はボディアース。消費電流以上の電力がバッテリーに貯められ、始動時はバッテリーから出力するという簡単な構造。
しかし、レギュレーターで電圧を調整しておかないと過剰電圧の印加でバッテリーが破損してしまう。
内容を簡単に記すと次になる。
電池
・リチウム電池は90年代にPCで充電中の発熱、発火問題があった。
・充電中の電圧変動、温度変化、圧力変化が主原因だった。
・電池内部に充電中の状態を監視する安全装置を持つ様になった。
・発熱発火事故は大きく減った。(電気自動車、HV、PCでは殆どない)
・GSユアサは安全技術でトップクラスだろう。
以上から電池の不良は考えにくい。
電源マネジメントシステム
・フランスのタレス社が電源マネジメントシステムを担当。
・タレス社は宇宙・航空・防衛関連企業である。
・高度な電源マネジメントシステムのノウハウを持っているだろう。
以上から電源マネジメントシステム不良も考えにくい。
そして記事が指摘するのは配線ミス。
・ローガン空港の燃料漏れ
非常事態で燃料を捨てる弁が誤動作(開放)したがコクピットに非表示
・ユナイテッド航空B787で配線ミス1/8 ウォール・ストリート・ジャーナル (電子版)
・米国政府認定までに電源管理の失敗で深刻な発火事故の発生・航空機(だけじゃないが)の電装系配線は「手作業」
・ヒューマンエラーの可能性は排除できない
結構大問題。
この記事の最後はエールを送る。
現在は、全世界で稼働していた約50機の787の全機が検査中だと思います。恐らくはこの配線の問題が真っ先に調査されていると思います。焼け焦げた電池の写真を見て「日本の電池が発火した。もう日本の技術はダメだ」などという声もあるようですが、私はその可能性は低いと思います。
仮に配線のミスであって、GSユアサやタレスも想定しなかったような、従ってハイテクの自己修正機能でも守れなかったような「ひどいヒューマンエラー」が原因であるならば、逆に日本の経済界は怒るべきです。仮にそうであるならば、「小型ジェット」などと生ぬるいことを言わず、製造業のノウハウが残っているうちに、日本は民生用航空機ビジネスの「最終メーカー」に名乗りを上げるべきだと思うのです。中国が767規模の機材を(色々な技術をコピーして)開発する時代です。日本がやらない理由はありません。
仮に配線のミスであって、GSユアサやタレスも想定しなかったような、従ってハイテクの自己修正機能でも守れなかったような「ひどいヒューマンエラー」が原因であるならば、逆に日本の経済界は怒るべきです。仮にそうであるならば、「小型ジェット」などと生ぬるいことを言わず、製造業のノウハウが残っているうちに、日本は民生用航空機ビジネスの「最終メーカー」に名乗りを上げるべきだと思うのです。中国が767規模の機材を(色々な技術をコピーして)開発する時代です。日本がやらない理由はありません。
いいね。是非国産の大型輸送機を開発して欲しい。
さて、50機中半数が日航と全日空。つまり25機だ。ヒューマンエラーによる接続ミスはありえそうだ。
まずは充電システムの最も簡単な例「自動車」を示そう。
自動車はエンジンの発電機(オルタネーター)から常に鉛蓄電池のバッテリーを充電している。

オルタネーターからの交流出力をレギュレーターで電圧と向きを整え、メインの正極回路を介して接続。負極側はボディアース。消費電流以上の電力がバッテリーに貯められ、始動時はバッテリーから出力するという簡単な構造。
しかし、レギュレーターで電圧を調整しておかないと過剰電圧の印加でバッテリーが破損してしまう。
ここではレギュレータを簡単にダイオードで示している。
さて、B787だ。電源マネジメントシステムと電池とを接続する訳だから、配線は最低でも下の様になるだろう。
しかもCFRPボディなので「ボディアース」を取れない。そこで、機器のノイズを考えて個別にアースを取ることになる。なお、各機器は専用アースが望ましい。

a) 出力負極(アース)
b) 出力正極
d) 充電負極
f) 電池情報送受信信号負極
b) 出力正極
この電極から出力
c) 充電正極d) 充電負極
この電極から充電
e) 電池情報送受信信号正極f) 電池情報送受信信号負極
この信号を基に飛行機本体のマネージングシステムが充電を止める。
g) 非常時安全装置制御動力正極これは飛行機本体からの充電停止が出来なかった時に電池側で充電を停止する遮断回路。
あとで回復出来る必要があるのでヒューズってわけにはいかない。
monitorとは接続されているかもしれない。
h) 非常時安全装置制御動力負極あとで回復出来る必要があるのでヒューズってわけにはいかない。
monitorとは接続されているかもしれない。
簡単に8pinコネクタが必要であるが、図で示した様に多分大電流用と制御用の統一コネクタは無い。
家電、PC、自動車等の量産機器は規格化された接続コネクタがある。
ATXメイン電源コネクタ
こういうコネクタでは接続ミスが生じにくい。というかまず生じない。あるとすれば断線だ。という事を考えると、通信用のe)~h)はこういうコネクタかもしれないが、a)~d)はがっちりとした接続ではないかと推測される。
そうするとe)~h)のコネクタ作成不良が頭をよぎる。ただし、バッテリーを回収しているから接続部は解析不能かもしれない。
またはe)~h)の機体のコントロール側で接続不良や、配線ミスが生じている可能性も捨てきれない。そうであればB社の工作技能がかなり劣化していることになる。
由々しき事態だ。
電子制御機器のワイヤーハーネス管理は結構困難なようだ。この辺はデジタルではないので、なんともいえませんが、接続ミスはありえそうだ。