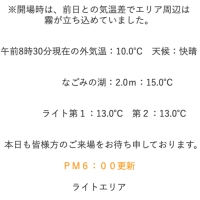Griffith's Gnatはミッジ・クラスタを模倣したフライではなく、Gnat ブヨを模倣していた。水面の見え方が結果としてミッジ・クラスタの模倣になっていたという偶然のフライである。と指摘されている。
現在はミッジ・クラスタとして#16程度がよく使用される。
フライフィッシング用語辞典によると「オリジナルがウィッチ(1901)で、グレー・パーマーまで遡れる」とのこと。
つまり、Griffithさんはこのフライへの貢献は、Griffithという響きがGrifonに近いから「なんかかっこいい」というところでしょうか。
折角なんで調べてみました。
Witch(フライフィッシング用語辞典)
タグがなければGriffith's Gnatですね。そして用語辞典によるとハルフォードのパターンを改良したものとか。
Grey Palmer(19世紀)(フライフィッシング用語辞典)
これがWitchのオリジナル。いやぁ面白いですね。
ちなみに佐藤成司氏によるとGriffith's Gnatの大型はDead chickenと身も蓋もない名称になっているらしい。
で、ちょいと考えてみた。
クラスターは虫の死骸がゴチャゴチャっと集まったものなので面積が大きくて、光量に濃淡がある。と考えられる。
となると、いわゆるデカパラとかスパイダーと呼ばれるバカでかいハックルを少ない目に巻いて、まるで傘の様に浮かぶタイプが相当しそうだ。
さらにここからは個人的な考えだが、パラシュートを頭とお尻にツインパラシュートにするとこれも微妙な感じを演出できるのでは?と。
ならば巻いてみよう。
調子に乗ったもの:頭部パラとテイルパラは両輪型 #12

水面直下から

フィッシュウィンドウ

水面

ハンプバックという方法を使ったもの1(ハックルが不足したので途中迄

水面直下から。ハックルに濃淡発生。

フィッシュウィンドウ

水面

ハンプバック型2。多分16と思われる鈎に巻いてみた。

水面直下から。

フィッシュウィンドウ

水面

ハンプバック型3。長い目のハックルをテイルのパラシュートポストに巻いてそれをヘッドで止める。そしてヘッドのパラシュートポストにしたもの

水面直下から。

フィッシュウィンドウ
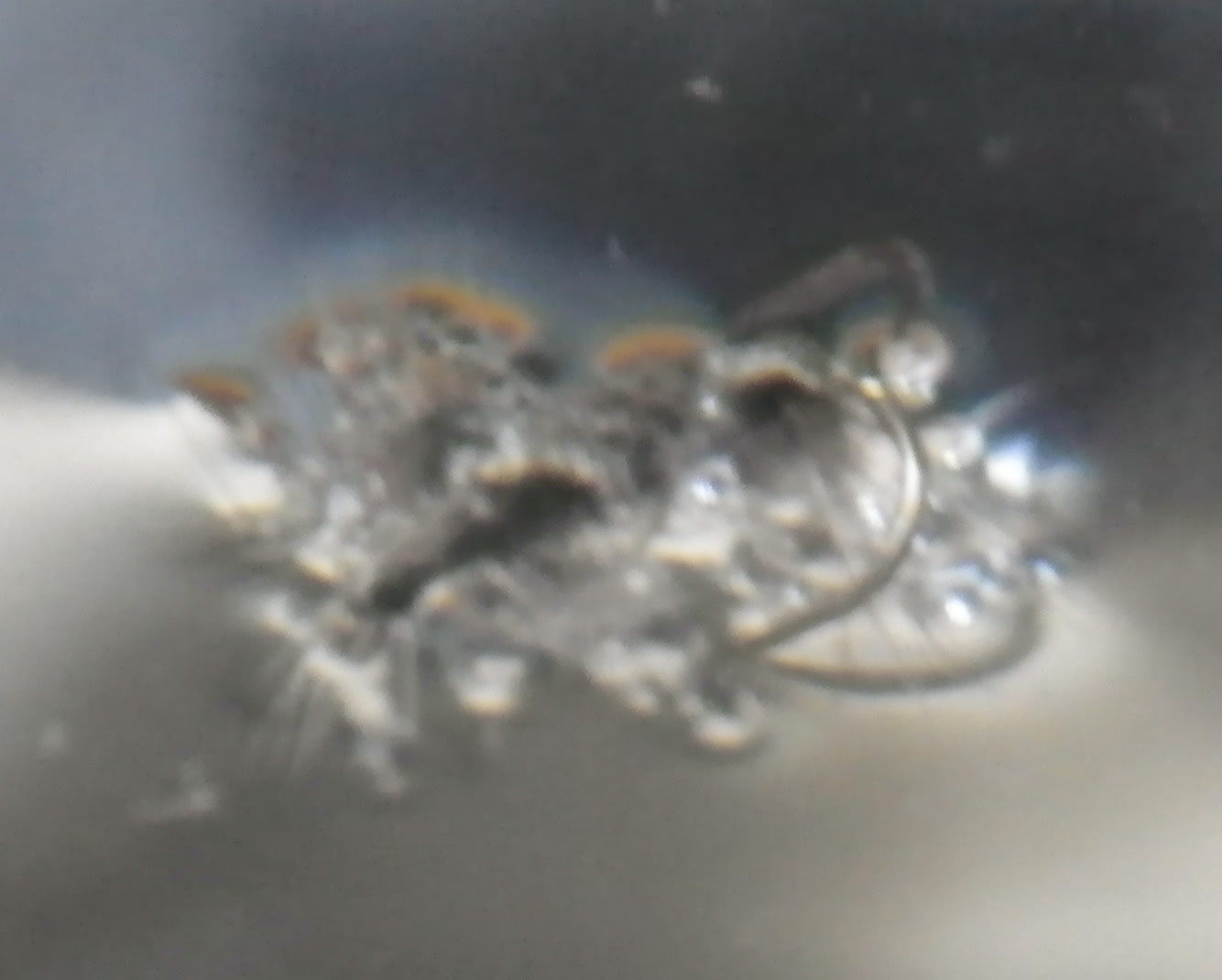
水面

ハンプバック型4。テイルのパラシュートポストを前に倒してみた。さらにボディは先達のものまね。

水面直下から

フィッシュウィンドゥ

水面

ツインパラ

水面直下

フィッシュウィンドウ

水面

こんな感じで巻いた。ボディはオストリッチ。ハックルはグリズリー。ポストはTMCの例の奴。
うーむ。ツインはいいけどポストにたくさん巻いてパーマーっぽくすると元のフライに戻ったようですね。でも巻くのはちょいと面倒なのでツインパラ程度にしておくのが良いのかもしれない。ツインパラは輸送用ヘリコプターから思いついていたってのもあります。
で、このツインポストにすると、薄いハックルを二段持つため沈みにくくそれでいてハックルの違和感を防げるかもってとこです。
ハンプバック型3 は巻くのが少し面倒だけどここまでハックルをつめなくても良かったかなぁ。
撮影はマニュアルフォーカスを駆使。画像サイズでかすぎて調整する必要があったのが面倒でした。
現在はミッジ・クラスタとして#16程度がよく使用される。
フライフィッシング用語辞典によると「オリジナルがウィッチ(1901)で、グレー・パーマーまで遡れる」とのこと。
つまり、Griffithさんはこのフライへの貢献は、Griffithという響きがGrifonに近いから「なんかかっこいい」というところでしょうか。
折角なんで調べてみました。
Witch(フライフィッシング用語辞典)
Hook Size: #14
Body: Peacock sword
Ribbing: Flat gold (maybe wire)
Tag: Ibis
Hackle: Palmar, whole body, Light honey dun
Wing: none
Body: Peacock sword
Ribbing: Flat gold (maybe wire)
Tag: Ibis
Hackle: Palmar, whole body, Light honey dun
Wing: none
タグがなければGriffith's Gnatですね。そして用語辞典によるとハルフォードのパターンを改良したものとか。
Grey Palmer(19世紀)(フライフィッシング用語辞典)
Hook Size: #14位?
Body: Peacock herl , black silk
Ribbing: gold or silver twist
Hackle: Palmar, whole body, gray or badger, grizzly
Wing: none
Body: Peacock herl , black silk
Ribbing: gold or silver twist
Hackle: Palmar, whole body, gray or badger, grizzly
Wing: none
これがWitchのオリジナル。いやぁ面白いですね。
ちなみに佐藤成司氏によるとGriffith's Gnatの大型はDead chickenと身も蓋もない名称になっているらしい。
で、ちょいと考えてみた。
クラスターは虫の死骸がゴチャゴチャっと集まったものなので面積が大きくて、光量に濃淡がある。と考えられる。
となると、いわゆるデカパラとかスパイダーと呼ばれるバカでかいハックルを少ない目に巻いて、まるで傘の様に浮かぶタイプが相当しそうだ。
さらにここからは個人的な考えだが、パラシュートを頭とお尻にツインパラシュートにするとこれも微妙な感じを演出できるのでは?と。
ならば巻いてみよう。
調子に乗ったもの:頭部パラとテイルパラは両輪型 #12

水面直下から

フィッシュウィンドウ

水面

ハンプバックという方法を使ったもの1(ハックルが不足したので途中迄

水面直下から。ハックルに濃淡発生。

フィッシュウィンドウ

水面

ハンプバック型2。多分16と思われる鈎に巻いてみた。

水面直下から。

フィッシュウィンドウ

水面

ハンプバック型3。長い目のハックルをテイルのパラシュートポストに巻いてそれをヘッドで止める。そしてヘッドのパラシュートポストにしたもの

水面直下から。

フィッシュウィンドウ
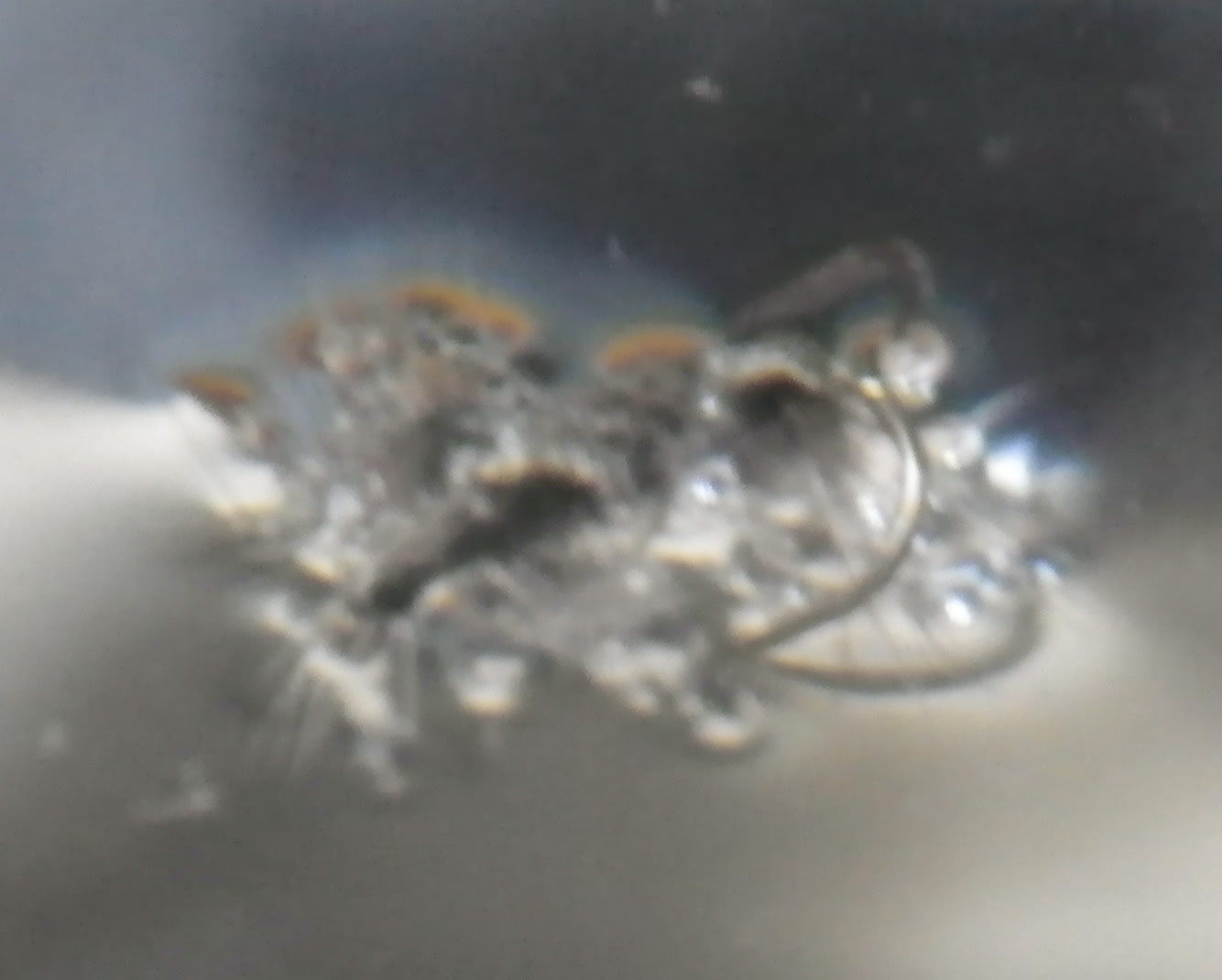
水面

ハンプバック型4。テイルのパラシュートポストを前に倒してみた。さらにボディは先達のものまね。

水面直下から

フィッシュウィンドゥ

水面

ツインパラ

水面直下

フィッシュウィンドウ

水面

こんな感じで巻いた。ボディはオストリッチ。ハックルはグリズリー。ポストはTMCの例の奴。
うーむ。ツインはいいけどポストにたくさん巻いてパーマーっぽくすると元のフライに戻ったようですね。でも巻くのはちょいと面倒なのでツインパラ程度にしておくのが良いのかもしれない。ツインパラは輸送用ヘリコプターから思いついていたってのもあります。
で、このツインポストにすると、薄いハックルを二段持つため沈みにくくそれでいてハックルの違和感を防げるかもってとこです。
ハンプバック型3 は巻くのが少し面倒だけどここまでハックルをつめなくても良かったかなぁ。
撮影はマニュアルフォーカスを駆使。画像サイズでかすぎて調整する必要があったのが面倒でした。