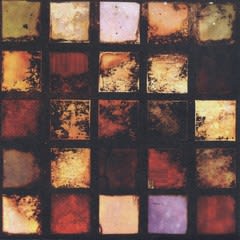『顕信の一撃』(02)で正に一撃を喰らい、その遅すぎた出会いに後悔する次第であった。何故、私は友川かずきをスルーしてきたのか。しかもその盟友、三上寛は常に聴き続けてきたのに。アホであった。思えば私がファンであるマリア観音=木幡東介(一度、対バンした事もあった)がやはり、友川かずきの影響下にあった事を承知していたのにも係わらず、聴こうともせず、観にも行かなかった事も怠惰の極みであったか。
30でミンガスを好きになった時も、40にしてピアソラのファンになった時も、特に後悔の念はなかった。しかし友川かずきだけはこれを今まで聴かなかった事を悔いた。もっと早く知るべきであった。
私が真に求めるもの、心の奥底で希求していた音楽がそこにあった。
長い間、音楽の趣味を拡げる事を使命のようにしていた。現実には叶わぬとしても、意識の上では日常を音楽で埋め尽くそうと目論む私にとって、その趣味を拡げ、必然的にその聴き方をも多様化させる事は、自然の成り行きであった。対座して音楽に向かい、その全てを腹の中に貯め込むような聴き方から音楽を耳に擦らせて心地よさに酔う聴き方まで。私はもはや音楽を日常生活のスパイスならぬバランサーとし、生に欠かせぬものとしていた。しかし、その際限無さはいつしか私の感性の中核を隠し、本質を見えにくくしていた筈だ。思い出すようにジョンコルトレーンを聴くのも、拡散する音楽リスニングの中に核心を思い起こす為であったと思う。嘗ては主食であったコルトレーンを今では他の‘イージーリスニング’の合間に聴いている。そんな私の前に友川かずきは‘コルトレーン的な中核’として顕れた。
灰野敬二、ハイライズといった極北系アーティストをリリースするP.S.Fレコードが友川カズキ(かずき改め)の7年ぶりのアルバム『花々の過失』をリリースするのが93年。メジャーレーベルに嫌気がさした友川かずきの要望だったと言う。思い起こせば私が、そのP.S.F、生悦住氏に「アレアとかジャズロックは好きじゃない」と言われたのが、その頃だ。自分のバンドのデモテープを送り、聴いていただいた感想に絡む発言であった訳だが、当然の反応であったか。生悦住氏は音楽の‘構成’や‘形’、いや、もはや‘アレンジ’という観念すら嫌悪するかのような音楽の中核のみに関心が向かっているように感じた。P.S.Fアーティストに共通する、装飾を全て剥ぎ取った魂のかたまりだけを提示するような音楽性は正に友川かずきが持つ本質そのものでもあっただろう。その意味でP.S.Fは彼にとって出会うべきにして出会ったレーベルであった。
闘病生活から復帰した友川カズキの新作『青い水 赤い水』をアマゾンで注文したが、在庫切れの返事。タワー行っても置いていない。どこにもない。これが現状か。仕方なく取り寄せを依頼し、一週間で届くが。ちゃんと品揃えせえと言いたくなる。
さて、アルバムの内容について書かねばならないが、音楽を聴けば聴くほど、書く気が失せる。相変わらず、圧倒的だ。こんな音楽を前に一体、何が書けるのか。
強烈な肉声が時には低く、或いは高らかに突き刺さる。これをアルトー的、中也的、コルトレーン的な<叫び>と同一視するのは容易いが、やはり、音楽的な完成度にまず、感心する。‘形’をものともしない‘叫び’、‘魂’が赤裸々に放射される友川ミュージックの中に、むしろ音楽的様式美を感じる。それは音楽の‘形’が楽曲形成によってなし得るのではなく、友川カズキの発声される言葉から導かれる必然的な音のピラミッドのように成り立つ、まぎれもない‘形式’のような感触である。
その様式美を私はある‘余裕’の顕れと見る。その‘余裕’はメジャー時代の初期活動期と比べれば明らかだ。初期衝動的表現から音楽的成熟に向かったという‘余裕’の事ではない。P.S.F以降の友川ミュージックに歌が音に取り囲まれる最良の形を成す事によってより、激しく、衝動的になるというマジックを見るのである。
バックの演奏過剰、アレンジ過剰が目立ったメジャー時代、そんな制作側が用いた手法の失敗を友川かずきの歌と声が相殺してみせる瞬間が多くあった。しかしその相殺は友川かずきの‘過剰’を手段とした意図的表現によるものであり、それを意図せざるを得ない友川かずき自身のフラストレーションは想像に難くない。従って、友川かずきは自然体に導かれた激越さこそを、目指すようになったのではないか。その時、歌を巡る演奏の形とはどのようなものになるのか。自分の歌にはいかなるバック演奏も合わない。ただ、石塚俊明(ds,per)のみが単独の語り手として自らの歌に対峙し、二人で一つの世界を作り得る事を認識したのだろうか。かくしてP.S.F以降の形態は歌一本、あるいは+リズムというシンプルなものに行き着き、その基盤から最低限のパートを加える形式が採られていく。
『青い水 赤い水』に於いて、言葉がその音楽の中心に在り、既に言葉だけで音楽になっている。従ってその様式とは言葉をフォローするサウンドの集合ではなく、運動性の高い言葉というボールを四方八方からはね返し合うような音達が絶えず動きながら全体を創り続けているようなものと映る。友川ミュージックに不可分な要素である石塚俊明(ds,per)、永畑雅人(g)は友川の言葉をはじき飛ばすような演奏をしている。そんな動性こそが、友川ミュージックのどっしりした骨格感、立体的な様式美を実現しているようだ。
脳味噌もカラダも脆弱ときた
運気の兆しもさっぱりだ
さなり一番 でたとこ勝負だ
ケムリもアルコールも打っちゃって
酔いなき ざれ者の句読点
君よ貧しき使者よ とっとと来やがれ
「続・ボーする日」
眠ったように死んでいるのか
死んだように眠っているのか
ままあること げに空おそろしき
まっすぐ転落する魂に
投げた花は届くのか
私の声のスピードは足りるのか
昏酔然 昏酔然
「昏酔然」
闘病生活が過酷だったせいか、歌詞は幾分、内省的に。発声は幾分、柔和に。なったか。いや、皮相な感想だ。そんなのではない。取り消そう。友川カズキの再生が私達に伝えるもの。ピュアである事、激越である事の‘聖’こそを提示するリーダーであろう。表現者が私的な根拠に独り立ち、その外部への影響を放置する時、打算なき本当の音楽的繋がりは生まれる筈だ。それはメッセージでも何でもなく、空中に放たれた表現物の掴み合いなのだ。誰もがそれをキャッチできる。共感する内的資質が少しでもあれば。友川カズキの歌に‘身に覚え’がある。そんな想いを持つ者、点在する同志が散らばって、一つになる。そして今度は、その各々が発信を開始しなければなるまい。
2008.11.27