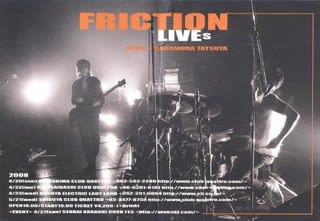このアルバムにある反米的とも言える体制批判の精神は元々、彼女にあったものなのか。多分、そうだろう。‘反米的’という言い方は語弊があるので、エリカ・バドゥの持つ様々な問題意識が現実に対峙する時、アメリカ社会の現状に対するアンチの心情を保持せざるを得ない、その姿勢と言い換えよう。『第4次世界大戦』と題された本作。外盤を買ったので歌詞の詳細は解らないが、インナースリーブにある数々のイラストと曲名、その英詞をざっと見ただけで、その激越ともとれる政治メッセージが窺える。9.11以降のアメリカの外交姿勢、ブッシュ政権への批判は今や、サブプライム問題やカトリーヌの被害地救済の怠慢に対する批判と相まって、アメリカでの表現者が広く共有する明確なタームになっている気がするが、エリカ・バドゥもまた、そんな戦列に加わったのだろうか。
ただ、私がより強くイメージするのはエリカ・バドゥのアフリカ志向である。正確にはそれは‘回帰’であろうが。本作『New Amerykah, Pt. 1: 4th World War』にある‘オールアメリカンブラックミュージック’たる、そのぎっしり詰まったブラックミュージックの幕の内弁当状態がすごい。彼女はまずアフロアメリカンの文化総体に対する帰属意識が濃厚にあり、従って、その先祖である母なる大地、アフリカへの何らかのアプローチが将来的に必然性を伴って具体化するであろう事を直感させる音楽を今、作り上げていると思われる。
Pファンクのパロディなのかと勘違いしそうな一曲目「amerykahn promise」はロイエアーズのプロデュース。猛烈に疾走するファンク。カッコいい。しかし2曲目以降はマッドリブによるアブストラクトヒップホップやら、従来のネオソウル、はたまたダンスポップや前衛色濃厚なナンバー、モストブラックな濃い口ソングと、その多様性が際立つ作品となっている。聴き通しての衝撃度、ファーストインパクト強し。確かに。
もはやエリカ・バドゥに真正面な‘ソウル’は求めるべくもない。歌唱法や様式、音響に対しても探求的であろうとする意欲が証明された。本作に見られる説得力はメッセージの先鋭化を際立たせる為の必然的なトラックメイキングの精緻さの追求だろう。その音の感触はブラックラディカリズム思想を単にスローガンとぜず、音楽構造上に於いても深化させたフリージャズのシカコ前衛派等を想起させるに充分な重みを感じる。つまり言葉の重みに充分、拮抗しうるサウンド構築が実現している。他方、それがより広汎なコマーシャリズムの獲得やソングライティングの自閉的失速を回避する為の戦略に基づくエリカ・バドゥの作為であるとも感じる。しかし何れにしてもそれら全てが‘創造’であろう。
先行シングル「honey」のプロモに於いてエリカ・バドゥはブラックミュージックの先達への愛を表明した。レコード店での色んなアルバムジャケットに自身が登場するアイデアは痛快だ。チョイスされたのはダイアナロス、ファンカデリック、グレイスジョーンズ、デラソウル、エリックB&ラキム、オハイオプレイヤーズ、E.W&F … あとは何だったかな。
おそらくエリカ・バドゥはブラックミュージックマニアだろう。その継続する音楽マニア志向が様々な問題意識の喚起につながり、概念的なものへの関心へと伸張する時、必然とも言えるアフリカ精神という表現拠点への帰結を強く予感させる。
2008.5.27