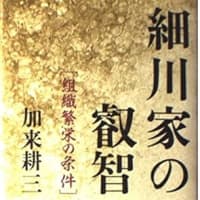今日は大晦日。今年出会った本の中でも本シリーズ「日本の古典を読む」は秀逸。以前チャレンジして二度も挫折していた源氏物語を始め、高校時代の古典の時間にわずかに触れただけであった「枕草子」「平家物語」など、書全巻を通して読むことは高いハードルであり、それでももう少し日本人なら知っておきたいという、微妙な距離感にあった日本の古典に親しむ機会になった事に感謝。
本書は、そうした日本の古典の中でも、再三登場する和歌の集大成として日本の古典文学の中でも屹立する2つの山を紹介する。905年に成立した古今和歌集と1205年頃に成立した新古今和歌集は、勅撰和歌集の二大和歌集とも言える存在。古今和歌集の背景にあるのは、摂関政治で娘を入内させることで権力を握り続けた藤原氏の存在である。
入内させた娘たちをより輝かせるために、その時代のスーパーエリートである女性文化人たちを娘のお世話と教育係としてチーム編成し、各勢力が競い合うという環境の中で、そうしたエリートサークルの仲間に娘を参加させ、あわよくば自分自身もそうしたサークルの一員に入りたいと望む、殿上人希望組の両親は、娘たちに和歌や漢詩の教育を施した。「后がね」とはそうした后になるための高級公卿たちの娘であり、后候補者。后がね教育サークルに入り込むために自分の娘を教育するという五位程度の貴族たちは、娘が紫式部や清少納言になれることを望んだ。五位になれば地方の国司に任命される可能性があり、国司になって中央への租税さえ収めれば、才覚次第で受益可能な経済的利益は大きかった。平安時代の女性による和歌やエッセイ、日記など、女性も学ぶかなの登場、摂関政治から院政にわたる平安時代に巨大な山脈のように積み重なるように存在し今でも残るのはこうした時代背景がある。
醍醐天皇勅撰和歌集である古今集は、当時ほころびが見え始めた律令制度を建て直すため歴史書の編纂や法令の制定などが行われた時代。しかし対象となったのは漢詩文ではなく、宮廷文学として成熟し始めていた和歌だった。古今集以降後撰集、拾遺集、後拾遺集と和歌集が継続して編纂されるようになった。平安後期には金葉集、詞華集、千載集そして後鳥羽上皇により新古今和歌集が編纂された。新古今和歌集には古くは万葉集の時代から、平安期の名高い歌も取り上げられ、撰者である藤原定家たちによる意匠を凝らした和歌も掲載された。古今集から新古今和歌集までの8つの和歌集を八代和歌集と呼ばれる。政権の主体が武家に移っても和歌集は編纂されるが、応仁の乱を最期に途絶える。
古今集は1100首をまずは四季の順に並べ、続いてお祝い、離別、羇旅、そして恋の歌、哀傷、雑歌の順に並ぶ全20巻。新古今和歌集でもこれに倣う。恋の歌では、恋が始まるときめきから、時の推移にそって心が移り変わるさまを描き、恋の成就、失恋、そして訪れる別れ、失った恋への哀惜などと続く。新古今和歌集では編者の藤原定家と編纂を命じた後鳥羽院が、和歌の選出と順序立てなどに心血を注いだ様子がうかがえる。後鳥羽院の時代は鎌倉に武家政権が登場して、都と東国の力のバランスが大きく変わり始めたとき。単なる遊興の延長ではなく、民の心を和らげ、君臣が相和して理想の治世の素晴らしさを祝いたいという理想が現れる。頼朝に続く頼家、実朝には、こうした理想を共有させたい、なんとかして権力の維持を図りたいという思いもあったに違いない。
後鳥羽院は、承久の乱で隠岐に流されたあとも絶海の孤島で新古今集の精選に取り組み400首ほどに削除の符号を付して完成させたという。表現の華やかさに傾きすぎた歌集と評されることもある新古今だが、藤原俊成が目指した深い叙情性と、その方法論を継承し発展、新規な言葉や趣向の面白さだけではなく、和歌本来の叙情性を回復させることこそが和歌の再生につながるとした定家の親子によるところが特徴となっている。