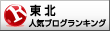今回は「十牛図」にみる禅の心を学習します。
「十牛図」とは、禅の修業の段階と悟りの境地を10枚の絵によってあらわしたものである。牛を探しだし、飼いならし、家に連れて帰るという物語だが、この牛はただの牛ではない。人間が本来もっている「仏心」の象徴だ。
一、尋牛(じんぎゅう)
村人が牛を探し歩いている。この牛は、欲望や執着にまどわされない「本来の自己(仏心)」の象徴である。人間は自分のなかの仏心にきづかず探しまわる。この図は、悟りを求め、煩悩の世界から第一歩を踏みだした姿。
二、見跡(けんせき)
探しまわった村人は、やっと牛の足跡を見つける。まだ「本来の自己」を見つけたわけではないが、経典を読んだり師の話を聞いて、知識として、自分のなかにあることをなんとなく理解する。図は、ようやく手掛かりを得た姿。
三、見牛(けんぎゅう)
村人はついに牛の姿の一部を見る。しかし、まだ全体は見えない。修行により、はじめて「本来の自己」の姿を見て、わずかに悟りが開けた段階である。村人は牛のほうに歩みを進める。図は、全体像がぼんやり見えた自分の姿。
四、得牛(とくぎゅう)
村人は牛を捕らえ、手綱をかけるが、牛は逃げようとし、逃すまいと手綱を引く村人。まだはっきり正体がわからない「本来の自己」とそれを求める自己。努力して修行を続けなければすぐに見失ってしまう緊張感をあらわした図。
五、牧牛(ぼくぎゅう)
やっとつないだ牛は、村人に手綱を引かれて一緒に歩く。しかし、まだ手綱は離せない。厳しい修行の結果「本来の自己」を得たつもりでも、常に迷いや欲望が襲う。悟りを開いたのちの悟後の修行の大切さを説いてる図。
六、騎牛帰家(きぎゅうきか)
もはや牛は、村人を背に乗せても逃げようとしない。村人の心は安らかに笛を楽しみながら牛に乗って家に帰る。ついに「本来の自己」と求める自分とが同化した。求めようと努力しなくてもよい自由な境地をあらわした図。
七、忘牛存人(ぼうぎゅうそんじん)
牛の姿はない。村人だけが家にいて、牛を得たことも忘れ、ゆったりとくつろいでいる。悟りを得たと意識すれば、それは迷いだ。その意識すら捨て、「本来の自己」になりきっている図。
八、人牛倶忘(じんぎゅうぐぼう)
牛の姿ばかりか村人の姿も消え、ただ空白の円がある。これを「空一円相」という。完全に自我を捨て、広大無辺な宇宙と一体になったかのような「無我の境地」いま、ここのいる自己は「空」。その境地をめざせという図。
九、返本還源(へんぽんかんげん)
美しい自然が広がっている。村人の修行や悟りとは無関係に、自然は最初からそこにあった。「無我の境地」にいたった村人は、時間も空間も超越し、ありのままの自然と一体になっている。万物が本来に返り、源に還るという図。
十、入鄽垂手(にってんすいしゅ)
村人が町へ出て、他人と接している。「鄽」は町、「垂手」はだらりと手をさげた姿をいい、お釈迦さまが何の印相も示さないのに、人々が自然にその教えに従うことを意味する。悟りを開いても禅の世界に閉じこもってはいけないという図。
今回ちょっと図を載せられないのですが、「十牛図」で検索しますと出てきますのでぜひ、検索してみてください。
「十牛図」とは、禅の修業の段階と悟りの境地を10枚の絵によってあらわしたものである。牛を探しだし、飼いならし、家に連れて帰るという物語だが、この牛はただの牛ではない。人間が本来もっている「仏心」の象徴だ。
一、尋牛(じんぎゅう)
村人が牛を探し歩いている。この牛は、欲望や執着にまどわされない「本来の自己(仏心)」の象徴である。人間は自分のなかの仏心にきづかず探しまわる。この図は、悟りを求め、煩悩の世界から第一歩を踏みだした姿。
二、見跡(けんせき)
探しまわった村人は、やっと牛の足跡を見つける。まだ「本来の自己」を見つけたわけではないが、経典を読んだり師の話を聞いて、知識として、自分のなかにあることをなんとなく理解する。図は、ようやく手掛かりを得た姿。
三、見牛(けんぎゅう)
村人はついに牛の姿の一部を見る。しかし、まだ全体は見えない。修行により、はじめて「本来の自己」の姿を見て、わずかに悟りが開けた段階である。村人は牛のほうに歩みを進める。図は、全体像がぼんやり見えた自分の姿。
四、得牛(とくぎゅう)
村人は牛を捕らえ、手綱をかけるが、牛は逃げようとし、逃すまいと手綱を引く村人。まだはっきり正体がわからない「本来の自己」とそれを求める自己。努力して修行を続けなければすぐに見失ってしまう緊張感をあらわした図。
五、牧牛(ぼくぎゅう)
やっとつないだ牛は、村人に手綱を引かれて一緒に歩く。しかし、まだ手綱は離せない。厳しい修行の結果「本来の自己」を得たつもりでも、常に迷いや欲望が襲う。悟りを開いたのちの悟後の修行の大切さを説いてる図。
六、騎牛帰家(きぎゅうきか)
もはや牛は、村人を背に乗せても逃げようとしない。村人の心は安らかに笛を楽しみながら牛に乗って家に帰る。ついに「本来の自己」と求める自分とが同化した。求めようと努力しなくてもよい自由な境地をあらわした図。
七、忘牛存人(ぼうぎゅうそんじん)
牛の姿はない。村人だけが家にいて、牛を得たことも忘れ、ゆったりとくつろいでいる。悟りを得たと意識すれば、それは迷いだ。その意識すら捨て、「本来の自己」になりきっている図。
八、人牛倶忘(じんぎゅうぐぼう)
牛の姿ばかりか村人の姿も消え、ただ空白の円がある。これを「空一円相」という。完全に自我を捨て、広大無辺な宇宙と一体になったかのような「無我の境地」いま、ここのいる自己は「空」。その境地をめざせという図。
九、返本還源(へんぽんかんげん)
美しい自然が広がっている。村人の修行や悟りとは無関係に、自然は最初からそこにあった。「無我の境地」にいたった村人は、時間も空間も超越し、ありのままの自然と一体になっている。万物が本来に返り、源に還るという図。
十、入鄽垂手(にってんすいしゅ)
村人が町へ出て、他人と接している。「鄽」は町、「垂手」はだらりと手をさげた姿をいい、お釈迦さまが何の印相も示さないのに、人々が自然にその教えに従うことを意味する。悟りを開いても禅の世界に閉じこもってはいけないという図。
今回ちょっと図を載せられないのですが、「十牛図」で検索しますと出てきますのでぜひ、検索してみてください。