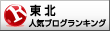ちょっとお釈迦さまの事がしりたくて色々読み漁っている私ですが、数あるエピソードの中でもアングリマーラのお話はお釈迦様の素晴らしさが判るお話でもあるので、ちょっとここでも紹介したいと思います。
アングリマーラはコーサラ国のバラモン大臣の子で、学生時代から群を抜いて優秀な青年でした。
バラモンの老いた師に付いて、長年学んでいたのですが、師の留守中に、師の若い妻に誘惑されたので、手厳しく拒絶して逃げ帰ります。
屈辱を受けたバラモンの妻は自分で衣類を引き裂き、爪で身体に傷をつけ、夫にアングリマーラに犯されかかってこんな目に遭った。それでも辛うじて自分は貞操を守ったと泣いて訴えました。
老いたバラモンは嫉妬に狂い、アングリマーラに復讐しようと考えを廻らせ、ある日、さり気なくアングリマーラを呼び出し、こう言うのです。
「もはやお前には、すべての学問も修行の方法も教え尽くした。最後に果たさなければならない修行が一つ残っている。それは百人の人間を殺して、指を一本ずつ証拠に切り取り、百の指をつないで首飾りをつくれば、お前の行は完成するのだ」
そう言って、その為の刀剣を渡しました。
アングリマーラは驚き怖れたものの、信じきっていた師の命令だからと、それから毎晩町へ出て、辻斬りをはじめるのです。
町の人々は突如現れた殺人鬼の凶行に怯え、昼間も人出がなくなり、その為アングリマーラの殺人は、次第に難しくなっていきました。
ようやく99人を殺し、あと一人で命じられた行が完成するというのに、百人目が通らないのでアングリマーラは焦っていました。
それを聞いたお釈迦さまは、弟子たちが必死に止めるのも聞かず、一人で灯も消えはてた町へ出かけます。
勿論、その背後から弟子が見えかくれに尾いていきました。
お釈迦さまが一人静かに歩いているのを見つけた覆面の殺人鬼が、物陰から躍り出て叫びます。
「止まれ」
お釈迦さまは静かな威厳のある声で言われました。
「私は止まっている。殺人鬼よ、お前こそ止まれ」
その声と態度に、アングリマーラはひるみましたが、虚勢を張って問いかえしました。
「お前は今、歩いているのに自分は止まっているといい、私は止まっているのに、動いているというのか」
お釈迦さまはすかさず。
「私は一切の生類に害心を持っていない。だから心は静止している。お前は生類に対して不殺生の自制心を失っているから、心が乱れ動揺しているのだ。動いているのはお前だ。殺人鬼よ、正気に返れ」
と烈しい声で叱咤された。その威厳と正しい叱責に打たれ、その場で正気を取り戻したアングリマーラは刀を投げ捨て、お釈迦さまの前にひれ伏しました。
お釈迦さまはアングリマーラをその場から祇園精舎に連れ帰って、彼の望む通り出家させてしまいます。
さすがに精舎の中でもこの事件には騒然となりました。
お釈迦さまは周りの声を無視して、アングリマーラを他の弟子と同様に扱いました。
托鉢に出ては、町の人々に包囲され、罵声を浴びせられ、石や棒で打ち据えられ、血みどろになって帰ってくるアングリマーラに
「ただ耐えよ」
と言われるお釈迦さまの言葉を命綱に、アングリマーラは毎日を耐えに耐えます。
国王も軍隊を引きつれアングリマーラの召し捕りに押し寄せますが、お釈迦さまは、一度自分の弟子になった者は、国王の命と言えど、引き渡す事は出来ないと拒み通しました。
国王もお釈迦さまに帰依してましたので、逆らう事もできずそのまま引き上げていきました。
「すべては流転する。同じ状態でつづくものはこの世にはない。それを無常という。人も、時も、事件も、噂も・・・」
お釈迦さまの口癖通り、あれほど非難と嫌悪の的になったアングリマーラを、教団ではもう誰もみな殺人鬼だったことなど忘れきったようになっていく・・・。
また、当時を知らない若い修行僧たちが、旧い僧の何倍か多く増えていきました。
時が流れ、お釈迦さまも亡くなる日が近づいてきました・・・。
お釈迦さまに長年侍者としてつかえているアーナンダが、ある日、アングリマーラにたずねます・・・。
「お母様はお元気か?」
アングリマーラは答えました・・・。
「いや、あの事件の後、私の様な極悪の子を産んだという理由で、父に追われ、実家に戻る途中の森の中で縊れて死んだと聞いている。父もその後、大臣の職を辞し、行方をくらましてしまった。自分の無智の引き起こした罪の深さは、年月を経ても少しも薄らぎはしない。これは今まで誰にも話したことはないが、あの夜、世尊の歩いて来られる前に、もう一人の人間が現れたのだ。獲物に餓えていた狂人の私はたちまちその者を捕らえた。剣を胸に刺しつけた時、
「早く殺しなさい」
と女の声がした。母だった。母が絶叫した。
「百人目に母を殺して、お前も死んでおくれ」
その時、世尊が向こうから歩いて来られた。母に当身をくらわせ、失神させ、私は世尊を襲おうとした。世尊に救われた一部始終を、気絶していた母は知らない。母が自殺したのは、私の殺した人々へのお詫びだと思う。
私の殺した九十九人の人々の家族の悲歎と不幸を私は忘れたことがない。アーナンダ、この世で一番悪い人間の罪は無智だ。戒律の一番重いものは、不殺生だ。殺してはならぬ、殺させてはならぬ、と世尊が説かれる度、自分ひとりに向けてのお説教だと、いつも全身が硬直してしまう。私にはこの世に生きて、自分の拭いきれない罪に後悔し続ける生が、地獄のどんな責苦とやらより辛い。だからこそ、自分には永遠に死ぬ事が許されないような気さえしている」
・・・ここまでのくだりを読んで絶句してしまったのは私だけでしょうか・・・。
どの様に感じるかは個人の自由です。
ただ、私は何度も何度もこの話を読み返してしまうのです・・・。
アングリマーラはコーサラ国のバラモン大臣の子で、学生時代から群を抜いて優秀な青年でした。
バラモンの老いた師に付いて、長年学んでいたのですが、師の留守中に、師の若い妻に誘惑されたので、手厳しく拒絶して逃げ帰ります。
屈辱を受けたバラモンの妻は自分で衣類を引き裂き、爪で身体に傷をつけ、夫にアングリマーラに犯されかかってこんな目に遭った。それでも辛うじて自分は貞操を守ったと泣いて訴えました。
老いたバラモンは嫉妬に狂い、アングリマーラに復讐しようと考えを廻らせ、ある日、さり気なくアングリマーラを呼び出し、こう言うのです。
「もはやお前には、すべての学問も修行の方法も教え尽くした。最後に果たさなければならない修行が一つ残っている。それは百人の人間を殺して、指を一本ずつ証拠に切り取り、百の指をつないで首飾りをつくれば、お前の行は完成するのだ」
そう言って、その為の刀剣を渡しました。
アングリマーラは驚き怖れたものの、信じきっていた師の命令だからと、それから毎晩町へ出て、辻斬りをはじめるのです。
町の人々は突如現れた殺人鬼の凶行に怯え、昼間も人出がなくなり、その為アングリマーラの殺人は、次第に難しくなっていきました。
ようやく99人を殺し、あと一人で命じられた行が完成するというのに、百人目が通らないのでアングリマーラは焦っていました。
それを聞いたお釈迦さまは、弟子たちが必死に止めるのも聞かず、一人で灯も消えはてた町へ出かけます。
勿論、その背後から弟子が見えかくれに尾いていきました。
お釈迦さまが一人静かに歩いているのを見つけた覆面の殺人鬼が、物陰から躍り出て叫びます。
「止まれ」
お釈迦さまは静かな威厳のある声で言われました。
「私は止まっている。殺人鬼よ、お前こそ止まれ」
その声と態度に、アングリマーラはひるみましたが、虚勢を張って問いかえしました。
「お前は今、歩いているのに自分は止まっているといい、私は止まっているのに、動いているというのか」
お釈迦さまはすかさず。
「私は一切の生類に害心を持っていない。だから心は静止している。お前は生類に対して不殺生の自制心を失っているから、心が乱れ動揺しているのだ。動いているのはお前だ。殺人鬼よ、正気に返れ」
と烈しい声で叱咤された。その威厳と正しい叱責に打たれ、その場で正気を取り戻したアングリマーラは刀を投げ捨て、お釈迦さまの前にひれ伏しました。
お釈迦さまはアングリマーラをその場から祇園精舎に連れ帰って、彼の望む通り出家させてしまいます。
さすがに精舎の中でもこの事件には騒然となりました。
お釈迦さまは周りの声を無視して、アングリマーラを他の弟子と同様に扱いました。
托鉢に出ては、町の人々に包囲され、罵声を浴びせられ、石や棒で打ち据えられ、血みどろになって帰ってくるアングリマーラに
「ただ耐えよ」
と言われるお釈迦さまの言葉を命綱に、アングリマーラは毎日を耐えに耐えます。
国王も軍隊を引きつれアングリマーラの召し捕りに押し寄せますが、お釈迦さまは、一度自分の弟子になった者は、国王の命と言えど、引き渡す事は出来ないと拒み通しました。
国王もお釈迦さまに帰依してましたので、逆らう事もできずそのまま引き上げていきました。
「すべては流転する。同じ状態でつづくものはこの世にはない。それを無常という。人も、時も、事件も、噂も・・・」
お釈迦さまの口癖通り、あれほど非難と嫌悪の的になったアングリマーラを、教団ではもう誰もみな殺人鬼だったことなど忘れきったようになっていく・・・。
また、当時を知らない若い修行僧たちが、旧い僧の何倍か多く増えていきました。
時が流れ、お釈迦さまも亡くなる日が近づいてきました・・・。
お釈迦さまに長年侍者としてつかえているアーナンダが、ある日、アングリマーラにたずねます・・・。
「お母様はお元気か?」
アングリマーラは答えました・・・。
「いや、あの事件の後、私の様な極悪の子を産んだという理由で、父に追われ、実家に戻る途中の森の中で縊れて死んだと聞いている。父もその後、大臣の職を辞し、行方をくらましてしまった。自分の無智の引き起こした罪の深さは、年月を経ても少しも薄らぎはしない。これは今まで誰にも話したことはないが、あの夜、世尊の歩いて来られる前に、もう一人の人間が現れたのだ。獲物に餓えていた狂人の私はたちまちその者を捕らえた。剣を胸に刺しつけた時、
「早く殺しなさい」
と女の声がした。母だった。母が絶叫した。
「百人目に母を殺して、お前も死んでおくれ」
その時、世尊が向こうから歩いて来られた。母に当身をくらわせ、失神させ、私は世尊を襲おうとした。世尊に救われた一部始終を、気絶していた母は知らない。母が自殺したのは、私の殺した人々へのお詫びだと思う。
私の殺した九十九人の人々の家族の悲歎と不幸を私は忘れたことがない。アーナンダ、この世で一番悪い人間の罪は無智だ。戒律の一番重いものは、不殺生だ。殺してはならぬ、殺させてはならぬ、と世尊が説かれる度、自分ひとりに向けてのお説教だと、いつも全身が硬直してしまう。私にはこの世に生きて、自分の拭いきれない罪に後悔し続ける生が、地獄のどんな責苦とやらより辛い。だからこそ、自分には永遠に死ぬ事が許されないような気さえしている」
・・・ここまでのくだりを読んで絶句してしまったのは私だけでしょうか・・・。
どの様に感じるかは個人の自由です。
ただ、私は何度も何度もこの話を読み返してしまうのです・・・。