四角シャボンライブを観に行きました。
代官山を歩きます。その前に駅前のハンバーガーショップ「SASA」でハンバーガーを食べずにビールを飲みます。

気軽に入られる割とお気に入りの場所です。
そして歩きます。ライブハウスのloopは代官山駅から若干歩きます。歩いているとひまわりフェスティバルがやっています。
都会の喧騒、代官山のお洒落さの中、心癒してくれます。ひまわり、黄色で好きなのです。

咲いたらさぞかし綺麗なことでしょう。そしてここでビアガーデンをやっています。飲みたい。
そしてライブハウス前。前回lab~再開発~で生ライブ、ベースを引いてくれた加藤さんが本番前にも関わらず粋なポーズをしてくれました。

そして本番。
いやーやはりライブはラブハウスに限ります。音の勢い、バンドの勢い、ボーカル樋口義也の勢いが全く違います。
そしてライブハウスに来ていた、前回メンバーからも「すげー」の声が聞こえます。「どうだ、凄いだろう。これを舞台に上げたいんだよ。」と鼻高々です。公演に使用した「river」「temp」や前々回の「神様ごっこ」やら、良い曲の目白押しです。今後新アルバムも出るとか。必聴です。
そんなライブハウスに来たメンバー

ブレブレで全然分からない。
楽器の技術性とボーカルの熱量、そして音波というグルーブ感がまるで料理のようにお互いを殺さず、高めあい、一つとして損なわれるところなく出てくるところに、ライブの良さがあるなと何となく思います。音楽のリズムは完全なる「技術」による正確に刻まれ、例え敢えて外したリズムになろうとも、メロディがそれに合わせることで別の「技術」的リズムが生まれると思います。
どれくらいの時間で自分たちで作った歌をマスターし、どれくらいの時間で毎回のイベント本番前で合わせていくのか、凄く興味深いです。今度聞いてみようと思います。
30分という時間が本当に短く感じ、料金に見合う内容であると思います。
昨日のオケにしても今回のバンドにしても、指揮者、樋口義也の「熱量」とオケメンバー、バンドメンバーの多くの「技術」が交じり合うところに良さを感じます。これがどちらか一方だけでも駄目であり、またバランスもここから損なうとよろしくない。
さて、これを芝居に当てはめると、なかなかこのような状況はお目にかかれません。大抵は「熱量」オンリーか、劇作演出の「技術」がメインにきます。
わたしが「面白い」と思うこのバランスを如何にお客様に伝えるか、それを考えact orchを行っておりますが、こう改めて文字にすると果たしてどうだったか、考えるところがあります。せっかく「若い→熱量」を使えるのだから、更なる「技術」を注いでも良かったのではと思うところもあります。
そして幸運にも10月に楽器と芝居のコラボレート企画に携わります。ここでこそ、音楽のプロフェッショナル性を考える絶好のチャンスです。4~5回程で本番を迎えるプロの音楽家たちと勝負です。
代官山を歩きます。その前に駅前のハンバーガーショップ「SASA」でハンバーガーを食べずにビールを飲みます。

気軽に入られる割とお気に入りの場所です。
そして歩きます。ライブハウスのloopは代官山駅から若干歩きます。歩いているとひまわりフェスティバルがやっています。
都会の喧騒、代官山のお洒落さの中、心癒してくれます。ひまわり、黄色で好きなのです。

咲いたらさぞかし綺麗なことでしょう。そしてここでビアガーデンをやっています。飲みたい。
そしてライブハウス前。前回lab~再開発~で生ライブ、ベースを引いてくれた加藤さんが本番前にも関わらず粋なポーズをしてくれました。

そして本番。
いやーやはりライブはラブハウスに限ります。音の勢い、バンドの勢い、ボーカル樋口義也の勢いが全く違います。
そしてライブハウスに来ていた、前回メンバーからも「すげー」の声が聞こえます。「どうだ、凄いだろう。これを舞台に上げたいんだよ。」と鼻高々です。公演に使用した「river」「temp」や前々回の「神様ごっこ」やら、良い曲の目白押しです。今後新アルバムも出るとか。必聴です。
そんなライブハウスに来たメンバー

ブレブレで全然分からない。
楽器の技術性とボーカルの熱量、そして音波というグルーブ感がまるで料理のようにお互いを殺さず、高めあい、一つとして損なわれるところなく出てくるところに、ライブの良さがあるなと何となく思います。音楽のリズムは完全なる「技術」による正確に刻まれ、例え敢えて外したリズムになろうとも、メロディがそれに合わせることで別の「技術」的リズムが生まれると思います。
どれくらいの時間で自分たちで作った歌をマスターし、どれくらいの時間で毎回のイベント本番前で合わせていくのか、凄く興味深いです。今度聞いてみようと思います。
30分という時間が本当に短く感じ、料金に見合う内容であると思います。
昨日のオケにしても今回のバンドにしても、指揮者、樋口義也の「熱量」とオケメンバー、バンドメンバーの多くの「技術」が交じり合うところに良さを感じます。これがどちらか一方だけでも駄目であり、またバランスもここから損なうとよろしくない。
さて、これを芝居に当てはめると、なかなかこのような状況はお目にかかれません。大抵は「熱量」オンリーか、劇作演出の「技術」がメインにきます。
わたしが「面白い」と思うこのバランスを如何にお客様に伝えるか、それを考えact orchを行っておりますが、こう改めて文字にすると果たしてどうだったか、考えるところがあります。せっかく「若い→熱量」を使えるのだから、更なる「技術」を注いでも良かったのではと思うところもあります。
そして幸運にも10月に楽器と芝居のコラボレート企画に携わります。ここでこそ、音楽のプロフェッショナル性を考える絶好のチャンスです。4~5回程で本番を迎えるプロの音楽家たちと勝負です。














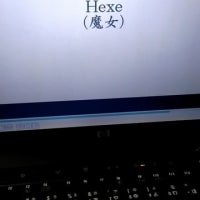





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます