
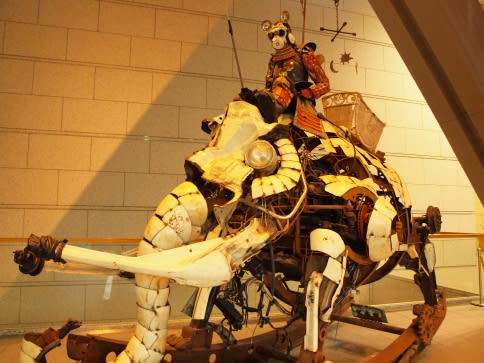
都立現代美術館
アートと音楽-新たな共感覚をもとめて
北千住の我が家からロードバイクで40分。人に勧め、また勧められた企画展。
下記写真は公式サイトから。




現代美術、体験系が好きなわたしにとっては非常に楽しめた。つまるところは五感で音を感じてみようという企画で、そこから日常に溢れる音…芸術に気づこうというもの。現代美術は「気付き」の芸術なのであろう。作り手の「気付き」によって受け取り手が新たに気付く。それは同じものでも良いし、受け取り手の自由なのである。
オノセイゲン+坂本龍一+高谷史郎
《silence spins》
音を吸収する素材で作られた茶室。暗闇のその中では、音が異なった感触で己に返ってくる。
これ、中で音を出すことで音を認識出来る構造である故、中で音を出さなければならない。つまり、二人で行くと会話が出来る故音を出すのは簡単なのであるが一人でいくとそうはいかない。「アー」などの単音は出せるが、会話レベル、更には高音、低音をだそうとすると容易なことではない。そんなことをしていたらば周りの人が奇妙な目でわたしを見るであろう。
と、わたしの後ろで並んでいた年配女性二人組み。終始話を続け、その会話の煩さから軽くわたしをいらつかせていたのだが、彼女たちの声こそ、この空間において必要なものであり、またわたしにとっても良い実験となる。
わたしちょっと待って、彼女たちが入ってくるのを待つ。
入ってきた。
無言。
なんで緊張するの?さっきみたいに喋ってよ。
マノン・デ・ブール
《二度の4分33秒》
映像作品。ジョンケージ《4分33秒》を二度に渡って流す。一度目は観客を二度目は風景を写す。そもそも《4分33秒》自体が無音である故、見手は映される観客や風景から漏れる音を、映像込みで聴くこととなる。
この作品、ようは《4分33秒》の正しい「感じ方」と受け取れた。わたしが見た時は周りのお客さんの笑い声や寝息が聴こえた。受け取り手の感覚によっては単なる無音、またはわけが分からない映像であるのだ。
カールステン・ニコライ
《ミルク》シリーズ
ミルクに特定の周波数をあて、その振動からミルク表面に浮かぶ波を映した作品。音が「無」ではなく「有」であることを表す。
先日行った萌ちゃんさんのダンスライブでも、ウーハーの利いた爆音を受け、その振動を体全体で感じるという経験をした。そんなんで青山テルマ聞いたり、TRF chiharu振り付けのダンスみたら感動しちゃうよね。
バルトロメウス・ラウベック
《Years》
木の年輪をレコードにみたてターンテーブルで回す。対応する音がピアノ音で流れるというものである。一見すると出鱈目な音なのだが、これが木の年輪…生命が生き続けてきた詩であると考えると不思議と感動する。
フロリアン・ヘッカー
《3チャンネル・クロニクス》
別方向を向いた3つのスピーカーから別の電子音が流れる。立ち位置によって全く異なる印象を受ける。
「音」も「アート」も好きなので、色々感銘を受けた。最近は押し付けられる「物語」よりも受け取り手が物語を考える「抽象」の方が好みなのだ。














