モノオペラ「廻」(初演)
-trimurti meditation-(ソプラノと笙による)
Naoyuki Manabe「Mono Opera」-trimurti meditation- for Sho and Soprano
11月分を…というか今まで書けなかった分を一気にアップしまして漸く「廻」を振り返ります。
笙の真鍋さんとはlab01でお知り合いになりました。そもそもの作品の発注が「世界観芝居」でしたので、精神世界に「行く」という大学時代にやり尽くした世界観芝居をもう一度呼び起こし、それ以降に構築してきた作品作りのエッセンスを混ぜ合わせた、わたしの新旧合算した作品となりました。
ある人間が紐の前で目を瞑ります。
その刹那神が出現します。創造、維持、終局の神です。
神達は時空を越えてある人間の世界を変容させていきます。壮大な物語です。
変わりゆく世界で行為の象徴である業が語りかけます。その声はある人間には届きません。
ある人間は疑問を持ちます。神は本当に神なのか?と。
そして気付きます。業によって気付かされます。
その瞬間、一瞬の瞑想が終わります。ある人間は世界と繋がったのです。
そして紐にくくられます。
端的に書くとこのような物語です。台本で言うと10枚くらいになる作品を書きました。
結果としてそれが45分の音楽になったのですが、ストーリーを追っていくのは見慣れていない方には大変だったかもしれません。パフォーマーを導入し、見た目に分かりやすかったかも知れませんが、それにしても「理解する」ではなく「なんとなく印象に残る」レベルで終わってしまったかもしれません。
今回の自分に課した課題が「演劇を音楽と同様に『印象』として残るように」だったのである意味では成功だったかもしれません。が、パフォーマーの動きを結果「分かりやすい」ものにしてしまったのは、時間の無さ、もとい演出としての自分のふがいなさです。反省です。

楽屋の皆様。
今回は本当に役者に助けられました。先方との兼ね合いもあり出演者を限定しましたが、本当に今回のメンバーには助けられました。ありがとうございます。

稽古中はとにかく「調整」に尽きました。今現在出来る最大限の調整をしたつもりです。
当日は客席から観ず、照明室で照明さんと照明をやりながら観るという闘うスタッフとして参加しました。わたしも役者と共に闘う覚悟でした。
本番後、舞台上で挨拶する機会が持てました。これまで手掛けた作品の中で1,2を争う大変な内容でしたが、舞台上で挨拶した瞬間、その苦労が報われた気がしました。東京オペラシティの照明は本当に温かく素晴らしい。
今回の最大のテーマは「音楽の質、効率を演劇に当て嵌める。同質に捉える」というものでした。「そもそも違うじゃん」という答えはそりゃそうでして、そんな簡単に割り切らず、逆にどうなったら同質になるか、それには何が必要か…それを考える機会として、参加した役者の子達にも一緒に考えて欲しいと思いました。
結果としてどうだったのだろう。今度聞いてみます。
-trimurti meditation-(ソプラノと笙による)
Naoyuki Manabe「Mono Opera」-trimurti meditation- for Sho and Soprano
11月分を…というか今まで書けなかった分を一気にアップしまして漸く「廻」を振り返ります。
笙の真鍋さんとはlab01でお知り合いになりました。そもそもの作品の発注が「世界観芝居」でしたので、精神世界に「行く」という大学時代にやり尽くした世界観芝居をもう一度呼び起こし、それ以降に構築してきた作品作りのエッセンスを混ぜ合わせた、わたしの新旧合算した作品となりました。
ある人間が紐の前で目を瞑ります。
その刹那神が出現します。創造、維持、終局の神です。
神達は時空を越えてある人間の世界を変容させていきます。壮大な物語です。
変わりゆく世界で行為の象徴である業が語りかけます。その声はある人間には届きません。
ある人間は疑問を持ちます。神は本当に神なのか?と。
そして気付きます。業によって気付かされます。
その瞬間、一瞬の瞑想が終わります。ある人間は世界と繋がったのです。
そして紐にくくられます。
端的に書くとこのような物語です。台本で言うと10枚くらいになる作品を書きました。
結果としてそれが45分の音楽になったのですが、ストーリーを追っていくのは見慣れていない方には大変だったかもしれません。パフォーマーを導入し、見た目に分かりやすかったかも知れませんが、それにしても「理解する」ではなく「なんとなく印象に残る」レベルで終わってしまったかもしれません。
今回の自分に課した課題が「演劇を音楽と同様に『印象』として残るように」だったのである意味では成功だったかもしれません。が、パフォーマーの動きを結果「分かりやすい」ものにしてしまったのは、時間の無さ、もとい演出としての自分のふがいなさです。反省です。

楽屋の皆様。
今回は本当に役者に助けられました。先方との兼ね合いもあり出演者を限定しましたが、本当に今回のメンバーには助けられました。ありがとうございます。

稽古中はとにかく「調整」に尽きました。今現在出来る最大限の調整をしたつもりです。
当日は客席から観ず、照明室で照明さんと照明をやりながら観るという闘うスタッフとして参加しました。わたしも役者と共に闘う覚悟でした。
本番後、舞台上で挨拶する機会が持てました。これまで手掛けた作品の中で1,2を争う大変な内容でしたが、舞台上で挨拶した瞬間、その苦労が報われた気がしました。東京オペラシティの照明は本当に温かく素晴らしい。
今回の最大のテーマは「音楽の質、効率を演劇に当て嵌める。同質に捉える」というものでした。「そもそも違うじゃん」という答えはそりゃそうでして、そんな簡単に割り切らず、逆にどうなったら同質になるか、それには何が必要か…それを考える機会として、参加した役者の子達にも一緒に考えて欲しいと思いました。
結果としてどうだったのだろう。今度聞いてみます。














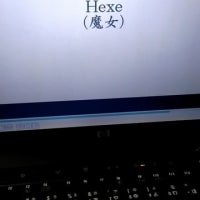





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます