ダイエットには運動がいいと言われてきた。しかし実際に運動してみたけれど、体重は全く減らなかったという経験はないだろうか? それもそのはず、運動は体重を減らすのには向いておらず、場合によっては体重の増加をもたらすことさえあるのだ。
これは米ニュース雑誌「TIME」によって紹介され、世界に衝撃を与えている。TIMEによると、確かに運動はカロリーを消費し、そしてカロリーの消費は体重の減少をもたらすのだが、運動にはある問題がある。それは私たちを空腹にしてしまうこと。
みなさんも経験があると思うが、人は運動後お腹が減り、いつもより食べ物を食べてしまう。また、運動したという達成感からも普段以上に食べてしまい、これが運動で消費したカロリーをあっという間に帳消しにする。場合によっては、運動で消費した以上のカロリーを食べ物から摂取してしまうことも。
これを示す例として、TIMEは科学雑誌「PLoS ONE」とティモシー・チャーチ博士が共同で行った実験を紹介している。
彼らは普段運動しない464人の肥満女性を対象に、次のような実験を行った。
1)464人を4つのグループに分ける。
2)グループAには専属トレーナーと共に一週間に72分、グループBには一週間に136分、グループCには一週間に194分運動してもらう。グループDは今までどおりの運動量を維持してもらう。
3)4グループとも食習慣は変えず、また一ヶ月ごとに健康診断アンケートに答えてもらう。
4)この生活を6ヶ月間続けてもらう。
6ヵ月後、平均してすべてのグループで体重が減っていたのだが、体重が減った量に関して、グループA、B、CとグループDにそれほど大差がなかったのだ。グループDの体重が減った理由としては、定期的な健康アンケートによって、被験者が自分が食べているものを意識し始め、その結果被験者の食べる量が減ったからだと予測されている。
また、すべてのグループに実験前より体重が増えた人がおり、中には10ポンド(約4.5キログラム)以上太った人たちもいた。つまり運動を始めたことによって、たくさんの人が実験前より多くの食事をとるようになった、もしくは運動したご褒美として実験前より家で動かなくなったということだ。チャーチ博士はこの現象を「compensation(代償作用)」と呼んでいる。
だが、そうやって自分の中にある欲望に負けるのは、ダイエットの意志が弱いからだという人もいるかもしれない。しかし、心理学上人間は自分の欲望を長期間抑えることができないのだ。2000年に心理学者のマーク・ムレイブン氏とロイ・バウマイスター氏が発表した論文によると、人の自制心は筋肉に似ているらしい。なぜなら自制心も使った後は弱くなるから。
よって、ダイエットのために自分を奮い立たせて1時間ジョギングをしても、その後自制心は低下し、お昼はサラダではなく自分の好きな脂っこい食べ物や甘い食べ物をついつい食べてしまうのだ。
その一方で、運動をすれば脂肪が筋肉に変わり、そして筋肉が増えれば基礎代謝が上がるのではという声もあるだろう。確かに、筋肉の増加によって基礎代謝量は増えるのだが、2001年にコロンビア大学が割り出した数値によると、1パウンド(約0.45キログラム)の筋肉は1日に6キロカロリー、1パウンドの脂肪は1日に2キロカロリーを基礎代謝として消費している。
つまり、頑張って10パウンド(約4.5キログラム)の脂肪を筋肉に変えたとしても、1日の基礎代謝量は40キロカロリー(バター小さじ一杯分)しか増えないのだ。
それでは、運動には全くメリットはないのだろうか? もちろんそういうことはない。むしろ運動をすると、心臓が強くなったり、ガンや糖尿病などの様々な病気にかかりにくくなったり、精神的なストレスも解消されたりと、それがもたらす健康効果は非常に大きい。ただ運動は体重を減らすのには向いていないというだけ。
では、体重を減らすのにはどうしたらいいのか? TIMEによると、何を食べるかに気を遣いなさいとのこと。意外とシンプルな答えが待っていた……(TIME)
ダイエットの研究は過去のものを塗り替えるためにあるんじゃないかと思うくらい、これまでの認識が悉くひっくり返ります。今回もダイエットに絶対であった「運動」が否定されています。ボディメイキングには必須であるかとは思うのですが。
運動するとその後の活動の意識が変わる、と己の体験で実感しています。一時期走っていない時がありましたが、ダイエット意識が低下していたのは間違いないです。運動による意識が自制心のキープに繋がるのは間違いないはず。
しかし、この記事は運動人口の低下をまねき、結果太る方が増えるのではないかと。
これは米ニュース雑誌「TIME」によって紹介され、世界に衝撃を与えている。TIMEによると、確かに運動はカロリーを消費し、そしてカロリーの消費は体重の減少をもたらすのだが、運動にはある問題がある。それは私たちを空腹にしてしまうこと。
みなさんも経験があると思うが、人は運動後お腹が減り、いつもより食べ物を食べてしまう。また、運動したという達成感からも普段以上に食べてしまい、これが運動で消費したカロリーをあっという間に帳消しにする。場合によっては、運動で消費した以上のカロリーを食べ物から摂取してしまうことも。
これを示す例として、TIMEは科学雑誌「PLoS ONE」とティモシー・チャーチ博士が共同で行った実験を紹介している。
彼らは普段運動しない464人の肥満女性を対象に、次のような実験を行った。
1)464人を4つのグループに分ける。
2)グループAには専属トレーナーと共に一週間に72分、グループBには一週間に136分、グループCには一週間に194分運動してもらう。グループDは今までどおりの運動量を維持してもらう。
3)4グループとも食習慣は変えず、また一ヶ月ごとに健康診断アンケートに答えてもらう。
4)この生活を6ヶ月間続けてもらう。
6ヵ月後、平均してすべてのグループで体重が減っていたのだが、体重が減った量に関して、グループA、B、CとグループDにそれほど大差がなかったのだ。グループDの体重が減った理由としては、定期的な健康アンケートによって、被験者が自分が食べているものを意識し始め、その結果被験者の食べる量が減ったからだと予測されている。
また、すべてのグループに実験前より体重が増えた人がおり、中には10ポンド(約4.5キログラム)以上太った人たちもいた。つまり運動を始めたことによって、たくさんの人が実験前より多くの食事をとるようになった、もしくは運動したご褒美として実験前より家で動かなくなったということだ。チャーチ博士はこの現象を「compensation(代償作用)」と呼んでいる。
だが、そうやって自分の中にある欲望に負けるのは、ダイエットの意志が弱いからだという人もいるかもしれない。しかし、心理学上人間は自分の欲望を長期間抑えることができないのだ。2000年に心理学者のマーク・ムレイブン氏とロイ・バウマイスター氏が発表した論文によると、人の自制心は筋肉に似ているらしい。なぜなら自制心も使った後は弱くなるから。
よって、ダイエットのために自分を奮い立たせて1時間ジョギングをしても、その後自制心は低下し、お昼はサラダではなく自分の好きな脂っこい食べ物や甘い食べ物をついつい食べてしまうのだ。
その一方で、運動をすれば脂肪が筋肉に変わり、そして筋肉が増えれば基礎代謝が上がるのではという声もあるだろう。確かに、筋肉の増加によって基礎代謝量は増えるのだが、2001年にコロンビア大学が割り出した数値によると、1パウンド(約0.45キログラム)の筋肉は1日に6キロカロリー、1パウンドの脂肪は1日に2キロカロリーを基礎代謝として消費している。
つまり、頑張って10パウンド(約4.5キログラム)の脂肪を筋肉に変えたとしても、1日の基礎代謝量は40キロカロリー(バター小さじ一杯分)しか増えないのだ。
それでは、運動には全くメリットはないのだろうか? もちろんそういうことはない。むしろ運動をすると、心臓が強くなったり、ガンや糖尿病などの様々な病気にかかりにくくなったり、精神的なストレスも解消されたりと、それがもたらす健康効果は非常に大きい。ただ運動は体重を減らすのには向いていないというだけ。
では、体重を減らすのにはどうしたらいいのか? TIMEによると、何を食べるかに気を遣いなさいとのこと。意外とシンプルな答えが待っていた……(TIME)
ダイエットの研究は過去のものを塗り替えるためにあるんじゃないかと思うくらい、これまでの認識が悉くひっくり返ります。今回もダイエットに絶対であった「運動」が否定されています。ボディメイキングには必須であるかとは思うのですが。
運動するとその後の活動の意識が変わる、と己の体験で実感しています。一時期走っていない時がありましたが、ダイエット意識が低下していたのは間違いないです。運動による意識が自制心のキープに繋がるのは間違いないはず。
しかし、この記事は運動人口の低下をまねき、結果太る方が増えるのではないかと。














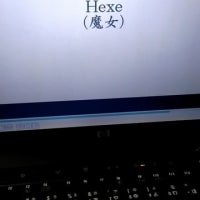





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます