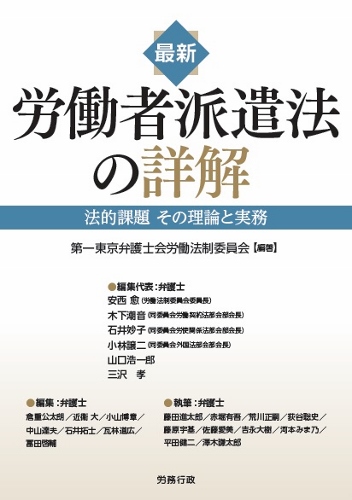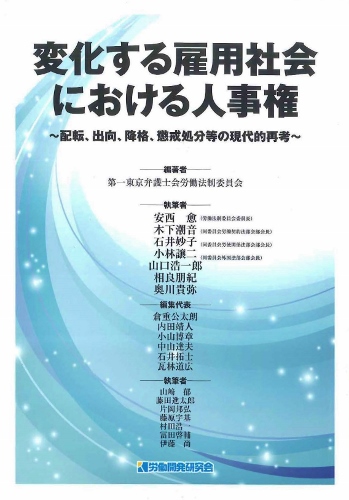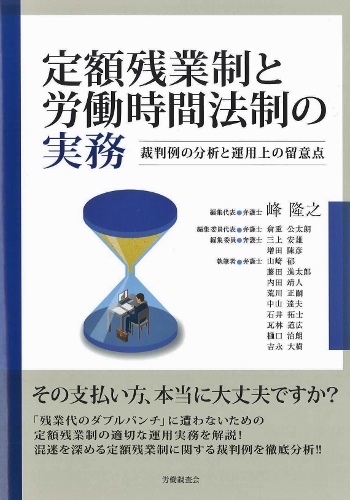Q3 勤務態度が悪い。
勤務態度の悪さは,基本的には注意,指導,教育して改善させるべき問題です。
口頭で注意,指導,教育しても改善しない場合は,書面で注意,指導,教育することになります。
書面を交付するのは大げさでやりにくいというのであれば,まずは電子メール等を利用することから始めてもよいでしょう。
書面で注意,指導,教育しても改善しない場合は,懲戒処分を検討することになります。
懲戒処分を行っても改善しない場合は,退職勧奨,解雇等を検討せざるを得ませんが,最後の手段です。
十分な注意,指導,教育をしないままいきなり解雇した場合は,無効とされるリスクが高くなります。
解雇が有効とされるためには,解雇予告手続(労基法20条)を取るだけでなく,就業規則の普通解雇事由又は懲戒解雇事由に該当し,解雇権濫用(労契法16条)や懲戒権の濫用(労契法15条)とされないこと等が必要となります。
解雇予告手続を取ったとしても解雇事由に該当しなければ解雇は無効となりますし,解雇事由に該当したとしても,解雇権又は懲戒権を濫用したものとして解雇が無効とされるリスクがあることに注意して下さい。
「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」(労契法16条),「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」(労契法15条)とされています。
普通解雇の場合は,職場から排除しなければならないほど社員としての適格性がないといえるのかが,懲戒解雇の場合は,職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが問題となります。
注意,指導,教育して,勤務態度の悪さを改善させることができるのであれば,注意,指導,教育して改善させればいいのですから,解雇の有効性を判断する際にも,改善が期待できないくらい勤務態度が悪いと評価できるかが問題となります。
注意,指導,教育して改善の機会を与えることもせずに,勝手に,改善の見込みがないと思い込んで解雇するのは危険です。
まずは,実際に,注意,指導,教育して改善の機会を与え,改善の見込みがないかどうかを確かめたことの証拠を残しておく必要があります。
口頭で注意,指導,教育しても改まらない場合には,書面で注意,指導,教育し,記録に残しておくべきです。
書面等の客観的証拠がないと,訴訟になった場合は,「注意,指導,教育されたことはありません。」と主張されるのが通常です。
また,書面で注意,指導,教育することにより,口頭での注意,指導,教育よりもより強く改善を促しているというメッセージにもなります。
書面で注意,指導,教育しても改善しない場合は,懲戒処分を検討します。
懲戒処分が有効というためには,就業規則の定める懲戒事由に該当し,懲戒権の濫用(労契法15条)にあたらず,就業規則の手続に従っていることが必要となります。
労契法15条では「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と定められており,懲戒事由に該当する場合であっても,懲戒処分が有効となるとは限らないことに注意が必要です。
もっとも,軽度の懲戒処分であれば使用者の裁量の幅が広く,有効と判断されるケースが多いですし,訴訟等で争われるリスクも比較的低いところです。
懲戒処分や事前の警告が解雇の前提要件というわけではありませんが,解雇は,余程悪質な事案を除き,戒告,減給,降格処分等の懲戒処分をし,改善しなければ解雇する可能性がある旨の警告をしてからにすることが望ましいところです。
問題社員に対して最初に行う処分が懲戒解雇,諭旨解雇といった退職の効果を伴う処分である場合は,訴訟等で使用者側か苦戦するケースが多いというのが実情です。
十分に注意,指導,教育し,繰り返し懲戒処分を行っているようなケースの場合,解雇をするまでもなく,合意退職が成立することが多いです。
解雇の有効性を見通すことが困難なケースが多いこともあり,どうしても辞めてもらいたい問題社員については,まずは退職勧奨により退職届を提出してもらうことに全力を尽くすのがセオリーです。
転職が容易ではない社員については,退職の合意を取り付ける難易度が高く,解雇した場合も訴訟等のトラブルになるリスクが高いです。
例えば,(賃金水準はそれ程高くなくても)居心地のいい職場に長年勤務している能力が低い社員に対し,退職勧奨したり解雇したりすると,訴訟等のトラブルに発展することが多いという印象です。
弁護士 藤田 進太郎
勤務態度の悪さは,基本的には注意,指導,教育して改善させるべき問題です。
口頭で注意,指導,教育しても改善しない場合は,書面で注意,指導,教育することになります。
書面を交付するのは大げさでやりにくいというのであれば,まずは電子メール等を利用することから始めてもよいでしょう。
書面で注意,指導,教育しても改善しない場合は,懲戒処分を検討することになります。
懲戒処分を行っても改善しない場合は,退職勧奨,解雇等を検討せざるを得ませんが,最後の手段です。
十分な注意,指導,教育をしないままいきなり解雇した場合は,無効とされるリスクが高くなります。
解雇が有効とされるためには,解雇予告手続(労基法20条)を取るだけでなく,就業規則の普通解雇事由又は懲戒解雇事由に該当し,解雇権濫用(労契法16条)や懲戒権の濫用(労契法15条)とされないこと等が必要となります。
解雇予告手続を取ったとしても解雇事由に該当しなければ解雇は無効となりますし,解雇事由に該当したとしても,解雇権又は懲戒権を濫用したものとして解雇が無効とされるリスクがあることに注意して下さい。
「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」(労契法16条),「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」(労契法15条)とされています。
普通解雇の場合は,職場から排除しなければならないほど社員としての適格性がないといえるのかが,懲戒解雇の場合は,職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが問題となります。
注意,指導,教育して,勤務態度の悪さを改善させることができるのであれば,注意,指導,教育して改善させればいいのですから,解雇の有効性を判断する際にも,改善が期待できないくらい勤務態度が悪いと評価できるかが問題となります。
注意,指導,教育して改善の機会を与えることもせずに,勝手に,改善の見込みがないと思い込んで解雇するのは危険です。
まずは,実際に,注意,指導,教育して改善の機会を与え,改善の見込みがないかどうかを確かめたことの証拠を残しておく必要があります。
口頭で注意,指導,教育しても改まらない場合には,書面で注意,指導,教育し,記録に残しておくべきです。
書面等の客観的証拠がないと,訴訟になった場合は,「注意,指導,教育されたことはありません。」と主張されるのが通常です。
また,書面で注意,指導,教育することにより,口頭での注意,指導,教育よりもより強く改善を促しているというメッセージにもなります。
書面で注意,指導,教育しても改善しない場合は,懲戒処分を検討します。
懲戒処分が有効というためには,就業規則の定める懲戒事由に該当し,懲戒権の濫用(労契法15条)にあたらず,就業規則の手続に従っていることが必要となります。
労契法15条では「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と定められており,懲戒事由に該当する場合であっても,懲戒処分が有効となるとは限らないことに注意が必要です。
もっとも,軽度の懲戒処分であれば使用者の裁量の幅が広く,有効と判断されるケースが多いですし,訴訟等で争われるリスクも比較的低いところです。
懲戒処分や事前の警告が解雇の前提要件というわけではありませんが,解雇は,余程悪質な事案を除き,戒告,減給,降格処分等の懲戒処分をし,改善しなければ解雇する可能性がある旨の警告をしてからにすることが望ましいところです。
問題社員に対して最初に行う処分が懲戒解雇,諭旨解雇といった退職の効果を伴う処分である場合は,訴訟等で使用者側か苦戦するケースが多いというのが実情です。
十分に注意,指導,教育し,繰り返し懲戒処分を行っているようなケースの場合,解雇をするまでもなく,合意退職が成立することが多いです。
解雇の有効性を見通すことが困難なケースが多いこともあり,どうしても辞めてもらいたい問題社員については,まずは退職勧奨により退職届を提出してもらうことに全力を尽くすのがセオリーです。
転職が容易ではない社員については,退職の合意を取り付ける難易度が高く,解雇した場合も訴訟等のトラブルになるリスクが高いです。
例えば,(賃金水準はそれ程高くなくても)居心地のいい職場に長年勤務している能力が低い社員に対し,退職勧奨したり解雇したりすると,訴訟等のトラブルに発展することが多いという印象です。
弁護士 藤田 進太郎