マーラーの交響曲第3番を聴いたのは、偶然だった。大学に入学して、第二外国語の志望動機を「ドストエフスキーを原書で読みたい」と空想を述べたが、文字通り空想となるのには時間を要しなかった。 しかし入学当初はまだ神保町の、ナウカや日ソ図書センターに出向いた。当時ソ連共産党の評価をめぐり、日共系と社会党系が分裂し、私はもっぱら日ソ図書センターに顔を出した。そんなある日バイトで稼いだ金を手に、ロシア語教材を買うつもりで行ったのだが、そこに目にしたのがNo9 の2枚組LPだった。当時LP1枚2000円の時代に確かLP2枚2500円ではなかったか?値段の安さとMahlerの未知の曲を聴きたい思いで購入したのでした。当時の我が家のステレオは、親戚からの大学入学祝い金をつぎ込んで購入した、パイオニア製のセパレート(スピーカーボックスが左右に分かれている)タイプのもので、結構大きいものでしたが、今から思えば、現在のちょっと高めのCDラジカセに劣る程度の音質だったのではと思います。それでもレコード針を落とした途端出てきた音は、グロテスクと思えるほど、暗く・重い・陰鬱な響きが部屋中重くのしかかる雰囲気でした。これまで聴いてきた、「大地の歌」「交響曲4番」とは異質の演奏に思え、当時のレコード**なるレコード評でも無視されるなどして、自分もその程度の演奏かと曲そのものも理解しえないでいました。
の2枚組LPだった。当時LP1枚2000円の時代に確かLP2枚2500円ではなかったか?値段の安さとMahlerの未知の曲を聴きたい思いで購入したのでした。当時の我が家のステレオは、親戚からの大学入学祝い金をつぎ込んで購入した、パイオニア製のセパレート(スピーカーボックスが左右に分かれている)タイプのもので、結構大きいものでしたが、今から思えば、現在のちょっと高めのCDラジカセに劣る程度の音質だったのではと思います。それでもレコード針を落とした途端出てきた音は、グロテスクと思えるほど、暗く・重い・陰鬱な響きが部屋中重くのしかかる雰囲気でした。これまで聴いてきた、「大地の歌」「交響曲4番」とは異質の演奏に思え、当時のレコード**なるレコード評でも無視されるなどして、自分もその程度の演奏かと曲そのものも理解しえないでいました。
その後はCD時代になってNo.1 を購入するまでほとんど聞くことはありませんでした。しかし、No.1の録音はNo.9と同年なのですが、まさに当時の米・ソの対立時代そのもので、明暗の両極とも思える、対照的な演奏でした。当時のレコードXXという雑誌の評価をはじめ、各種の評価もコンドラシンの演奏は無視され続けていました。反面No.1は当時は推薦盤でした。
を購入するまでほとんど聞くことはありませんでした。しかし、No.1の録音はNo.9と同年なのですが、まさに当時の米・ソの対立時代そのもので、明暗の両極とも思える、対照的な演奏でした。当時のレコードXXという雑誌の評価をはじめ、各種の評価もコンドラシンの演奏は無視され続けていました。反面No.1は当時は推薦盤でした。
その後No2のNHK-BSで放映されたものをDVDにダビングしたウィーンフィルとの演奏
 も聴いたが、この演奏は「オーストリアにあってはボヘミヤ人として、ドイツにあってはオーストリア人として、世界にあってはユダヤ人として」疎外感を味わったマーラー音楽の本質に迫る、L・Bの「NYにあってはロシア移民の子、ウィーンにあってはアメリカ人。世界にあっては、ユダヤ人」がマーラーと境遇とダブり別録音ではあるが、リハーサル風景(5番、9番の時の)のウィーンフィルの団員に対して、声を荒げて「マーラーはあなた方の音楽なのに、なぜ理解しないのか」と叫ぶL.Bの感情過多の演奏でした。したがって私には、No.1のほうが明快で聴きやすいと今でも思っているが、それにもまして、手持ちの演奏を改めて聴き返すと、No.9の演奏のすごさがわかったような気がします。
も聴いたが、この演奏は「オーストリアにあってはボヘミヤ人として、ドイツにあってはオーストリア人として、世界にあってはユダヤ人として」疎外感を味わったマーラー音楽の本質に迫る、L・Bの「NYにあってはロシア移民の子、ウィーンにあってはアメリカ人。世界にあっては、ユダヤ人」がマーラーと境遇とダブり別録音ではあるが、リハーサル風景(5番、9番の時の)のウィーンフィルの団員に対して、声を荒げて「マーラーはあなた方の音楽なのに、なぜ理解しないのか」と叫ぶL.Bの感情過多の演奏でした。したがって私には、No.1のほうが明快で聴きやすいと今でも思っているが、それにもまして、手持ちの演奏を改めて聴き返すと、No.9の演奏のすごさがわかったような気がします。
交響曲という形式に対するイノベーションは、ベートーベンの合唱付き,ベルリオーズの幻想交響曲と進展してきたが、それらの連続性を破壊したものが、マーラーの3番だと私は思う。これはすでに交響曲という名のジャンルを破壊した曲で、その意味からするとコンドラシンの演奏のすごさが理解できる。強弱の振幅の激しさ、弦楽器の露骨なクレシェンド、それでいながら、強固な構成を保ち揺るぎのない演奏は、指揮者、楽団の技量のすごさが伝わる。ただ録音に鮮明さが欠けるのが唯一の欠点といえる。(ただし歌唱はロシア語も欠点の要素か?)それでも私はこの演奏を今では24bit,96kHzにデジタル変換して聴いている。私の一押し推薦盤。
No.5 ベルナルド・ハイティンクという指揮者は不思議な指揮者だ。モーツァルトを振っても、ストラヴィンスキーを振っても違和感がなく、加えてヴェルディーもワグナーのオペラを振っても違和感のない音楽を作り出す。それでいて、ウィーンフィルであればウィーンフィルらしい音楽が流れ、ベルリンではベルリンフィルの音楽が出てくる。一聴すると、単なるメトロノームのようにの思えるが、聴き終えた時の満足感は大きい。マーラーの3番の破たんした音楽を、再構築を施し、ベルリンフィルの技量のなせる業かもしれないが、音楽が流れ、グロテスクともいえる音楽を美しくまとめ上げている。しかもスケール感の大きなまとめ方だ。推薦盤
ベルナルド・ハイティンクという指揮者は不思議な指揮者だ。モーツァルトを振っても、ストラヴィンスキーを振っても違和感がなく、加えてヴェルディーもワグナーのオペラを振っても違和感のない音楽を作り出す。それでいて、ウィーンフィルであればウィーンフィルらしい音楽が流れ、ベルリンではベルリンフィルの音楽が出てくる。一聴すると、単なるメトロノームのようにの思えるが、聴き終えた時の満足感は大きい。マーラーの3番の破たんした音楽を、再構築を施し、ベルリンフィルの技量のなせる業かもしれないが、音楽が流れ、グロテスクともいえる音楽を美しくまとめ上げている。しかもスケール感の大きなまとめ方だ。推薦盤
No.3 No.4
No.4 アバドのマーラーについては下記Blogをご覧いただければ幸いです。
アバドのマーラーについては下記Blogをご覧いただければ幸いです。
アバド追憶 マーラーの交響曲 2番&3番(http://blog.goo.ne.jp/yyamamot7493/e/c4dd130ddb26da486b1cb30bcafee13a)
No.6 LP時代、レコード***なる雑誌の評論家のご推薦だったが、安サラリーマン時代には買えなかった。しかしCD時代になり、廉価版CDで名をはせたBRILLIANTレーベルが様々なレーベルのマーラーの交響曲を寄せ集め廉価版全集として売り出した。安さにつられ購入したが、マーラーの骨格をレントゲン写真さながらに浮き出した演奏は、マーラーの大切な歌心までそぎ取ってしまった演奏になっている。
LP時代、レコード***なる雑誌の評論家のご推薦だったが、安サラリーマン時代には買えなかった。しかしCD時代になり、廉価版CDで名をはせたBRILLIANTレーベルが様々なレーベルのマーラーの交響曲を寄せ集め廉価版全集として売り出した。安さにつられ購入したが、マーラーの骨格をレントゲン写真さながらに浮き出した演奏は、マーラーの大切な歌心までそぎ取ってしまった演奏になっている。
No.7 DENONのデジタル録音で評判を呼んだエリアフ・インバル+フランクフルト放送交響楽団のCDがBRILLIANTレーベルで廉価版となり購入。全曲を知りたい人にはお勧め。
DENONのデジタル録音で評判を呼んだエリアフ・インバル+フランクフルト放送交響楽団のCDがBRILLIANTレーベルで廉価版となり購入。全曲を知りたい人にはお勧め。
No.8 BS-Hiでの画像の美しさが光る。演奏も生誕150年記念演奏会として行われたもので、オーケストラの力量が反映された響きの美しさは認めるが、この曲の特色であるグロテスクさはない。
BS-Hiでの画像の美しさが光る。演奏も生誕150年記念演奏会として行われたもので、オーケストラの力量が反映された響きの美しさは認めるが、この曲の特色であるグロテスクさはない。
| Mahler,Gustav Sym No.3 | |||||||
| Con | Orch | Rec Time | Alto | Rec | |||
| 1 | Bernstein,Leonard | New York Phi | 99:57:00 | ,Martha Lipton | SM2K 47576 | 1961/04/03 | CD/2 |
| 2 | Bernstein,Leonard | Winner Phi | UK | Christa Ludwig | DVD=NHK | 1972/04 | Winne |
| 3 | Claudio Abbado | Berliner Phil | UK | アンナ・ラーション | DVD=NHK | 1998/10/19 | サントリーホール |
| 4 | Claudio Abbado | Lucerne Festival Orchestra | UK | アンナ・ラーション | DVD=NHK | 2007/08/18-19 | Lucerne Festival |
| 5 | Haitink,Bernard | Berlin Phi | UK | フローレンス・クイヴァー | DVD=Sky-A | 1992/12 | Berlin |
| 6 | Horenstein,Jascha | London Sym | 97:36:00 | Norma Procter | BRILLIANT | CD/11 | |
| 7 | Inbal,Eliahu | RSO Frankfurt | 98:13:00 | Doris Soffel | BRILLIANT | 1985/04/18-19 | CD/15 |
| 8 | Jansons,Mariss | Concertgebouw Orch Amsterdam | 98:03:00 | ベルナルダ・フィンク | BD=NHK | 2010/02/03 | Amsterdam |
| 9 | Kondrashin,Kirill | Moscow Phi | 90:26:00 | Valentina Levko | C-0383 | 1961 | LP/2 |














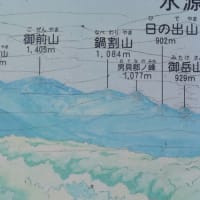






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます