
ヤナーチェックを集中的に聴こうと思って自分のコレクッションを整理していたら、偶然マルテヌーのNHKBSで放映された時のVTRが出てきた。1995/12のプラハでのウラジーミル・ヴァレークとチェコフィルとのコンサートで、ピアノ協奏曲4番、日本の和歌を素材にした歌曲ニッポリナ、それに交響曲1番のコンサートだった。
どれもが耳に優しい聴きやすい曲だった。
この放送の前後に偶然ではあるが結構マルティヌーのCDを買い込んでいた。私のリストに1997年購入と記されていたノイマン=チェコフィルとの全6曲の交響曲はナチにより祖国を追われたどり着いたアメリカで作曲されたものだ。そのためか、戦争の悲劇も、前衛音楽の先鋭さも欠けてはいるが、それがかえってバルトークとは違ったアメリカでの創作意欲となったのだろうか。当初はそこが物足りなくバルトークほど聴く機会はなかった。しかし改めて聴くと、ドボルザークの響きも聞こえ懐かしい響きがする。1942年から53年の間に書かれた曲だが、スメタナの時代に戻ったような雰囲気だ。アメリカ大陸にはなぜか故郷への望郷の念を止められない何かがあるのだろうか、シェーンベルクもストラヴィンスキーも戦火に終われアメリカに渡ると先鋭さが消えていった。コルンゴルドはどっぷりハリウッドに埋没してしまった。
でもマルティヌーの交響曲にはなぜがバルトーク同様のエトランゼの哀愁が漂う。

ミュンシュ=ボストン交響楽団の演奏で6番の交響曲がある。
アメリカでのマルティヌーはクーゼビッキーが支援したこともありボストン交響楽団が1,3,6番を初演しており、6番はミュンシュが1955/12に初演しておりこのCDは翌年の録音だ。「交響的幻想曲」の副題があるが、ミュンシュの変幻自在にオケを操りダイナミックな響きはまさに幻想的だ。
いずれにしても判りやすく聴きやすい交響曲だが、ヤナーチェックのような音楽の凄みは感じない。
どれもが耳に優しい聴きやすい曲だった。
この放送の前後に偶然ではあるが結構マルティヌーのCDを買い込んでいた。私のリストに1997年購入と記されていたノイマン=チェコフィルとの全6曲の交響曲はナチにより祖国を追われたどり着いたアメリカで作曲されたものだ。そのためか、戦争の悲劇も、前衛音楽の先鋭さも欠けてはいるが、それがかえってバルトークとは違ったアメリカでの創作意欲となったのだろうか。当初はそこが物足りなくバルトークほど聴く機会はなかった。しかし改めて聴くと、ドボルザークの響きも聞こえ懐かしい響きがする。1942年から53年の間に書かれた曲だが、スメタナの時代に戻ったような雰囲気だ。アメリカ大陸にはなぜか故郷への望郷の念を止められない何かがあるのだろうか、シェーンベルクもストラヴィンスキーも戦火に終われアメリカに渡ると先鋭さが消えていった。コルンゴルドはどっぷりハリウッドに埋没してしまった。
でもマルティヌーの交響曲にはなぜがバルトーク同様のエトランゼの哀愁が漂う。

ミュンシュ=ボストン交響楽団の演奏で6番の交響曲がある。
アメリカでのマルティヌーはクーゼビッキーが支援したこともありボストン交響楽団が1,3,6番を初演しており、6番はミュンシュが1955/12に初演しておりこのCDは翌年の録音だ。「交響的幻想曲」の副題があるが、ミュンシュの変幻自在にオケを操りダイナミックな響きはまさに幻想的だ。
いずれにしても判りやすく聴きやすい交響曲だが、ヤナーチェックのような音楽の凄みは感じない。














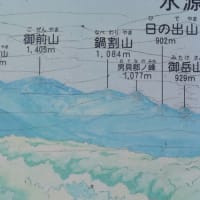






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます