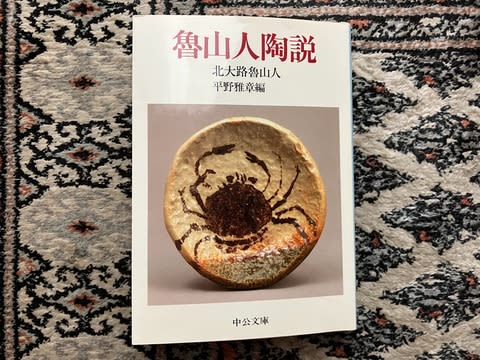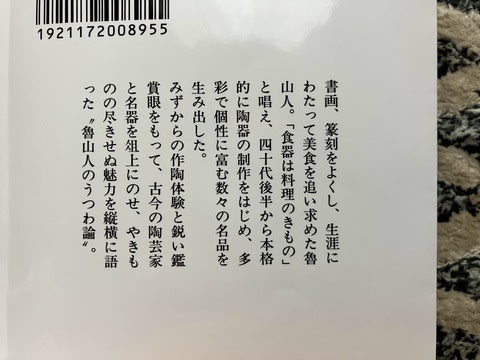映画「ブリッジ・オブ・スパイ」を観た。2015年、米、スティーブン・スピルバーグ監督、コーエン兄弟脚本、原題Bridge of Spies。なぜこの映画を観たかというと、最近、中川右介著「冷戦とクラシック」という本を再読したら、最後のあとがきに、氏がこの映画のことに言及していたからだ。氏の本は冷戦時に音楽家たちがどういう人生をたどったのかを書いたものであり、この映画も冷戦を描いている。

冷戦時、ベルリンの壁ができる少し前、アメリカで活動していたソ連のスパイのアベル(マークライランス)がFBIに逮捕された、米政府は形だけの裁判によりアベルを死刑にするべく法廷の準備をする、弁護士のドノバン(トム・ハンクス)にアベルの弁護の依頼がくる。ドノバンは嫌がったが引き受けざるを得なくなった。調べていくとアベルはソ連を売るようなことはせず、また、FBIによるアベルの逮捕についても捜査令状もスパイとしての逮捕状もないことが明らかになるが、検事に裁判は形だけだで有罪にすることが大事と言われた。やがて、ドノバンは司法長官に直談判に及びアベルを死刑にしたらソ連が米人スパイを拘束したときに交換条件で差し出す切り札がなくなり米人を危険に晒すと訴えると事態は・・・
その後、米偵察機がソ連上空で追撃され、米兵がソ連に拘束され、東ドイツでは米学生が拘束された。そして人質交換を司法長官に訴えたドノバンに米政府非公式代表でベルリンでソ連と東ドイツと非公式交渉を始める。

このストーリーは実話だとテロップにでていた。有り得る話だろう。ドノバンはその後ケネディ大統領から新たな任務を与えられ、1962年にピッグス湾での捕虜1113名の解放を目指してキューバのカストロと交渉して9703名の男女子供が解放された。ホンマかいなと思うような偉業だ。
いくつかのコメントを書きたい
- ストーリーは面白く、2時間以上の映画だったが、時間の長さは全く感じなかった。スピルバーグ監督やコーエン兄弟の脚本が良いのだろう。しかし、ただ面白かっただけの映画であるとも言える、何か観た人に考えさせるような内容がないのは、アメリカではそのような韻を含んだ映画は流行らないので、この映画のようなわかりやすい映画が作られるのだと思う、といったら米人に失礼か。
- ただ、日本人には、自国民がスパイ容疑で他国に拘束されたら、相手国のスパイを拘束して、交換することによって救出する、これが現実だ、という教訓を示している。今現在でも多くの日本人がスパイ容疑で隣国に拘束されている。「改正反スパイ法」でますます日本人は狙い撃ちされるであろうが、隣国のスパイは我が国でやりたい放題やっている。日本も法改正して隣国のスパイを拘束し、自国民救出の材料とするしかないのが世界の現実だと悟るべきだろう。
- 最近アメリカはイランに拘束されていた米人5人とアメリカが拘束していたイラン人5人を交換し、さらにイランの資産60億ドル(8,800億円)の凍結を解除したとのニュース があった。このバイデン政権のディールについて共和党は60億ドル払って人質を取り戻す実績を作ったとして疑問視しているようだ。
- この映画は「事実に基づく」と説明されている。「基づく」なのでどこまで事実かはわからない。例えば、ソ連のスパイを逮捕するのに明確な理由や証拠がないし、結論ありきで裁判は形式的だと裁判官が言う、こんなことまで事実に基づいているのだろうか。
- 私はほとんど事実ではないかと思った。アメリカというのは昔から敵を決めたら証拠をでっち上げてもやりたいことをやる国だ。その点、わが国の隣国やロシアと大差ない。大国は常に自分勝手だと日本人は悟るべきだ。アメリカの無法な振る舞いは以前観た映画「モーリタニアン、黒ぬりの記録」(こちらを参照)でも描かれている。日本は、アメリカを信用しきっていると、きっと裏切られるだろう。
- アメリカの偵察飛行機に乗り込む極秘任務の兵士に上司が、ソ連に捕まりそうになったらこの飛行機を爆破せよ、捕虜になりそうになったら1ドルコインの中にある毒がついた針で死ね、狙撃されるな、捕虜になるな、任務は家族にも誰にも言うな、という。これが兵士を大事に、捕虜を処遇を適切にする国のやることか。
- この極秘任務の兵士が拘束され、さらに東独に留学していた(左翼かぶれの)米人学生も拘束された。CIAは兵士の救出をミッションとし、左翼学生は見捨てろと最後までドノバンに言った。アメリカのヒューマニズムもこんなもんだろう。

非常に面白い映画だった。