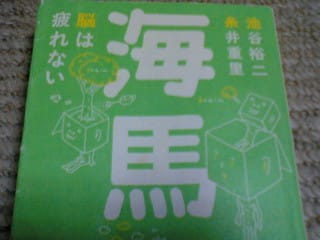
「海馬」糸井重里、池谷祐二の対談。
海馬は簡単にいうと、瞬間の記憶をしっかりと記憶するか、
忘れていいかの判断をしているようだ。
記憶について、丸暗記と経験にもとづく記憶を
二つに分けて議論しているのが、印象的。
ブログ書くついでにネット検索してみると
糸井をべた褒めの池谷のスタンスに批判があるが、おおむね好評。
アマゾンがカスタマーレビューが読めて良い。
レビューが81もあって、全部は読めない。
賛成した人の多さとか、もっと分類したり並べなおすような、
アマゾンの工夫が必要だな。
この本が2001年ごろの対談だ。
脳について科学と日常経験をつなぐ対談になっている。
海馬が壊れた人間について語る場面で、
5分の記憶しかない男がメモをたよりにして生きていく映画がでてきた。
私も、このタイプに非常に近い。
メモしないとすぐ忘れてしまう。
10分くらいまとめて教えてくれる先輩が、
なぜか途中でメモするのを嫌がるのだが、
私にはそれは一番困るのだ。
話してる内容を常に頭に入れて、しかも考えてしまうので、
聞いたことと考えたことが混ざって
10分の授業の間に結局なにを教わったか、分からなくなってしまう。
これは、学生時代(90年代後半)から自覚していた特徴で
「不揮発性メモリを持たない人間」と
自分で勝手に自己判断していた。
私のこの性質は、海馬の不具合と関係あるかもと、この本を読んでちょっと思った。
不揮発性メモリとは、
パソコンに使われるDRAMの揮発性メモリと比較される言葉で、
電源を切った後に情報が残る性質のメモリだ。
ちょっと発想が飛んでいるな。
つまり、DRAMは電源を入れている間は同じ内容を記憶していて
作業が続くわけだけど、それは、
常に消えかかる0・1の信号を書き直し続けている状態だというのが
根底にあるわけ。
現実のパソコンメモリとしての揮発性か不揮発性かのメモリの違いは
情報を保持するコンデンサから電気が逃げるか逃げないか?
という物理というのを学校で習っていたので、
ちょっと変わった、人間の記憶について解釈を自己流にしてたんだ。
瞬間的な注意力のふらつきが、電源オフのように働いて
連続した記憶が消えてしまって発想や言葉が飛び飛びになる症状についてだ。
さて、このふたりが自分で自分たちのことを天才だといっているような
対談でもあるんだが。
その二人に共通する逸話が自分とも共通していて、うれしかった。
「日常、常に歌っている」という共通点だ。
僕を知っているひとはみんな不思議がるんだけど、
駅から学校まで歩く時間に大きな声で鼻歌を歌ってしまうのだ。
実家に戻るとうちの母親がまったく一緒で、
始終歌っている。
たぶん外では歌ってないとは思うけどね。
ああ、そういう人も他にもいるんだな、
そんなひとで立派に活躍してる人もいるんだとホッとした。
あと、対談からの小さな教訓のひとつが
「ちいさな目標をひとつづつ達成していく」
っていうもの。
学生時代の恩師から言われたことを思い出した。
「たくさんのものをいっぺんに考えてはいけない。
ひとつづつ考えなさい。」
みたいな教えなんだ。
また、小さな達成が脳にとっても良いっていうのが、
今の資格勉強のテーマになっていて、
難しい資格を長期目標に据えて
簡単な資格を確実にとっていくことで「自信」をつける。
これが、勉強の目標になってる。
弁理士になって資格をもとにビジネスすることよりも
資格を取ったっていう達成感から自信という精神的な強さを
求めているんだ。
最終的には、自信だけあっても仕事がないといけないわけだから、
小さな資格たちを束ねる大きなビジョンが大切なんだけど、
もう少し、自分磨きレベルのプチ勉強でウォーミングアップしていく予定。
そうそう。やる気っていうのも化学物質で
風邪クスリとかで阻害されてしまうなんて話も載ってたなあ。
経験的に言えるんだけど、
やる気ってやり始めないと湧かないもんだ。
たとえば、勉強も、本を読んだりノートを作ったりと
やり始めると、その部分の脳が暖まって
(ウォーミングアップされて)、そこでようやく「やる気」が生まれた状態になる。
なんか今日はスーツをお値打ちに買うっていう小さな幸せから
1日ハッピーに過ごせた。
久しぶりにこんな長く書いたなあ。

















