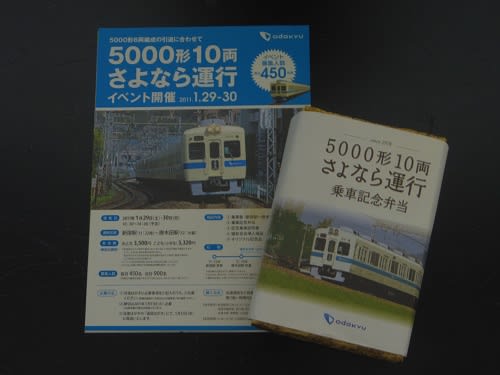生田緑地で保存されているスハ42 2047とD51 408を観察に行って来ました。生田緑地自体は何度も足を運んでいますが、枡形地区の川崎市青少年科学館がリニューアルされてからは初の訪問です。2012年4月にプラネタリウムと科学館の展示物を刷新したことは知っていたのですが、周辺にも大幅に手を入れていたことにビックリしました。。。
今日は登戸駅からのシャトルバスに乗って行こうと思っていたのですが、藤子・F・不二雄ミュージアムの展示物入れ替えに伴う休館によりバスも29日まで運休とのことだったので向ヶ丘遊園駅から徒歩で向かいました。正門を抜けて真っ直ぐ進むと、進行方向に見えて来ます。
以前は売店を併設した喫茶店の前にあり、どう見ても店の休憩スペースのような感じのあったスハ43ですが、科学館の改築とカフェの新設と共に綺麗に移設されていました。移転と共に整備を行ったようで青い車体が艶々と輝いています。貫通路が閉鎖され、ちょっと面妖な雰囲気の妻面ですが所属や自重、定員などの各種表記はキッチリ国鉄書体で美しく書き直されています。
車内に入ると、旧型客車独特の高い天井に板張りの床、質素な造りのボックスシートがずらりと並び往時を偲ばせてくれます。屋外の保存で自由に車内に見学出来るにも関わらず、注意書きの札が無ければ動態保存車と見紛うばかりの良好な状態を保っていますね。モケットの傷みもない他、トイレや洗面所も使用禁止(当然ですが)ながら透明の仕切りを設置して内部を見れるようにしている所にも驚かされます。市で管理しているとはいえ、整備が行き届かず劣化して処分されてしまったり、部品などを盗まれて無残な状態になる車両もある中、これ程手入れの行き届いた旧客の保存車はなかなか無いんじゃないでしょうかね。
窓を開けてみました。全ての客窓は開閉可能になっておりこちらにも補修が行われたのか、軽く力を入れただけで簡単に開けられるようになっています。

天井には古風な扇風機が取り付けられていますが、カバーをよく見ると「JNR」のロゴが入っています。これはアルファベット表記ですが、現在でもよく知られているマークより更に古いタイプなんでしょうか? ちなみに、車内の開放時間が午前9時30分から午後4時30分までの為か蛍光灯などの灯火類は取り外されていました。
解説によれば1948年に日本車輛で落成し水戸客貨車区に配置され1985年に廃車となり当地で保存されることになったそうです。後年改造で電気暖房装置を設置したことにより元々の番号である47に2000をプラスして2047号車となりました。原番号は「スハ42 47」で47番目に製造された車両ですね。(当時国鉄の規定では、電気暖房装置を備えた客車は車番+2000で区別していました)製造から67年、廃車後30年も過ぎているのにこの姿を保っているのは関係者の方々の相当な努力を窺わせます。
このスハ42形はオハ35形のグループの一員です。よく混同されるスハ43形客車は、従来車の実績を踏まえて居住性や乗り心地を大幅に改善し、1951年から製造されたグループでオハ35(スハ42)はこの一世代前の車両ということですね。戦前に登場したグループはオハ35以前に製造されていたスハ32系の設計を基本とし、TR23形台車形ペンシルバニア形軸ばね台車を装着していました。戦後の増備車より、軸受の構造を変更したTR34形台車へまず移行します。これらの台車は軌道に掛かる負荷が軽減できる特徴がありましたが乗り心地に難があった為、改善を図るべく新規設計されたウイングばね式鋳鋼台車TR40形台車に改められました。このTR40形台車では従来のものと比較すると約6トンも重量が増加したため、「スハ42」という形式に区分されることになったのです。ちなみに形式記号の片仮名は車両の重量を表し、オは大型のオが由来で32.5t以上37.5t未満の車両を示します。ス=37.5t以上42.5t未満の車両で、鋼製車体=スチールカーから、だそうな。(←自宅に戻ってから図鑑をひっくり返しネットで調べまくりました)

科学館の入り口付近にはD51 408号機が保存されています。こちらは特に場所は変更されませんでした。一応階段がありますが、運転室への立ち入りは出来ません。車体の各部が磨き上げられたようにピカピカでした。
408号機は最終配置が川崎市内の新鶴見機関区だったことが縁で保存に選ばれたようです。解説曰く生きた教材とのことですが、両者の状態の良さを見ると“今ひとたび”も可能なんじゃ・・・、と思ってしまいますね(笑)