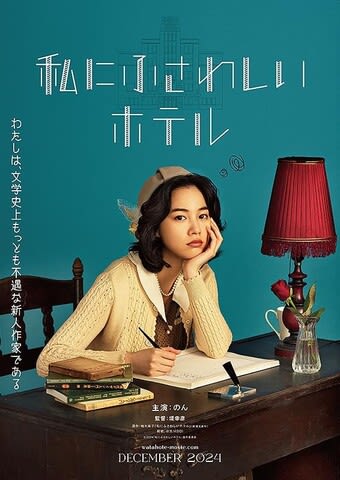オペラ演出家のオットー・シェンクが今月9日に亡くなったのを知った、享年94才(新聞記事はこちら)、オットー・シェンクは私の好きなオペレッタ「こうもり」の演出で知った、彼の演出した「こうもり」はつい最近までウィーン国立歌劇場で上演されていて私も大好きだった(こちら参照)、心よりご冥福をお祈りします





映画「はたらく細胞」を観た、2024年製作、109分、監督武内英樹
人間の体内の細胞たちを擬人化した斬新な設定で話題を集め、テレビアニメ化もされた同名漫画を実写映画化したもの、原作漫画「はたらく細胞」とスピンオフ漫画「はたらく細胞 BLACK」の2作品をもとに、ある人間親子の体内世界ではたらく細胞たちの活躍とその親子を中心とする人間世界のドラマを並行して描く映画

永野芽郁が赤血球役、佐藤健が白血球役でそれぞれ主演を務め、人間の漆崎茂を阿部サダヲ、その娘の日胡を芦田愛菜が演じる、人間の体内には37兆個もの細胞が存在し、無数の細胞たちが人間の健康を守るため日夜はたらいている
高校生の漆崎日胡は、父の茂と2人暮らし、健康的な生活習慣を送る日胡の体内の細胞たちはいつも楽しくはたらいているが、不規則・不摂生な茂の体内ではブラックな労働環境に疲れ果てた細胞たちが不満を訴えている、そんな中、よりによって日胡の体内へ侵入を狙う病原体が動き始め、細胞たちの戦いが始まるが・・・

なかなか面白い設定で、原作のすばらしさが想像できる、原作マンガは読んでいないが、いきなり映画を観ても十分理解できた、鑑賞した感想を述べよう
- 血液の働きなど知っているようで知らないことを勉強できた、血液の中の赤血球は酸素を運ぶ役割を、白血球は細菌と戦う役割があったとは知らなかった、キラーT細胞や血小板などいろんな医学用語が出てくるが、映画で見ているとその役割がよく理解できた
- 日胡が白血病になった時の治療で、放射線治療をすると体内を模した世界では空からオーロラが地上に降りてきて地上を焼き尽くすようなイメージが描かれ、また、抗がん剤治療を行うと、空から地上にいる悪玉菌めがけて抗がん剤のミサイルが飛んできて、悪玉菌だけではなく周辺の正常な組織にも被害を与える悲惨な状況になるのを実にうまく描がいていた

- 日胡が抗がん剤治療でも回復しないため、最後は骨髄移植を受けることになるが、骨髄移植とはてっきりドナーの骨髄を外科手術で患者の骨髄に移植することだとばかり思っていたが、映画ではドナーの腰(腸骨)から全身麻酔で吸引した骨髄液を患者に点滴で注入する治療の姿が描かれており、「そうなんだ」と初めてどういう治療かわかった、移植という言葉に惑わされていた
- 体内の血液の働きを説明するときの映像にはものすごい数のエキストラが使われており、さぞかし動員が大変だったろうな、コストがかさんだろうなと思った
いろいろ体内の仕組みについて勉強になったが、内容的には小学生が観て面白おかしく勉強する映画だと思った