
菅野完著『日本会議の研究』扶桑社新書212
政治に関しては疎い人間であるが、昨今の動き、流石に気になってきてこの本を注文した。アマゾンで2016-05-04に注文したが、2016-05-23にやっと届いた。05-01発行で、すでに第3刷、凄い売れ行きなのだ。
具体的で驚くべき内容に惹かれて夢中で読み通した。今の政権の目指すものは、アベノミクスとか憲法第九条改廃ではない。終局的にはもっと根本的な価値観の復古を狙う思想に支えられていることを指摘している。以下は印象に残った部分のメモである。
扶桑社はフジテレビの子会社で、「新しい歴史教科書をつく」った出版社である(教科書は現在育鵬社)。僕がこの会社の本を手にすることは初めてである。当の日本会議からは、事実誤認があるとして出版差し止めの要求が出ているという。いわばとんでもない爆弾と見えるが、内容は当事者たちへの面会や徹底した書誌的資料に依り、それらの裏とりも綿密に行っている。メディアや出版社などには、多様な人間がおり、利害も入り組んでいるだろうから、単純な色分けでは済まないところがある。
この本は安倍内閣のバックボーンをなす「日本会議」の組織的淵源を追求するものである。漠然と右翼思想と、靖国神社に代表される神道がまとまって起こしたものと言うのが、僕の感じ方であり、一般的理解であろう。これがひっくり返される。
著者、菅野はまずその動員の際の組織力、管理の周到で正確なことに注目する。これが政治家を惹きつける力にもなるという。小さくても頼りになると感じさせるのだ。リベラル、無党派の頼りなさとは正反対である。参加者の思想は幼稚であるが、企画者の事務能力はきわめて優れているとする。
彼らは中韓の反日と、クリントンに代表される世界の左翼が連携し、日本では平成に入って細川内閣が生まれたことに危機感を抱く。そこで対抗すべきポイントとして考えたものが「歴史認識」「夫婦別姓反対」「従軍慰安婦」「反ジェンダーフリー」の4点であるという。そして左翼に振り回されるのではなく、攻撃を仕掛けるべき時期に来たという「保守革命」を唱える。
その中心人物が安倍ブレーンのトップとされる「日本政策センター」の伊藤哲夫である。そのセミナーでは憲法改正のプログラムが次のように述べられている。
1.緊急事態条項の追加。
2.家族保護条項の追加。
3.自衛隊の国軍化。
1は三権分立、基本的人権の一時停止。内閣総理大臣に独裁権を与えるもの。この順序もまた重要である。そしてセミナーでの質疑に答える形で、研究センター側から「最終目標は明治憲法の復元」「しかしいきなり合意を得ることは難しいから合意を得やすいところから変えていく」という趣旨の発言があったという。そしてこうした運びは、内閣や自民党内の憲法改正推進本部の志向と一致している。
著者は「日本会議」を担うもう一つの組織「日本青年協議会」を挙げる。そしてこれも「日本政策センター」も、その指導者は「生長の家」に発することを突きとめる。生長の家は現在分裂して、「エコロジー左翼」と「生長の家原理主義運動」などと言うべきものになっており、彼らはその後者というわけである。
しかもこれらのリーダーの幾人かは、70年安保の頃の左翼学生に対抗する学生運動に起源を持っている。しかしそれが、左翼学生運動が力を失った50年後の現在まで持続しているのだ。しかし、これらのリーダーの誰をとっても、もう一つカリスマ性に欠ける。更に上に立つものがいるはずだとして、ベールの奥に安東巌という人物を探り当てる。
安東は青春期7年間を病気で臥せって過ごし、やがて生長の家に帰依することで快癒する。そして入った長崎大学で左翼学生の支配をひっくり返すのである。左翼の暴力による屈辱に耐え、まっとうな組織活動で勝利を収める様は感激的であり、民族派学生の伝説となったという。
後に新右翼「一水会」を起こす早稲田大学の鈴木邦男との、民族派内の争いにも一旦負けながら勝利する。ここでは陽性な鈴木と、対象的な安東の暗いが着実な性格が描かれる。安東の「講話」を聞いていると、この著者、菅野でさえ、爆笑し号泣するなど話しに引き込まれてしまうという。
しかし彼は表に立たないのである。安東の話は、生長の家の「中心帰一」という概念:「天之御中主神→天照大御神=天皇」の最後に「→谷口雅春」を付け加えたかのように見えるという。谷口雅春は神に近いのである。宗教運動なのである。
まとめると、日本会議の運動は、とても小さなグループによって指導されている。それは非民主的思想を持ちながら、草の根民主運動とでも言うべき地道な活動を粘り強く続けることで現在に至り、改憲に王手をかけているということだ。
この本、最後に近づくほど迫力を増し、安東の経歴を読むに連れ掌に汗を書くほどである。また半ば秘密に近いそういう事実を実証的に掘り起してゆく著者の執念にも驚きを覚えた。
政治に関しては疎い人間であるが、昨今の動き、流石に気になってきてこの本を注文した。アマゾンで2016-05-04に注文したが、2016-05-23にやっと届いた。05-01発行で、すでに第3刷、凄い売れ行きなのだ。
具体的で驚くべき内容に惹かれて夢中で読み通した。今の政権の目指すものは、アベノミクスとか憲法第九条改廃ではない。終局的にはもっと根本的な価値観の復古を狙う思想に支えられていることを指摘している。以下は印象に残った部分のメモである。
扶桑社はフジテレビの子会社で、「新しい歴史教科書をつく」った出版社である(教科書は現在育鵬社)。僕がこの会社の本を手にすることは初めてである。当の日本会議からは、事実誤認があるとして出版差し止めの要求が出ているという。いわばとんでもない爆弾と見えるが、内容は当事者たちへの面会や徹底した書誌的資料に依り、それらの裏とりも綿密に行っている。メディアや出版社などには、多様な人間がおり、利害も入り組んでいるだろうから、単純な色分けでは済まないところがある。
この本は安倍内閣のバックボーンをなす「日本会議」の組織的淵源を追求するものである。漠然と右翼思想と、靖国神社に代表される神道がまとまって起こしたものと言うのが、僕の感じ方であり、一般的理解であろう。これがひっくり返される。
著者、菅野はまずその動員の際の組織力、管理の周到で正確なことに注目する。これが政治家を惹きつける力にもなるという。小さくても頼りになると感じさせるのだ。リベラル、無党派の頼りなさとは正反対である。参加者の思想は幼稚であるが、企画者の事務能力はきわめて優れているとする。
彼らは中韓の反日と、クリントンに代表される世界の左翼が連携し、日本では平成に入って細川内閣が生まれたことに危機感を抱く。そこで対抗すべきポイントとして考えたものが「歴史認識」「夫婦別姓反対」「従軍慰安婦」「反ジェンダーフリー」の4点であるという。そして左翼に振り回されるのではなく、攻撃を仕掛けるべき時期に来たという「保守革命」を唱える。
その中心人物が安倍ブレーンのトップとされる「日本政策センター」の伊藤哲夫である。そのセミナーでは憲法改正のプログラムが次のように述べられている。
1.緊急事態条項の追加。
2.家族保護条項の追加。
3.自衛隊の国軍化。
1は三権分立、基本的人権の一時停止。内閣総理大臣に独裁権を与えるもの。この順序もまた重要である。そしてセミナーでの質疑に答える形で、研究センター側から「最終目標は明治憲法の復元」「しかしいきなり合意を得ることは難しいから合意を得やすいところから変えていく」という趣旨の発言があったという。そしてこうした運びは、内閣や自民党内の憲法改正推進本部の志向と一致している。
著者は「日本会議」を担うもう一つの組織「日本青年協議会」を挙げる。そしてこれも「日本政策センター」も、その指導者は「生長の家」に発することを突きとめる。生長の家は現在分裂して、「エコロジー左翼」と「生長の家原理主義運動」などと言うべきものになっており、彼らはその後者というわけである。
しかもこれらのリーダーの幾人かは、70年安保の頃の左翼学生に対抗する学生運動に起源を持っている。しかしそれが、左翼学生運動が力を失った50年後の現在まで持続しているのだ。しかし、これらのリーダーの誰をとっても、もう一つカリスマ性に欠ける。更に上に立つものがいるはずだとして、ベールの奥に安東巌という人物を探り当てる。
安東は青春期7年間を病気で臥せって過ごし、やがて生長の家に帰依することで快癒する。そして入った長崎大学で左翼学生の支配をひっくり返すのである。左翼の暴力による屈辱に耐え、まっとうな組織活動で勝利を収める様は感激的であり、民族派学生の伝説となったという。
後に新右翼「一水会」を起こす早稲田大学の鈴木邦男との、民族派内の争いにも一旦負けながら勝利する。ここでは陽性な鈴木と、対象的な安東の暗いが着実な性格が描かれる。安東の「講話」を聞いていると、この著者、菅野でさえ、爆笑し号泣するなど話しに引き込まれてしまうという。
しかし彼は表に立たないのである。安東の話は、生長の家の「中心帰一」という概念:「天之御中主神→天照大御神=天皇」の最後に「→谷口雅春」を付け加えたかのように見えるという。谷口雅春は神に近いのである。宗教運動なのである。
まとめると、日本会議の運動は、とても小さなグループによって指導されている。それは非民主的思想を持ちながら、草の根民主運動とでも言うべき地道な活動を粘り強く続けることで現在に至り、改憲に王手をかけているということだ。
この本、最後に近づくほど迫力を増し、安東の経歴を読むに連れ掌に汗を書くほどである。また半ば秘密に近いそういう事実を実証的に掘り起してゆく著者の執念にも驚きを覚えた。














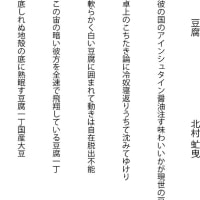
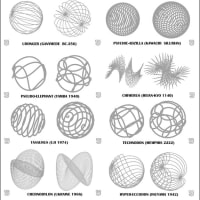












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます