
<維新派「アマハラ」>
維新派の公演「アマハラ」を見た。ダンス劇というのだろうか、この種のものを見たことは数えるほどしか無い。しかし期待を超える面白さであった。アート、文学、(数学以外の)学問、いずれに対しても素人で、見た作品は非常に少ない。劇の批評も真面目に読んだことはない。いつものとおり少ない例によって感じたことを述べる。
テーマは日本がアジアと不離不分のものであることの確認であろう。これは「東アジア文化都市2016奈良市」の行事であるが、2009年公演「台湾の、灰色の牛が背のびをしたとき」の題にすでに登場している。
見るところ、この劇団は徹底して人の間に距離をおいている。等間隔に並べることもしばしば。人は絡ませるのでなく、配置されるのである。(維新派ホームページ)をぜひ大画面で見ていただきたい。
僕は自分の創作を行うときは徹底して屋内密室派であるが、人と交流する場としては屋内が嫌いである。距離のおける屋外なら雄弁になれる。維新派の距離のことは、見終わりこの報告を書く段になって初めて気がついたのであるが、僕としては無意識的にそこが気に入っていたのである。
この人の間の距離はせりふにも現れている。劇の定番の応答はないのである。「あなたは何処にいるか」「フィリピンのバギオ」といった簡単な応答はあるのだが、論戦はない。説得し、あるいは学ぶというより、単に発語し感得する淡白なコミュニケーションである。ダンスでは当然と言われればそうであるが、ダンスよりは言葉に重きをおいている。民族区別的言い草となるが、北方よりも東南アジア的志向と言えようか。このさわやかさも僕が無意識的に選ぶ因となっている。こうした理屈、いささか自己撞着気味であるが。
この淡白さによって言葉の論理構造の必要性が減る。維新派はその代わりに単語の音色とリズムにこだわっている。盛り上がるところでは大きな装置の重低音がバックアップする。
アジアとのつながりがテーマであるから、舟を操るイメージや、トランクを持った移動のイメージはよく用いられるが、もう一つ目立つのは、労働を取り入れたダンスである。セバスチャン・サルガドの写真に見るような、重い労働の所作が踊りとなっている。
もう一つ、劇団のプリンシプルであろうが、強調すべきことがある。舞台の構築される場所である。今回は平城宮址(漢字制限によって平城宮跡とされた)である。平城京はシルクロードの終着点と言われアジアとの交通を意識させる。西大寺駅と新大宮駅の間に拡がるこの地区からは一旦建物はすべて消え去った。僕の父の話ではマムシの巣窟だったと言う。近年、朱雀門、大極殿などが再建されているが、いまだ草と灌木に覆われた広大な平地が広がっている。
その東に列石や船の肋材を思わす斜めの柱に囲まれた屋根のない巨大な舞台が作られた。開演は17時15分、この季節では太陽がちょうど西の生駒山系に没した時刻である。観客席はその残照に向かうように作られている。照明も大切であるから日照は避けなければならない。微妙な時間、方向などすべて周到に考慮されたものだと思う。僕の見た日は曇り空であったので空は薄明かりに包まれていた。観劇中、それはとても高い天井のようにも見えた。始終取り巻く曠野を意識した。半分閉じ、半分開いた空間で劇が進行するのである。舞台に突如闖入する大きな舞台も作られた。そしてこれらは公演終了とともにすべて取り払われるという痛快。
これまでに見た舞踏・劇では、土方巽・芦川洋子や太田省吾の転形劇場が好みであるが、これもそれらに匹敵するものであった。4時間の労は報われた。
亡くなられた主宰松本雄吉氏の遺影に一礼して劇場を後にした。
---------------------------
いつ行けるだろうかと迷っているうちに前売り券は完売し、当日券を求めて2時間前に並んだ。雨もぽつぽつ降ったし、行列嫌いとしては苦行であった。今日は土曜日であったため、混んでいたようだ。話を聞いていると遠くの県から来た人も多い。勤めで無理してきている人も多いようだし、近隣の退職者の僕としては、ウィークデイに来るべきだった。
しかし当日券購入者として前の通路に案内されたため、目や耳の弱った身としてはかえって好都合であった。スポンジの「座布団」も貸していただけた。しかし2時間平らなところに座っていることは、そこそこ苦痛である。年をとると同じ姿勢をとっている場合、床に触れて体重がかかる部分が痛くなってくるのである。またもし雨が降ってきても、他の人の視線を遮るため、傘はさしてはいけないそうである。かっぱを用意していないので危ないところであった。そんな注意はネットでも徹底していただきたい。終了後、写真を取るためにカバンを舞台において注意を受けた。これの意味はわからなかったが、舞台は役者の魂であるからだろうか。
舞台の外に作られる屋台も面白そうだがパスした。

維新派の公演「アマハラ」を見た。ダンス劇というのだろうか、この種のものを見たことは数えるほどしか無い。しかし期待を超える面白さであった。アート、文学、(数学以外の)学問、いずれに対しても素人で、見た作品は非常に少ない。劇の批評も真面目に読んだことはない。いつものとおり少ない例によって感じたことを述べる。
テーマは日本がアジアと不離不分のものであることの確認であろう。これは「東アジア文化都市2016奈良市」の行事であるが、2009年公演「台湾の、灰色の牛が背のびをしたとき」の題にすでに登場している。
見るところ、この劇団は徹底して人の間に距離をおいている。等間隔に並べることもしばしば。人は絡ませるのでなく、配置されるのである。(維新派ホームページ)をぜひ大画面で見ていただきたい。
僕は自分の創作を行うときは徹底して屋内密室派であるが、人と交流する場としては屋内が嫌いである。距離のおける屋外なら雄弁になれる。維新派の距離のことは、見終わりこの報告を書く段になって初めて気がついたのであるが、僕としては無意識的にそこが気に入っていたのである。
この人の間の距離はせりふにも現れている。劇の定番の応答はないのである。「あなたは何処にいるか」「フィリピンのバギオ」といった簡単な応答はあるのだが、論戦はない。説得し、あるいは学ぶというより、単に発語し感得する淡白なコミュニケーションである。ダンスでは当然と言われればそうであるが、ダンスよりは言葉に重きをおいている。民族区別的言い草となるが、北方よりも東南アジア的志向と言えようか。このさわやかさも僕が無意識的に選ぶ因となっている。こうした理屈、いささか自己撞着気味であるが。
この淡白さによって言葉の論理構造の必要性が減る。維新派はその代わりに単語の音色とリズムにこだわっている。盛り上がるところでは大きな装置の重低音がバックアップする。
アジアとのつながりがテーマであるから、舟を操るイメージや、トランクを持った移動のイメージはよく用いられるが、もう一つ目立つのは、労働を取り入れたダンスである。セバスチャン・サルガドの写真に見るような、重い労働の所作が踊りとなっている。
もう一つ、劇団のプリンシプルであろうが、強調すべきことがある。舞台の構築される場所である。今回は平城宮址(漢字制限によって平城宮跡とされた)である。平城京はシルクロードの終着点と言われアジアとの交通を意識させる。西大寺駅と新大宮駅の間に拡がるこの地区からは一旦建物はすべて消え去った。僕の父の話ではマムシの巣窟だったと言う。近年、朱雀門、大極殿などが再建されているが、いまだ草と灌木に覆われた広大な平地が広がっている。
その東に列石や船の肋材を思わす斜めの柱に囲まれた屋根のない巨大な舞台が作られた。開演は17時15分、この季節では太陽がちょうど西の生駒山系に没した時刻である。観客席はその残照に向かうように作られている。照明も大切であるから日照は避けなければならない。微妙な時間、方向などすべて周到に考慮されたものだと思う。僕の見た日は曇り空であったので空は薄明かりに包まれていた。観劇中、それはとても高い天井のようにも見えた。始終取り巻く曠野を意識した。半分閉じ、半分開いた空間で劇が進行するのである。舞台に突如闖入する大きな舞台も作られた。そしてこれらは公演終了とともにすべて取り払われるという痛快。
これまでに見た舞踏・劇では、土方巽・芦川洋子や太田省吾の転形劇場が好みであるが、これもそれらに匹敵するものであった。4時間の労は報われた。
亡くなられた主宰松本雄吉氏の遺影に一礼して劇場を後にした。
---------------------------
いつ行けるだろうかと迷っているうちに前売り券は完売し、当日券を求めて2時間前に並んだ。雨もぽつぽつ降ったし、行列嫌いとしては苦行であった。今日は土曜日であったため、混んでいたようだ。話を聞いていると遠くの県から来た人も多い。勤めで無理してきている人も多いようだし、近隣の退職者の僕としては、ウィークデイに来るべきだった。
しかし当日券購入者として前の通路に案内されたため、目や耳の弱った身としてはかえって好都合であった。スポンジの「座布団」も貸していただけた。しかし2時間平らなところに座っていることは、そこそこ苦痛である。年をとると同じ姿勢をとっている場合、床に触れて体重がかかる部分が痛くなってくるのである。またもし雨が降ってきても、他の人の視線を遮るため、傘はさしてはいけないそうである。かっぱを用意していないので危ないところであった。そんな注意はネットでも徹底していただきたい。終了後、写真を取るためにカバンを舞台において注意を受けた。これの意味はわからなかったが、舞台は役者の魂であるからだろうか。
舞台の外に作られる屋台も面白そうだがパスした。















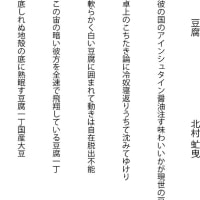
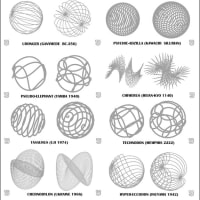













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます