
<詩人の逝去>
近年友人の詩人を続けて喪った。いずれも因縁浅からぬ人たちである。主として自分との関係で述べることをお許し頂きたい。
まず何よりも、本日2015年6月26日に詩人の寺岡良信さんが亡くなられた。一昨日に家族で面会に行ったところである。彼はとても元気があり、自分で歩き、心は落ち着いていたようである。「身辺をすべて整理でき、病院の『緩和ケアセンター』という素晴らしいところを得て、自分も模範生として過ごしている」と語ってくれた。
彼は俳句にも詳しく、「北の句会」に投句し、元気なときは出席もしていた。詩人、大橋愛由等氏の経営する神戸のスペイン料理店「カルメン」によく姿をあらわし、そこを根城とする詩誌「めらんじゅ」の編集長を続けていた。彼の詩は、とても美しくしかもペシミスティックであった。言葉は端正で、自ら反時代的であると称していた。実際そういう点で彼を凌ぐ詩を見たことがない。
出版した詩集は『ヴォカリーズ』、『焚刑』、『凱歌』、『龜裂』(いずれもまろうど社)の4冊である。彼の詩の一端は、「北の句会」への最後の投句である次の句からうかがうこともできるであろう。
波が来て人魚の檻をあらふ夏 寺岡良信
石棺のミイラの吐息野ばら散る 寺岡良信
このように紹介すると、高踏派の選民意識のある人と思われるかもしれないが、事実はまったく逆であった。一昨日、彼の述べたところでは、父親は沖仲仕を仕事とし、家には喧嘩もいとわないあらくれの人々が出入りしていたという。自分も喧嘩早いと言って笑った。彼は神戸で育ち、詩は、海や港、船のイメージに満ちている。彼自身は高校の教師をしていたが、筋金入りの民主主義者であったと言えばよいだろう。
彼は一昨日、「むかし、北村さんが『寺岡さんはイデオロギーは異なるが、思想は同じだね』と言った」と述べた。たしかにペシミストという点で似ていると思う。そして、「いま、『水際の焚火操る偽空也(虻曳)』が好きだ」と述べてくれた。私の定型短詩集『模型の雲』(冨岡書房)を家の枕辺に置いていたそうである。
私の詩集を気に入ってくれる人は少ないが、もう一人は新しい詩的な川柳の流れを興した石部明さんである。流れを起こす大胆さを持ちながらながら、とても豊かな否定性、死のイメージを展開していた。そうしたところで、私とお互いに共鳴できたのだと思う。俳句作り始めのころ、「北の句会」でいろいろご教示いただいた。しかし、癌で危なくなった私を追い抜いて、2012年に亡くなられた。私はネットに短文に私から見た石部像を書いている。ちょうど書き上げた頃に亡くなられた。
月光を浴びる荒野のめし茶碗 石部 明
そしてもう一人が若い時からの友人、社会学者村上直之さんである。彼は高校の頃から詩集を出す多才な人で、私の上述の詩集の「跋」を書いていただいた。八面六臂、とても元気であったが、1年前に急逝した。死の病が発覚した頃、急に「あなたの詩集の兄弟編のようなものを作り、書棚に並べたい」と言って、やはり定型短詩集とする『ゆきくれて』(冨岡書房)を苦痛を押してベッドでiPadを用いて書き上げた。同時に社会学のラベリング理論の定番であるカイ・T.エリクソン著『あぶれピューリタン逸脱の社会学』(現代人文社)岩田強氏との共訳で増補を行っている。これらの完成はわずかに存命中に間に合わなかったが。このブログの短文参照。
浅き夜の夢の余白の花むくげ 村上直之
どの方も独自の流儀で生きる腹のすわった詩人であり、とても素晴らしい仕事を成し遂げた人たちである。でも幾分かは、同じ空気を吸うことのあった同志と感じるだけに、寂しい。今年亡くなられた俳人・化学者の和田悟朗先生を加えると、私の詩集に好意を持っていただいた数少ない4人が、この3年間で鬼籍に入られた。妙な因果を感じる。
近年友人の詩人を続けて喪った。いずれも因縁浅からぬ人たちである。主として自分との関係で述べることをお許し頂きたい。
まず何よりも、本日2015年6月26日に詩人の寺岡良信さんが亡くなられた。一昨日に家族で面会に行ったところである。彼はとても元気があり、自分で歩き、心は落ち着いていたようである。「身辺をすべて整理でき、病院の『緩和ケアセンター』という素晴らしいところを得て、自分も模範生として過ごしている」と語ってくれた。
彼は俳句にも詳しく、「北の句会」に投句し、元気なときは出席もしていた。詩人、大橋愛由等氏の経営する神戸のスペイン料理店「カルメン」によく姿をあらわし、そこを根城とする詩誌「めらんじゅ」の編集長を続けていた。彼の詩は、とても美しくしかもペシミスティックであった。言葉は端正で、自ら反時代的であると称していた。実際そういう点で彼を凌ぐ詩を見たことがない。
出版した詩集は『ヴォカリーズ』、『焚刑』、『凱歌』、『龜裂』(いずれもまろうど社)の4冊である。彼の詩の一端は、「北の句会」への最後の投句である次の句からうかがうこともできるであろう。
波が来て人魚の檻をあらふ夏 寺岡良信
石棺のミイラの吐息野ばら散る 寺岡良信
このように紹介すると、高踏派の選民意識のある人と思われるかもしれないが、事実はまったく逆であった。一昨日、彼の述べたところでは、父親は沖仲仕を仕事とし、家には喧嘩もいとわないあらくれの人々が出入りしていたという。自分も喧嘩早いと言って笑った。彼は神戸で育ち、詩は、海や港、船のイメージに満ちている。彼自身は高校の教師をしていたが、筋金入りの民主主義者であったと言えばよいだろう。
彼は一昨日、「むかし、北村さんが『寺岡さんはイデオロギーは異なるが、思想は同じだね』と言った」と述べた。たしかにペシミストという点で似ていると思う。そして、「いま、『水際の焚火操る偽空也(虻曳)』が好きだ」と述べてくれた。私の定型短詩集『模型の雲』(冨岡書房)を家の枕辺に置いていたそうである。
私の詩集を気に入ってくれる人は少ないが、もう一人は新しい詩的な川柳の流れを興した石部明さんである。流れを起こす大胆さを持ちながらながら、とても豊かな否定性、死のイメージを展開していた。そうしたところで、私とお互いに共鳴できたのだと思う。俳句作り始めのころ、「北の句会」でいろいろご教示いただいた。しかし、癌で危なくなった私を追い抜いて、2012年に亡くなられた。私はネットに短文に私から見た石部像を書いている。ちょうど書き上げた頃に亡くなられた。
月光を浴びる荒野のめし茶碗 石部 明
そしてもう一人が若い時からの友人、社会学者村上直之さんである。彼は高校の頃から詩集を出す多才な人で、私の上述の詩集の「跋」を書いていただいた。八面六臂、とても元気であったが、1年前に急逝した。死の病が発覚した頃、急に「あなたの詩集の兄弟編のようなものを作り、書棚に並べたい」と言って、やはり定型短詩集とする『ゆきくれて』(冨岡書房)を苦痛を押してベッドでiPadを用いて書き上げた。同時に社会学のラベリング理論の定番であるカイ・T.エリクソン著『あぶれピューリタン逸脱の社会学』(現代人文社)岩田強氏との共訳で増補を行っている。これらの完成はわずかに存命中に間に合わなかったが。このブログの短文参照。
浅き夜の夢の余白の花むくげ 村上直之
どの方も独自の流儀で生きる腹のすわった詩人であり、とても素晴らしい仕事を成し遂げた人たちである。でも幾分かは、同じ空気を吸うことのあった同志と感じるだけに、寂しい。今年亡くなられた俳人・化学者の和田悟朗先生を加えると、私の詩集に好意を持っていただいた数少ない4人が、この3年間で鬼籍に入られた。妙な因果を感じる。














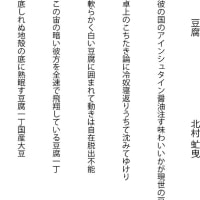
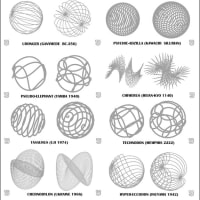












友人に話すことには、それぞれ「この人でないと」というところがあります。それがだんだん欠けてゆくのはさびしいことです。
まだ梅雨が続いています。くれぐれもお体を愛おしまれお元気でお過ごし下さい。