こんにちは。
トロピカーナです。

久しぶりの学スタブログです。
今回は先週行ってきた環境コースの環境調査実習について紹介します。
行ってきたのは平山城址公園。
緑いっぱいで都会にあるとは思えない場所でした。


そこでは木々の種類や草花の特徴などを学んできました。
例えば、雑木林の木は主にコナラ、クヌギ、エゴ、シデノキで構成されているそうです。
一番多いのはコナラで、雑木林の7割近くを占めているとか。
縦の割れ目が目立つのが特徴で、秋にはドングリが取れます。

他にもクヌギという木があります。
この木は甘い樹脂が取れ、カブトムシなどの昆虫が集まりやすいです。
コルク質の木肌が特徴です。

画像が小さくて分かりにくいとは思いますが、違いがなんとなーく分かりますか?
同じような縦縞の木でも、特徴がそれぞれありますね。
また、公園に辿り着くまでの間にも、道端にある草花の解説がありました。
例えば、黄色い花が咲くカタバミという植物。
街中でも時々見かけるこの植物にはシュウ酸が含まれていて、葉を複数重ねて黒くなった10円玉を擦るとピカピカの新品のような輝きを取り戻します。

他にはワルナスビ。
その名の通り、ナスに似た花と実をつけますが実は小さく、棘を持っているのが特徴です。

また、写真は撮れませんでしたが、ガビチョウという鳥の紹介もありました。
外来種の一種で鳩よりも体長が小さく、全体茶色い羽根に白ぶちの目が特徴です。
漢字で書くと「画眉鳥」で、さえずりがとにかくうるさいのが印象に残りました。
誰かが喋っていると、その声に対抗してさえずってくる面倒さ。
次にお目にかかる時は、一枚写真をぜひ撮りたいですね。
最後にチラリと授業風景。


公園に行きつくまでの道のりが険しかったせいか、広い公園の中でも縦一列の行動になりやすかったですね(笑)
ちなみに、その前に通っていた道がこちら。

細くて、草木が覆い茂って、虫もいて・・・
フィールドワークの過酷さを知った瞬間でしたね。
なんだかんだ終了した実習の感想としては、とても楽しかったです。
日常では体験できないものだからこその楽しさがあったと思います。
近々機会があれば、またブログに載せたいです。
実験を仕事にする
東京バイオテクノロジー専門学校
トロピカーナです。

久しぶりの学スタブログです。
今回は先週行ってきた環境コースの環境調査実習について紹介します。
行ってきたのは平山城址公園。
緑いっぱいで都会にあるとは思えない場所でした。


そこでは木々の種類や草花の特徴などを学んできました。
例えば、雑木林の木は主にコナラ、クヌギ、エゴ、シデノキで構成されているそうです。
一番多いのはコナラで、雑木林の7割近くを占めているとか。
縦の割れ目が目立つのが特徴で、秋にはドングリが取れます。

他にもクヌギという木があります。
この木は甘い樹脂が取れ、カブトムシなどの昆虫が集まりやすいです。
コルク質の木肌が特徴です。

画像が小さくて分かりにくいとは思いますが、違いがなんとなーく分かりますか?
同じような縦縞の木でも、特徴がそれぞれありますね。
また、公園に辿り着くまでの間にも、道端にある草花の解説がありました。
例えば、黄色い花が咲くカタバミという植物。
街中でも時々見かけるこの植物にはシュウ酸が含まれていて、葉を複数重ねて黒くなった10円玉を擦るとピカピカの新品のような輝きを取り戻します。

他にはワルナスビ。
その名の通り、ナスに似た花と実をつけますが実は小さく、棘を持っているのが特徴です。

また、写真は撮れませんでしたが、ガビチョウという鳥の紹介もありました。
外来種の一種で鳩よりも体長が小さく、全体茶色い羽根に白ぶちの目が特徴です。
漢字で書くと「画眉鳥」で、さえずりがとにかくうるさいのが印象に残りました。
誰かが喋っていると、その声に対抗してさえずってくる面倒さ。
次にお目にかかる時は、一枚写真をぜひ撮りたいですね。
最後にチラリと授業風景。


公園に行きつくまでの道のりが険しかったせいか、広い公園の中でも縦一列の行動になりやすかったですね(笑)
ちなみに、その前に通っていた道がこちら。

細くて、草木が覆い茂って、虫もいて・・・
フィールドワークの過酷さを知った瞬間でしたね。
なんだかんだ終了した実習の感想としては、とても楽しかったです。
日常では体験できないものだからこその楽しさがあったと思います。
近々機会があれば、またブログに載せたいです。
実験を仕事にする
東京バイオテクノロジー専門学校
















 春休みモードに馴染み過ぎて、学校が始まった時に身体がついていけるか心配に感じています。
春休みモードに馴染み過ぎて、学校が始まった時に身体がついていけるか心配に感じています。
 雨の日が多いですよね。
雨の日が多いですよね。 。
。
 や自転車
や自転車 に対する意識や付近を走行している自動車への注意など、運転の真の大変さを知りました。
に対する意識や付近を走行している自動車への注意など、運転の真の大変さを知りました。





 と
と 自動車
自動車 の免許取得。
の免許取得。

 はあいかわらず厳しいですね。
はあいかわらず厳しいですね。

 期末テスト
期末テスト を乗り切れるよう、勉学にも励まないと・・・。
を乗り切れるよう、勉学にも励まないと・・・。
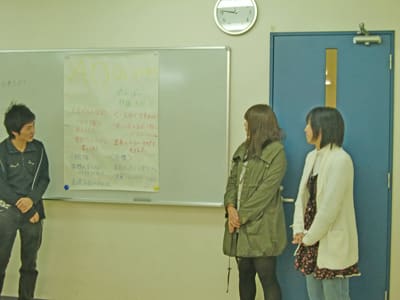







 が取り上げられているのを見ました。
が取り上げられているのを見ました。 の予防にも役立ちます。
の予防にも役立ちます。 寒くなったり
寒くなったり 暖かくなったり・・・。
暖かくなったり・・・。 です。
です。 はぁ。
はぁ。
