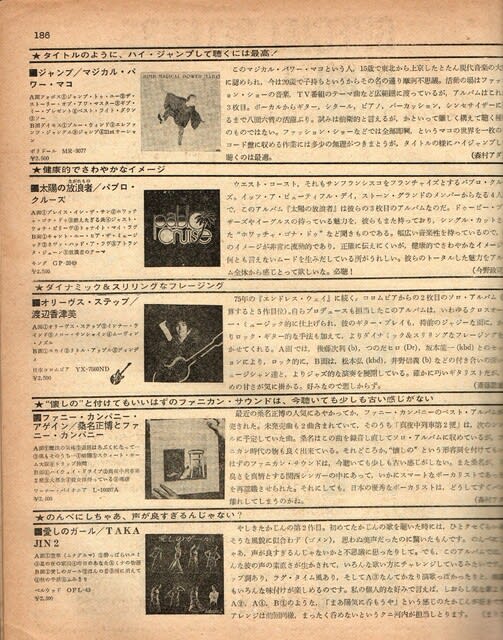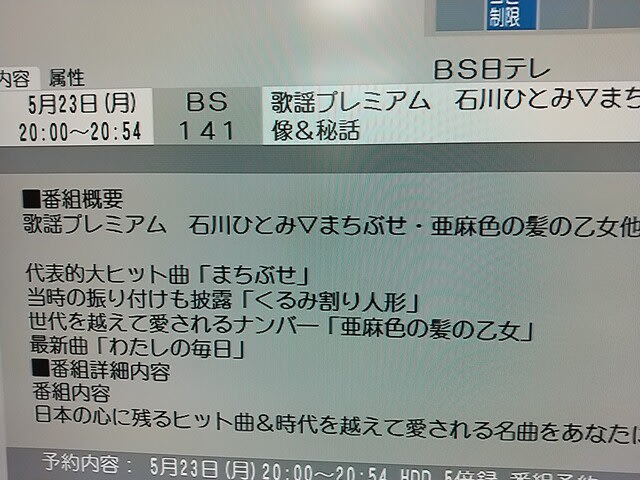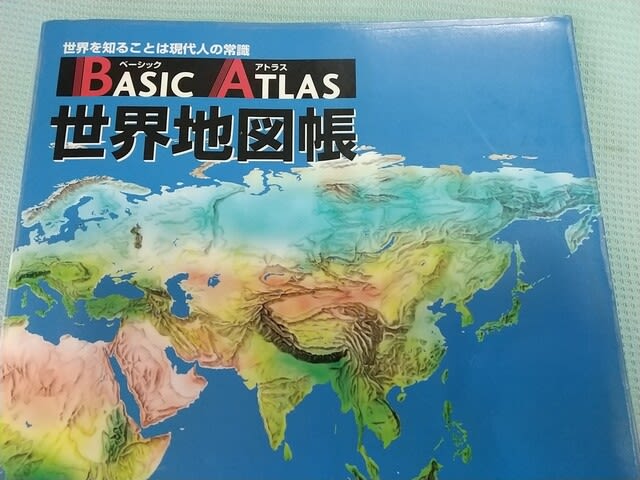NHKで放送した「本土復帰50年SP うちなーポップスの半世紀」という番組を見ました。番組表で見た「南沙織」の文字に反応したのですが、出てきたのは紅白歌合戦初出場の映像でした。1971年なのでまだ本土復帰前ですね。そしてほぼ2コーラス流れました。画質も音質もまずまず良かったのですが、さすがにNHKには映像残ってるんですね。それにしても、あれで当時は「歌が下手」という批判もあったということは、歌謡界全般がレベルが高かったのでしょう。
そして次に出てきたのがフィンガー5の「学園天国」。これがなんと1974年の東京音楽祭出場時のもので、「映像提供:TBS」というクレジットもありました。彼らは年齢の問題で紅白には出てなかったのでしょうか。
何がどうかというと、東京音楽祭の映像も残ってるなら全編公開して欲しいと願うものであります。1974年にどういう人が出てたのかは知りませんが、こうやって断片的な映像を見るたびに「このまま塩漬けにしておいて誰のためになるの?」と歯がゆくてなりません。有料のオンデマンドでもいいので、なんとか見られるようにして欲しいものです。権利だの許可だのという話があるのはわかりますが、文化的な資産であるのは間違いないので、その辺を克服できるようにならないでしょうか。実際、今の世の中はいつどこで戦争が起きるかわからないし、大きな災害が起きるかもわかりません。「いつかそのうち」「機会があれば」なんて言ってると永久にそういう機会はないのかもしれないと考えるのが人情というものです。
それで、沖縄の音楽というとコンディショングリーンもちょびっと出たし、紫の演奏している映像なんてのは私は初めて見ました。あとは喜納昌吉&チャンプルーズ、安室奈美恵、MAX、SPEED、ネーネーズ、佐渡山豊、りんけんバンド、BEGIN、HY、オレンジレンジ、モンゴル800、Kiroroなどなど、色々見ました。
こうやってあらためて見ると、沖縄というのは明らかに本土とは文化とか生活様式が違うと感じるし、そもそも言葉からして違うので本土復帰の意味をあれこれ考えさせられました。沖縄については基地問題とかいろいろ思うところはありますが、ここでは書きません。本土復帰50年を記念したイベントが続いたここ数週間だけじゃなくて、常に色々考えてできることをしていかねばなりませんね。
それはそうと、紅白と東京音楽祭の映像はすべて出すべし!とNHKとTBSには要望したいです。放送局というのはどこを向いて誰のために仕事をしてるんだか。まったくもう。