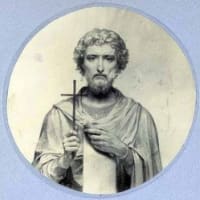『宋朝とモンゴル 世界の歴史6』社会思想社、1974年
11 悲劇の朝鮮半島
5 反逆と抵抗

井上靖の『風涛(ふうとう)』は、モンゴルの圧力の前に、高麗の人々がいかに苦しんだか、その間の動きを克明につづったものである。
小説のかたちをとっているけれども、正確な記録にもとづき、史実に即して、えがかれている。
ともあれ高麗は、フビライが日本に目をむけたことによって、ふたたび受難の時代をむかえたのであった。
フビライの詔書をみると、当然のことながら、みずから「大蒙古国皇帝」と袮し、日本の君主は一段ひくく「日本国王」とよんでいる。
それだけでも日本が、モンゴルの申しいれを拒絶することは、明らかであった。
かねてから日本の天皇は、中国の皇帝にむかって対等の礼をとろうとしてきたし、高麗の国王にむかっては朝貢の礼をもとめてきた。
その日本が、尊大なモンゴルの詔書を受けいれるはずはない。
日本が拒否すれば、モンゴル軍が出動するであろう。
その軍は高麗を通過する。高麗には、ふたたびモンゴル軍が駐留し、そして属国である以上は、軍役の負担を命ぜられる。
いや、派兵も命ぜられるであろう。
どれをとっても、疲弊した高麗には堪えられない。
ここにおいて高麗は、さまざまの策をもちいた。
まずモンゴルの国使が、日本に到達できないよう、工作する。
風涛がはげしいから、というのが理由であった。
しかしフビライの詔書には、「風涛の険阻なるをもって、辞となすことなかれ」と命じている。これは失敗した。
ついで高麗は、国王の名をもって日本へ使者をおくり、モンゴルの申しいれを受けいれるように勧告した。
これも日本が、受けつけない。燕京と江都と、そして高麗と日本との間に、何回もの使者が往復した。
なんの進展もなかった。
そうしたとき、すなわち至元六年(一二六九)六月、江都の宮廷に大事件がおこった。
国王が力づくで退位させられたのである。将軍の林衍(りんえん)は、かねてから元宗のおぼえが悪かった。
そこで元宗を廃し、玉弟の安慶公を国王に立てた。
これを知って、フビライは怒った。
属国の臣たるものが、宗主国のゆるしもえぬまま、かってに王の廃立をおこなうとは何ごとか、というのであった。
討伐の兵もさしむけるという。
林衍も屈して、十一月には元宗を復位させた。
そして元宗は、事情を釈明するために、またしてもフビライのもとへおもむかねばならなかった。
それだけではない。
今度は西北の地方で兵乱がおこった。崔坦(さいたん)という者が、林衍を討つと称して兵をあげた。
そして西北の大部分をおさえると、モンゴルに対して軍の進駐を要請したのである。
モンゴル軍の力によって、自分の勢力を保持しようとしたのであった。
フビライは、その願いをみとめた。軍に出動を命ずるとともに、高麗の西北部(平壤をふくむ)を、ことごとくモンゴルの領土に編入してしまった。
こうして高麗は、その領土の一部を失った。
燕京についた元宗は、西京の還付をねがった。
しかし無視された。江都から開京へうつるために、若干の兵を借りたいと申しでた。
これに対するフビライの答えは、大部隊を進駐させようというものであった。
逆都のことは、もはや猶予をゆるされない。
すでに年は改まっていた(一二七〇)。
その五月末、開京までもどった元宗は、還都のことを命じた。
しかし江都には、島を出ることに反対する勢力があった。島の守備軍たる三別抄(さんべつしょう)である。
かねてからモンゴルとの抗戦にしたがい、モンゴルには激しい敵愾心をいだいていた。
いま、モンゴルの大軍が進駐してきている。島を出れば、どのようになるか。
三別抄は、反モンゴルの旗をかかげて、いっせいに立った。
大官たちは、国王を出むかえるため、開京におもむいている。その子女たちだけが島にのこっていた。江都の官署をおさえた三別抄は、公私の財物をうばったうえ、島内の舟艇をことごとく集めて南方の海上に去った。
高官の子女たちは、人質として連行した。
痛哭(つうこく)の声が天地にふるったという。
やがて三別抄は、半島の西南端にある珍島を占領する。ここを根拠にして、南部の州県に出没した。
ついで耽羅(たんら=いまの済州島)を攻略した。
高麗の朝廷は、金方慶をつかわして討伐にあたらせたが、あまり成果はあがらない。
三別抄の勢いは、いよいよさかんなまま、その年も暮れた。それというのも、三別抄には民衆の支持があったからである。三別抄が攻めよせると、多くの州県は戦わずに從った。
三別抄に呼応して一揆をおこしたところも、少なくなかった。その鎮圧に、政府は手をやいた。政府の求めによって、モンゴル軍も出動した。
三別抄と、各地の一揆は、モンゴルに屈した政府に、あからさまな反抗をしめしたのであった。
ときに中国におけるモンゴル軍は、南宋への攻撃をつづけている。
そのさなかにあって、至元八年(一二七一)十一月、フビライは新しい国号を立て、「大元」と袮した。
中国の古典『易経(えききょう)』のなかにある「大哉乾元(だいなるか、けんげん)」という句にもとづいて採用したものである。
いまやフビライの帝国は、中国を統治する王朝たることを、はっきりと宣明した。
翌年には国都(いまの北京)の名もあらためて、大都と称する。
高麗では、なお三別抄は耽羅にあり、抵抗をつづけている。
東方においてモンゴルになびかぬものは、耽羅と日本のみであった。
あくまでも日本が通交をこばむなら、元としては兵を出さねばならぬ。
しかし、その前に耽羅をかたづけておかねばならなかった。
三別抄は、その舟艇をしきりに出動せしめ、半島の西方および南方の制海権をにぎっている。
ために海上の輸送はとどこおり、日本へ出兵しようとしても、艦隊を発することが危険であった。
至元九年(一二七二)末、ついに元は耽羅を征することを決した。
すでに高麗には、二千の元軍が駐留している。
これに、三千の軍兵を増派した高麗に対しては、五千の軍兵と、三千の水手を出すことが命ぜられた。
あわせて一万三千という大軍をもって、耽羅における三別抄を討とうというものであった。
翌年(一二七三)二月、元と高麗の軍は、次々に南下していった。
四月、耽羅島へ攻めこんだ。
大軍に寄せられては、さしもの三別抄も敵することはできなかった。
大いに戦ったのち、ついに耽羅はおちいった。
三別抄は抵抗をこころみること、およそ三年にしてほろぼされた。
モンゴルに服属した高麗の朝廷にとって、三別抄は逆徒であったに違いない。
しかし、モンゴル軍による苦しみを、死とともに味わってきた民衆にとって、三別抄は頼もしい味方であった。
彼らの王朝が屈してしまったのち、民衆は三別抄によって、侵略者に対する抵抗をあらわすことができたのである。
それゆえにこそ、三別抄は強かった。
おもうままに、力を発揮することができたのであった。
三別抄が平定されたのち、元は耽羅をその直轄領に編入した。
さきに元は、崔坦の反逆によって、西北部を領土としている。
ここに及んで、高麗の北と南とを、がっしりとおさえたのであった。

11 悲劇の朝鮮半島
5 反逆と抵抗

井上靖の『風涛(ふうとう)』は、モンゴルの圧力の前に、高麗の人々がいかに苦しんだか、その間の動きを克明につづったものである。
小説のかたちをとっているけれども、正確な記録にもとづき、史実に即して、えがかれている。
ともあれ高麗は、フビライが日本に目をむけたことによって、ふたたび受難の時代をむかえたのであった。
フビライの詔書をみると、当然のことながら、みずから「大蒙古国皇帝」と袮し、日本の君主は一段ひくく「日本国王」とよんでいる。
それだけでも日本が、モンゴルの申しいれを拒絶することは、明らかであった。
かねてから日本の天皇は、中国の皇帝にむかって対等の礼をとろうとしてきたし、高麗の国王にむかっては朝貢の礼をもとめてきた。
その日本が、尊大なモンゴルの詔書を受けいれるはずはない。
日本が拒否すれば、モンゴル軍が出動するであろう。
その軍は高麗を通過する。高麗には、ふたたびモンゴル軍が駐留し、そして属国である以上は、軍役の負担を命ぜられる。
いや、派兵も命ぜられるであろう。
どれをとっても、疲弊した高麗には堪えられない。
ここにおいて高麗は、さまざまの策をもちいた。
まずモンゴルの国使が、日本に到達できないよう、工作する。
風涛がはげしいから、というのが理由であった。
しかしフビライの詔書には、「風涛の険阻なるをもって、辞となすことなかれ」と命じている。これは失敗した。
ついで高麗は、国王の名をもって日本へ使者をおくり、モンゴルの申しいれを受けいれるように勧告した。
これも日本が、受けつけない。燕京と江都と、そして高麗と日本との間に、何回もの使者が往復した。
なんの進展もなかった。
そうしたとき、すなわち至元六年(一二六九)六月、江都の宮廷に大事件がおこった。
国王が力づくで退位させられたのである。将軍の林衍(りんえん)は、かねてから元宗のおぼえが悪かった。
そこで元宗を廃し、玉弟の安慶公を国王に立てた。
これを知って、フビライは怒った。
属国の臣たるものが、宗主国のゆるしもえぬまま、かってに王の廃立をおこなうとは何ごとか、というのであった。
討伐の兵もさしむけるという。
林衍も屈して、十一月には元宗を復位させた。
そして元宗は、事情を釈明するために、またしてもフビライのもとへおもむかねばならなかった。
それだけではない。
今度は西北の地方で兵乱がおこった。崔坦(さいたん)という者が、林衍を討つと称して兵をあげた。
そして西北の大部分をおさえると、モンゴルに対して軍の進駐を要請したのである。
モンゴル軍の力によって、自分の勢力を保持しようとしたのであった。
フビライは、その願いをみとめた。軍に出動を命ずるとともに、高麗の西北部(平壤をふくむ)を、ことごとくモンゴルの領土に編入してしまった。
こうして高麗は、その領土の一部を失った。
燕京についた元宗は、西京の還付をねがった。
しかし無視された。江都から開京へうつるために、若干の兵を借りたいと申しでた。
これに対するフビライの答えは、大部隊を進駐させようというものであった。
逆都のことは、もはや猶予をゆるされない。
すでに年は改まっていた(一二七〇)。
その五月末、開京までもどった元宗は、還都のことを命じた。
しかし江都には、島を出ることに反対する勢力があった。島の守備軍たる三別抄(さんべつしょう)である。
かねてからモンゴルとの抗戦にしたがい、モンゴルには激しい敵愾心をいだいていた。
いま、モンゴルの大軍が進駐してきている。島を出れば、どのようになるか。
三別抄は、反モンゴルの旗をかかげて、いっせいに立った。
大官たちは、国王を出むかえるため、開京におもむいている。その子女たちだけが島にのこっていた。江都の官署をおさえた三別抄は、公私の財物をうばったうえ、島内の舟艇をことごとく集めて南方の海上に去った。
高官の子女たちは、人質として連行した。
痛哭(つうこく)の声が天地にふるったという。
やがて三別抄は、半島の西南端にある珍島を占領する。ここを根拠にして、南部の州県に出没した。
ついで耽羅(たんら=いまの済州島)を攻略した。
高麗の朝廷は、金方慶をつかわして討伐にあたらせたが、あまり成果はあがらない。
三別抄の勢いは、いよいよさかんなまま、その年も暮れた。それというのも、三別抄には民衆の支持があったからである。三別抄が攻めよせると、多くの州県は戦わずに從った。
三別抄に呼応して一揆をおこしたところも、少なくなかった。その鎮圧に、政府は手をやいた。政府の求めによって、モンゴル軍も出動した。
三別抄と、各地の一揆は、モンゴルに屈した政府に、あからさまな反抗をしめしたのであった。
ときに中国におけるモンゴル軍は、南宋への攻撃をつづけている。
そのさなかにあって、至元八年(一二七一)十一月、フビライは新しい国号を立て、「大元」と袮した。
中国の古典『易経(えききょう)』のなかにある「大哉乾元(だいなるか、けんげん)」という句にもとづいて採用したものである。
いまやフビライの帝国は、中国を統治する王朝たることを、はっきりと宣明した。
翌年には国都(いまの北京)の名もあらためて、大都と称する。
高麗では、なお三別抄は耽羅にあり、抵抗をつづけている。
東方においてモンゴルになびかぬものは、耽羅と日本のみであった。
あくまでも日本が通交をこばむなら、元としては兵を出さねばならぬ。
しかし、その前に耽羅をかたづけておかねばならなかった。
三別抄は、その舟艇をしきりに出動せしめ、半島の西方および南方の制海権をにぎっている。
ために海上の輸送はとどこおり、日本へ出兵しようとしても、艦隊を発することが危険であった。
至元九年(一二七二)末、ついに元は耽羅を征することを決した。
すでに高麗には、二千の元軍が駐留している。
これに、三千の軍兵を増派した高麗に対しては、五千の軍兵と、三千の水手を出すことが命ぜられた。
あわせて一万三千という大軍をもって、耽羅における三別抄を討とうというものであった。
翌年(一二七三)二月、元と高麗の軍は、次々に南下していった。
四月、耽羅島へ攻めこんだ。
大軍に寄せられては、さしもの三別抄も敵することはできなかった。
大いに戦ったのち、ついに耽羅はおちいった。
三別抄は抵抗をこころみること、およそ三年にしてほろぼされた。
モンゴルに服属した高麗の朝廷にとって、三別抄は逆徒であったに違いない。
しかし、モンゴル軍による苦しみを、死とともに味わってきた民衆にとって、三別抄は頼もしい味方であった。
彼らの王朝が屈してしまったのち、民衆は三別抄によって、侵略者に対する抵抗をあらわすことができたのである。
それゆえにこそ、三別抄は強かった。
おもうままに、力を発揮することができたのであった。
三別抄が平定されたのち、元は耽羅をその直轄領に編入した。
さきに元は、崔坦の反逆によって、西北部を領土としている。
ここに及んで、高麗の北と南とを、がっしりとおさえたのであった。