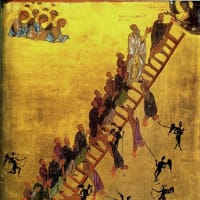『アジア専制帝国 世界の歴史8』社会思想社、1974年
16 オスマン・トルコ
5 トルコ軍の花形
オスマン勢力の強大な軍事力の秘密は、どこにあったのだろうか。
こうして疑問をいだいたものが、すでに、いまから五百余年のむかしにあった。
イタリア人フランチェスコ・フィレルフォである。
かれは、オスマン・トルコの脅威におびえるコンスタンチノープルの城壁の一角にたたずんで、その思いにふけっていた。
オスマンの軍隊をこれほど強力にしたものは、いったい何なのか。――これが、かれの解こうとしていた謎であった。
そのあげく、かれは、解答をイェニチェリ軍団のなかに見い出した。
オスマン軍は、ごくはじめには騎兵だけから成っていた。
それがバルカン半島に進出すると、都市の攻撃や占領地域での駐屯、国境の警備などにあたる常備の歩兵軍団が必要になってきた。
そこで一つの方法として、ヨーロッパで征服した地域のキリスト教徒の子弟を、定期的に強制徴集してイスラムに改宗させ、厳格な軍事訓練をほどこした。
こうしてスルタンに絶対忠誠をちかう兵士にしたてあげたのち、スルタンの親衛隊に編入した。
これが、トルコの各種の歩兵軍団のうち、その精鋭をほこったイェニチェリ(新軍)軍団である。
徴集にあたっては、家柄がよくて健康、しかもハンサムで、うぶな独身者がえらばれた。
シラクモやタムシ(どちらも皮膚病)などの病気もちや、大都市に住んだことのあるすれっからし、商人の子弟などは除外された。
イェニチェリ兵は、スルタンの親衛兵であるだけでない。
身分としては奴隷で、スルタンの身辺の雑事をもおこない、一定の給与を支払われた。
この制度は、オスマンの軍隊を強化念せ、キリスト教臣民のイスラム化をおしすすめただけでなく、征服地のキリスト教徒をオスマン政権につなぎとめておく役割をも果たした。
なんとなれば、イェニチェリ兵は一種の人質でもあったからである。
イェニチェリ制は、キリスト教徒から「悪魔の思いつき」「人間税」として非難された。
しかし、その兵士はいろいろの特権をあたえられていた上に、宮廷にはいって高官につくものもあらわれたため、みずからすすんで子弟を提供するものもあった。
イェニチェリ軍団は、コンスタンチノープルの占領、エジプトの征服、ヨーロッパヘの遠征などに多くの武勲をたて、まさに、数あるオスマン軍団のなかでも、その花形であった。
しかし、それもせいぜい十七世紀前半までのことであった。
本来の選抜規定が守られなくなるにつれて、無頼の徒がこれに加わり、スルタンの廃立や政策に干渉し、反乱や紛争の種子(たね)をまくことが多くなってきたからである。
これは、忠実な働き蜂がひとたび狂いだすと、手に負えなくなるのに似ているともいえようか。
一八二六年、革新の意気にもえるマフムト二世がこれを廃止したのは、けだし当然の処置であった。
現在のトルコ語で「大鍋をひっくりかえす」というと、「反乱する」ことを意味する。
これはイェニチェリ軍団が、つねに野戦料理につかう大鍋を連隊旗がわりにもち歩き、不平不満がつのると反乱をおこして、この大鍋をひっくりかえし、大きい木匙(きさじ)でこれをたたいたことに由来している。