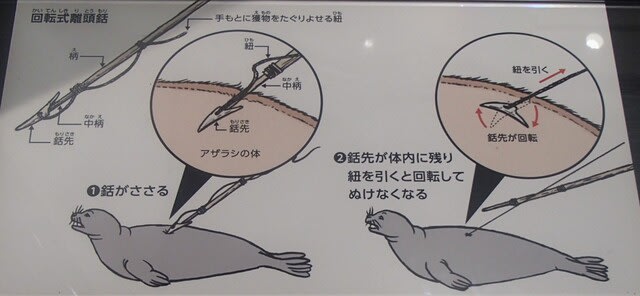北海道立埋蔵文化財センター。北海道江別市西野幌。
2022年6月23日(木)。
札幌市野幌の北海道博物館から北隣にある江別市の北海道立埋蔵文化財センターへ向かい、15時30分過ぎに着いた。


後期旧石器時代。細石刃。木古内町新道4遺跡。
遺跡は津軽海峡に注ぐ木古内川の右岸、標高20m前後の段丘縁辺に立地する。遺跡はほぼ東西に700〜800mにわたり広がっており、後期旧石器時代および縄文時代早期〜晩期の遺構・遺物が多数検出されている。旧石器時代の遺物は、D地区から掻器・削器・彫刻刀形石器・石刃・細石刃・細石刃核など約24,000点が出土した。これらは細石刃文化に属するもので、石材は黒曜石24点(産地の判明したものは赤井川産)のほかは、頁岩で、接合により多数の原石に復元され、細石刃の生産、細石刃核の製作過程が明らかになった。
細石刃文化は、日本列島を含む東アジアからアラスカにかけて広い地域に分布しており、起源はシベリア方面に求められ、およそ2万4000年前に北海道に出現し、2万年前以降には道内各地で細石刃を出土する遺跡が急増する。さらに、この数千年後には本州へ波及した。


暁式土器。縄文時代早期(約9千年前)の土器。帯広市暁遺跡から命名。約9千年前~8千5百年前ころ、十勝を含む東北海道地域で盛行した。表面にあまり模様をつけず、底が平らで、底面にホタテ貝のあとが付けられたことに特徴がある。
沼尻式土器。貝殻を押しつけたり引きずったりして施文した文様を特徴とする貝殻文・条痕文土器のグループで、釧路市沼尻遺跡で出土する条痕文のある平底土器。道南西部では土器の底がとがる尖底土器が中心となるのに対し、道東部では平底土器になる。平底土器は液体や食糧などを入れるのに用いられたもので、尖底土器は煮炊き用として使用された。
縄文時代早期後半の土器。


東釧路Ⅲ式土器。薄手の平底土器。縄文時代に入って縄文の文様がもっとも発達した時で縄や紐を転がしたり、押し付けたりして上から交互に向きを変えて、細い縄文がつけられている。北海道内に広く分布した。
千歳市キウス5遺跡。キウス5遺跡は、石狩低地帯東辺の馬追(まおい)丘陵から西流するキウス川右岸の丘陵下端部とキウス川旧河道の谷底平野に立地する。縄文時代中期後半の竪穴住居跡が多数発掘された。遺物は土器が多く石器は少量である。土器は道南地方のノダップ2式や東北地方の最花式(大木式系)が出土している。他の時期では、後期旧石器時代の忍路子型細石刃核を伴う石器群をはじめ旧石器時代から縄文時代・続縄文時代・擦文時代・アイヌ期とすべての時期の遺物が混在して出土している。
世界遺産・千歳市キウス周堤墓周辺の縄文遺跡群。住居群などの集落的な様相は縄文時代早期中葉に現れる。イカベツ2遺跡(暁式期、虎杖浜式期)、キウス5遺跡(暁式期)、キウス9遺跡(東釧路Ⅲ式期)で竪穴住居(群)が検出された。キウス9遺跡では90点以上の石刃鏃が出土した。
早期後葉の住居群はキウス7・キウス4・キウス5の各遺跡ほかで見られる。前期前半ではキウス5遺跡で急斜面に40軒以上の竪穴が密集していたほか、土坑墓が検出された。キウス4遺跡では西側低位部に大型住居がある。
中期後半にはキウス4・キウス5・キウス7遺跡に集落が分布し、特にキウス5遺跡では多数の住居跡が重複して見つかっている。後期前葉ではキウス7遺跡に竪穴住居・大型貯蔵穴が残され、キウス4遺跡、キウス5遺跡、丸子山遺跡、オルイカ1遺跡にも住居跡がある。後期中葉ではキウス5遺跡の東端部付近から対岸のキウス7遺跡全域に竪穴住居や平地住居、貯蔵穴、土坑墓など多数の遺構が見られ、キウス4遺跡では周堤墓・盛土遺構・道跡・建物跡・水場遺構・貯蔵穴などが確認され、周堤墓20基が群在する東側の墓域と266軒の住居や建物が集まる西側の居住域やそれを囲む南北2列の長大な盛土遺構など、集落構成の全体がほぼ明らかとなった。

中茶路式土器。細い粘土ヒモの貼付けと、細かい縄文が特徴。
コッタロ式土器。細い貼付帯(てんふたい)上に縄の圧痕が施文された土器。

足形付土版。千歳市美々7遺跡。縄文時代早期後半。

玦状耳飾。縄文時代前期。
千歳市美々4遺跡。美々4遺跡は、札幌、苫小牧の中央を流れる美々川の支流、美沢川左岸の台地・斜面部から低位段丘と水付部に広がる。新千歳空港建設のために発掘された。



縄文時代中期の円筒上層式土器。
円筒土器は、円筒状のシンプルなかたちをした土器で、東北地方北半部から北海道南西部にかけて分布し、縄文時代前期の円筒下層式土器、縄文時代中期の円筒上層式土器に区分されるが、さらに前者は円筒下層式a型・b型・c型・d型、後者は円筒上層式a型・b型・c型・d型・e型に細分される。平底深鉢形土器の器形が、口縁がやや広がった円筒形(バケツ形)を呈することに由来している。
円筒土器文化圏の北側の境界線は概ね石狩平野であり、それ以北の道北・道東地方には北筒式土器文化圏、南側の境界線は概ね秋田市-田沢湖-盛岡市-宮古市を結ぶ線で、大木式土器文化圏が広がる。
類似する平底円筒型土器が遼河地域、朝鮮半島北部からアムール川流域、沿海州にかけての広範囲で紀元前6千年紀頃から紀元前2千年紀ごろまでの間に発見されており、ハプログループN1を担い手とする遼河文明との関連が指摘される。

北筒式土器は北海道円筒式土器の略で、縄文時代中期後半に主として道東や道北に分布した、若干の繊維を含んだ円筒形の土器である。口縁は山形突起をもった波状もしくは平縁である。