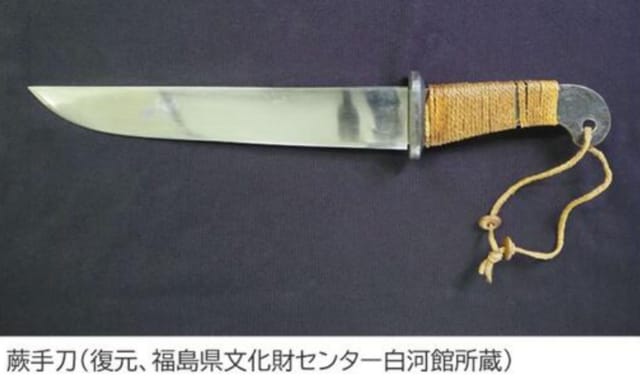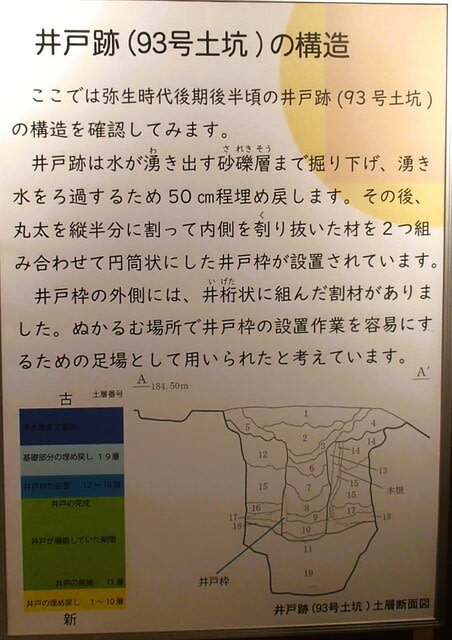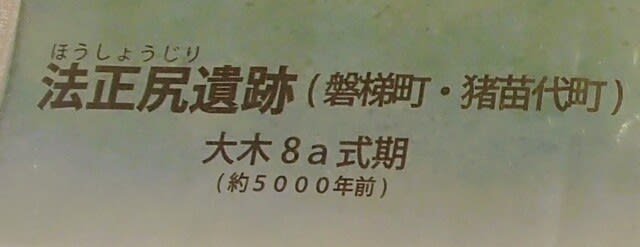境の明神。福島県白河市白坂明神。
2024年6月1日(土)。

福島県文化財センター白河館「まほろん」を見学後、白河関方面へ向かい、国史跡・白河関跡の前に、まず白坂の境の明神を訪れることにして、ポケットパークの駐車場に駐車した。
松尾芭蕉「おくのほそ道」や「曾良随行日記」によれば、松尾芭蕉と河合曽良は、1689(元禄2)年4月20日(陽暦6月7日)朝、那須湯本を立ち、奥州街道の芦野宿(栃木県那須町芦野)、郊外の遊行柳を経由し奥州街道を北上した。そして、上り坂を歩くこと約10キロでたどり着いたのが「境の明神」で、いわゆる「白河の関」、陸奥(みちのく)の入り口である。芭蕉の供をした曽良は「卯の花を かざしに関の 晴れ着かな」と、この時期に白河で咲いていた卯の花を詠み込んでいる。



曽良日記には「寄居村有。是ヨリハタ村ヘ行ハ、町ハツレヨリ右ヘ切ル也。関明神ノ関東ノ方ニ一社、奥州ノ方ニ一社、間二十間計有、両方ノ門前ニ茶ヤ有、小坂也。コレヨリ白坂(宿)へ10丁ホドアリ。古関を尋ねて白坂の町の入口ヨリ右へ切れて旗宿へ行く。廿日の晩泊る。」と記す。
古代の白河関の場所については、1800年(寛政12年)、白河藩主松平定信が文献による考証を行い、その結果、旗宿の現在の白河神社の建つ場所をもって、白河の関跡であると論じ、国史跡にも指定されているが、現在でも正確には特定されているわけではない。
松尾芭蕉の時代でも白河関跡の故地推定地は4か所ほど知られていたらしく、白坂の「境の明神」(新関)から旗宿の「境の明神」(古関)を参詣し、翌朝には関山を訪れている。芭蕉も確信をもって白河関跡を見たとは言えなかったために、「おくのほそ道」では芭蕉は「旅心定(たびごころさだま)りぬ」と記したが、「白河の関」の具体的描写はしていない、という。

境の明神(陸奥側)。福島県白河市白坂明神。
白河から見ると、陸奥側(白河市)には玉津島明神(女神・衣通姫)、下野側(栃木県那須町)には住吉明神(男神・中筒男命)が祀られている。「玉津島明神」と「住吉明神」は、国境の神・和歌の神として知られ、女神は内(国を守る)・男神は外(外敵を防ぐ)という信仰に基づき祀られている。このため、陸奥・下野とも自らの側に「玉津島明神」を祀り、反対側に「住吉明神」を祀るとしている。
社殿については、会津領主蒲生氏により造営され、白河藩主本多能登守により改修されたという記録があるが、現存する社殿は、火災による焼失のため、弘化元年(1844)に再建されたものである。
松尾芭蕉の奥の細道俳諧紀行で、みちのくの第一歩を記した場所として句碑や歌碑が建立されているとともに、大名家や商人から多くの燈籠が寄進されていることから、陸奥・下野の国境である境の明神として重要な場所であったことがうかがえる。
また、神社の向い側には、南部藩出身と伝わる一家が営んだ「南部屋」と称する茶屋跡や、松平定信の時代に建てられたという「従是北白川領」と刻まれた石柱がある。
「関明神」は、両国境に玉津島神社と住吉神社が対に祀られていたことから「関の二所明神」と言われていた。この通称と福島県側にあった茶屋「南部屋」の主人が盛岡出身だったこともあり、南部藩主お抱えの力士が創設した相撲部屋「二所ノ関」の名が付けられたという。
境の明神は、明治時代になって新国道や鉄道が開通すると、それにともない奥州街道の交通量も減り衰退した。明治期の道路拡張などの手が入っていながらもなお、江戸時代における奥州街道沿いの国境の景観を色濃く残し、陸奥国の玄関口としての白河の近世史を語る上で、重要な史跡である。

『白河二所の関碑』。ここは新関とされるが、実は古関であったという説が書かれている。

境の明神(下野側)方向。

国史跡・白河の関。白河神社登り口。白河市旗宿関ノ森。

白河関は、奈良時代から平安時代にかけて、都から陸奥国に通じる東山道の要衝に設けられた関門として歴史上名高く、「みちのく(奥州。現代の東北地方)の玄関口」とされてきた。鼠ヶ関(ねずがせき)・勿来関(なこそのせき)とともに『奥州三関』の1つに数えられる。
所在地は白河神社が祀られる白河市旗宿に比定されており、国の史跡に指定されている。
設置時期は明らかでない。『類聚三代格』承和2年(835年)太政官符では、「白河・菊多(勿来)の関を設置して以来400余年」と見えることから、9世紀前半の835年当時には「5世紀前半に設置された」と認識されていたとみられる。
当初、白河関はヤマト政権が北方の蝦夷に対抗するために建立した前線基地であったが、朝廷の勢力がさらに北進したことで軍事的意義は小さくなり、陸奥国との国境検問所という役割が残ったという。
平安時代以降、律令制度の衰退とともにヤマト政権の軍事的要衝としての白河関の機能は解消していき、白河関は遠い「みちのく」の象徴として和歌の歌枕に選ばれ、文学的感傷をもたらす存在となった。和歌での初出例は、平安中期の平兼盛が詠んだ「たよりあらばいかで都へ告げやらむ今日白河の関は越えぬと」(「拾遺和歌集」別)とされる。
平安末期または鎌倉時代始期の1189年(文治5年)、源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼす奥州合戦の際に、頼朝が白河に達した際に梶原景季に歌を詠むよう命じると、景季は「秋風に草木の露をば払わせて、君が越ゆれば関守も無し」と詠んだ。
関の廃止の後、その遺構は長く失われて、その具体的な位置も分からなくなっていた。1800年(寛政12年)、白河藩主松平定信は文献による考証を行い、その結果、白河神社の建つ場所をもって、白河の関跡であると論じた。

古関蹟碑。松平定信が、寛政12年(1800)に、この場所が白河関跡に間違いないとし、建立した碑が残っている。


古歌碑。
平兼盛、能因法師、梶原景季が白河関を詠んだ歌三首を刻んだ歌碑。
便りあらば いかで都へ 告げやらむ 今日白河の 関は越えぬと (平兼盛)
都をば 霞とともに 立ちしかど 秋風ぞ吹く 白河の関 (能因法師)
秋風に 草木の露を はらわせて 君が越ゆれば 関守もなし (梶原景季)

白河神社。参殿。
白河神社は、白河関跡を境内とし、関の明神、二所関明神とも呼ばれ、古墳時代の315年、白河国造・鹽伊乃自直命(しほいのこじのあたいのみこと)を祀ったのが始まりだという。
元和元年(1615)に伊達政宗が社殿を改築奉納したと言われ、本殿の棟紋に九曜星、縦三引きの紋が刻まれている。
治承4年(1180)、源義経が兄・頼朝の挙兵を知り鎌倉に向かう道中に詣で、境内の松に矢を立て勝利を祈願したと伝わり、祈願をした「矢立の松」が、小さな根元のみの姿となって残っている。
西会津はまたの機会として、白河関跡で今回の福島県の旅を終了し、16時30分頃に栃木県那須塩原市の道の駅へ向かった。